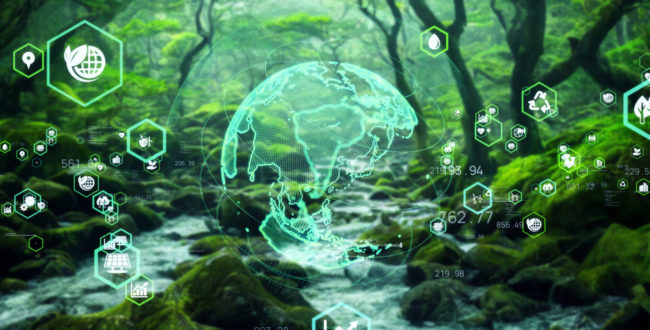ESGフロントライン:TCFD開示の再点検のすすめーーISSB基準・SSBJ基準時代の気候開示
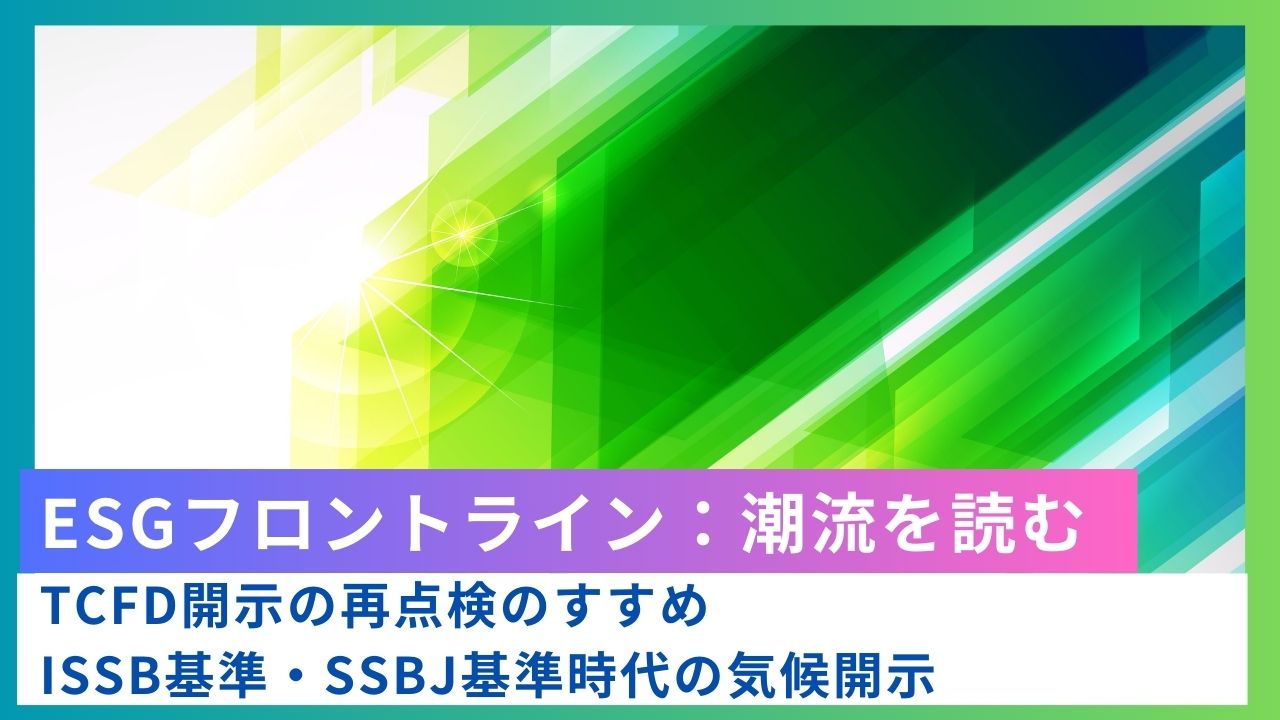
※本記事は、ESG Journal編集部が注目のニュースやトレンドを取り上げ、独自の視点で考察しています。
2025年、サステナビリティ開示にとって大きな転換点となる年になるだろう。というのも、24年に、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が策定した「IFRS S1」「IFRS S2」、2月に公表されたCSRD/ESRS基準の簡素化およびISSB基準との整合性への連携、および国内のSSBJ(サステナビリティ基準委員会)による開示基準の公表など、サステナビリティ開示の基準が基準、統合と標準化に向かっている。
企業は今、投資家・規制当局・市場からの要請を受け、この新たな世界共通ルールに対応することが急務となっている。
気候関連開示の「軸」は依然TCFDに
特に、IFRS S2(気候関連開示)は、2015年に金融安定理事会(FSB)が設立したTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の開示原則をベースに構築されており、すでにTCFDに基づいた開示を行ってきた企業にとっては“国際基準への整合・統合へのスムーズな移行が可能になると考える。
多様な基準が登場する中でも、「気候関連開示の軸」は依然としてTCFDの原則にあるだろう。実際、ISSBのIFRS S2は、TCFDが提示した11の推奨開示項目を基盤として構築されている。
また、TCFDは日本の企業に広く普及している。
IFRS/ISSBが2024年に発表した報告書「Progress on Corporate Climate‑related Disclosures」によれば、2023年度時点で上場企業の82%がTCFDの11の推奨項目のいずれかに沿った開示を実施していた。また、経済産業省によれば、2023年11月時点で日本のTCFD賛同企業は1,488社に達し、世界最多となっている。
ただし、TCFDに基づく開示を行っているといってもその内容は必ずしもISSB基準の要求水準を全て満たしているわけではない点には留意が必要だ。
たとえば、KPMG「The move to mandatory reporting」2024年版にもあるとおり、IFRS S2ではスコープ 3排出量の全範囲にわたる開示や、複数の気候シナリオに基づく財務影響の定量的報告、取締役会による監督や報酬制度への組み込みなど、従来のTCFD対応だけでは不十分な領域が明確に求められている。したがって、既存のTCFD開示を土台としつつ、その精度や範囲を高めることで、ISSB時代の要請にスムーズに対応することが可能となる。
企業にとって最も戦略的かつ効果的な対応は、TCFDの原則に立ち戻り、その開示の精度を高めることである。ISSB基準やCSRD/ESRS基準への対応を進める場合であっても、気候関連開示に関してはTCFD開示という「基盤」があれば十分な移行が実現する可能性が高い。
TCFD開示は「終わったもの」ではなく、「次の開示時代へ進むための出発点」として自社のTCFD開示を再点検することが求められるだろう。
TCFDとは何か──「気候関連情報の型」をつくった開示枠組み
TCFDは、「企業が気候変動にどう備え、どうリスクを管理しているか」を財務インパクトと結びつけて示すフレームワークとして、グローバルに普及してきた。開示の基本構造は次の4つの柱に分類される。
- ガバナンス:取締役会・経営陣による気候リスク監督
- 戦略:気候変動がビジネス戦略・財務計画に与える影響
- リスク管理:リスクの特定、評価、対応プロセス
- 指標と目標:GHG排出量、ネットゼロ目標、KPI等
加えて、TCFD開示ではシナリオ分析が重要視される。これは、1.5℃や4℃といった複数の将来気候シナリオを前提に、企業がどのような影響を受け、どのように適応・移行するかを定量・定性の両面で示すものである。
このように、TCFDは単なる排出量報告にとどまらず、経営戦略や資本配分に組み込まれた気候対応を可視化する枠組みとして機能する。
SASBとISSB:補完的な枠組みとの関係性
一方で、SASB(サステナビリティ会計基準審議会)は業種ごとの財務的に重要なサステナビリティ課題にフォーカスした開示基準であり、こちらはIFRS S1の参考情報として組み込まれている。
SASBは77業種別に指標を定めており、たとえば製造業では職場安全や排出量が、テック業界ではデータプライバシーやエネルギー効率が重要テーマとなる。このように、TCFDが「戦略」や「ガバナンス」といった構造的視点を提供するのに対し、SASBは「定量評価」を支える道具として位置付けられている。
つまり、TCFD=戦略・気候リスクに関する物語構造、SASB=サステナビリティ実績を支える定量指標という関係性であり、どちらかを選ぶのではなく、統合的に活用することが現在の主流となっている。
日本企業にとっての「再点検」のポイントとは
気候関連開示の国際的な基盤は、依然としてTCFDが提示した11の推奨開示項目にある。ISSBのIFRS S2やSASBの業種別指標も、このTCFDの枠組みを基礎として構築されており、今後の制度対応においてもTCFD開示の再点検が出発点となる。
ただし、ISSB基準はTCFDの原則を踏まえつつ、より厳格かつ具体的な開示を求めている。特に、「任意性から必須化」「定性的から定量的へ」といった進化が見られる。
以下はその主要な相違点である。
| 項目 | TCFD | ISSB(IFRS S2) | 企業が確認 すべき点 |
| スコープ排出量の開示 | 推奨 | 必要 | 取引先や製品使用段階を含め、スコープ3データ収集体制を整備しているか。 |
| シナリオ分析 | 推奨 | 必要 | 自社のシナリオ分析を定量的に行い、財務数値との接続を明示できているか。 |
| 取締役会の関与(ガバナンス) | 推奨 | 必要 | 気候リスクを取締役会が定期的に議論し、意思決定に組み込んでいることを証拠立てられるか。 |
| 開示の保障体制 | 明示的な保証要求はない | 基準自体は保証を義務化していないが、投資家向け信頼性確保の観点から保証を前提とした開示準備を想定。 | 第三者保証や内部監査を見据えた開示プロセス設計が進んでいるか。 |
この比較から明らかなように、ISSB基準ではTCFDに比べて開示の水準が引き上げられている。特にスコープ3、シナリオ分析、取締役会ガバナンスは「必須化・高度化」しており、日本企業は優先的に再点検すべき領域である。また、保証体制についても法的義務化はされていないが、投資家の要請を踏まえれば早期の準備が競争優位につながるだろう。
したがって、日本企業にとって重要なのは「すでにTCFD開示をしているから十分」と考えるのではなく、ISSB基準の要求水準に照らして自社の開示を点検し、データ収集や社内統制の高度化を前倒しで進めることである。これは単なる規制対応にとどまらず、投資家からの信頼獲得や資本コストの低減につながり、企業価値向上の観点からも意義を持つ。
また、日本の気候関連開示に関連する基準である「SSBJ基準」もISSB基準を参照しているため、TCFD開示の再点検は、制度対応の基盤づくりにつながるだろう。
TCFDの原則に立ち戻り、次の開示時代へ
TCFDは、気候関連財務情報開示の原点であり、今なおその原則はIFRS S2を通じて“標準”として位置づけられている。TCFDの枠組みに基づいてすでに報告を行っている企業も、その開示の深さ・網羅性を見直す必要がある。
「開示済みだから終わり」ではなく、「より信頼される開示へどう進化させるか」が問われている。
サステナビリティ戦略を次のレベルに進める第一歩として、自社のTCFD開示を再確認し、IFRS S2への橋渡しとすること。これが2025年、気候関連開示に取り組む日本企業にとって最も実践的かつ戦略的な対応となる。
関連オリジナル解説記事
◆TCFDをわかりやすく!実施手順と陥りがちなポイントを紹介
◆ISSB×SASBスタンダード改訂:実務対応の整理とステップガイド
◆TCFD×TNFD統合開示ガイド:いま企業が備えるべき実務対応とは?(再掲)
文:菅沼友音(ESG専属ライター)
参考:TCFD HP