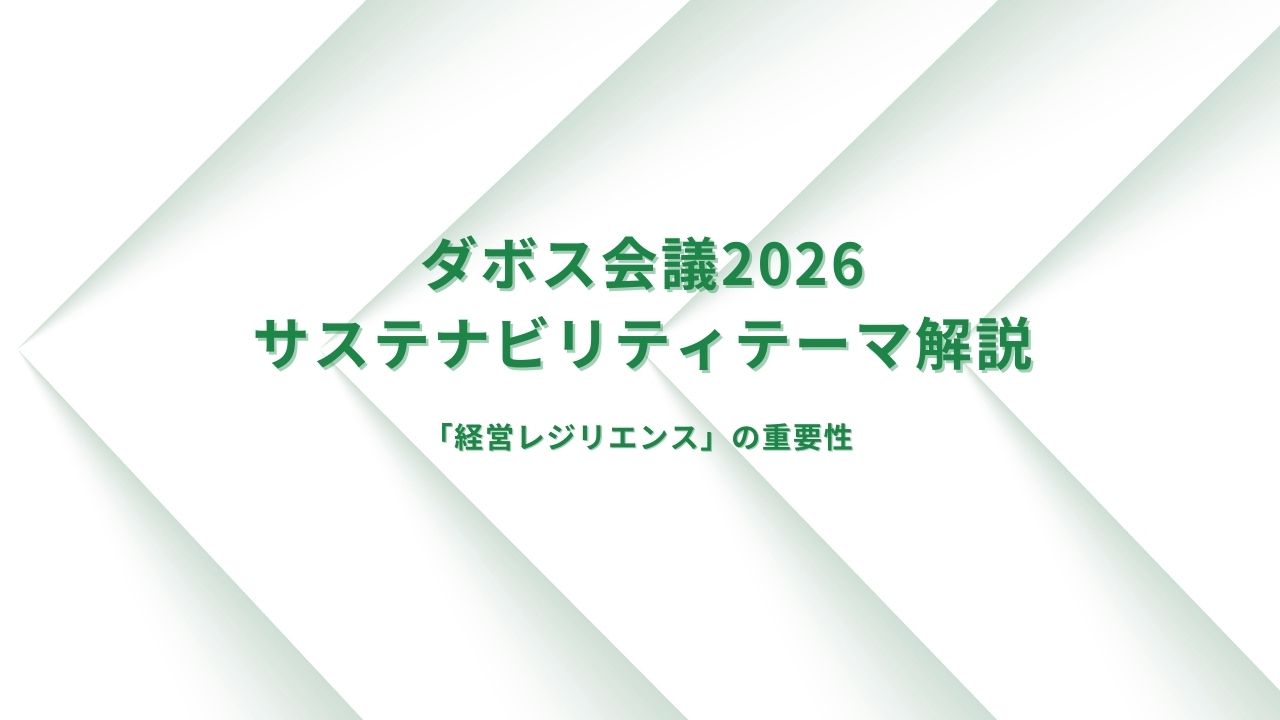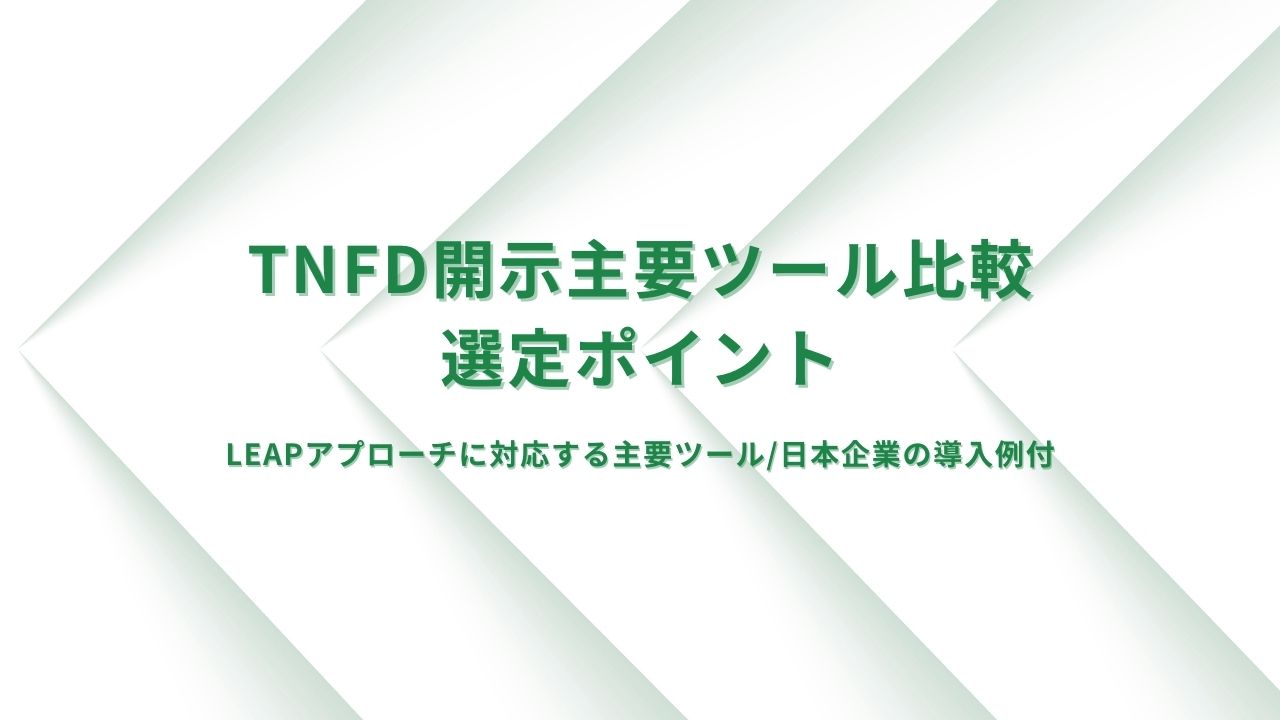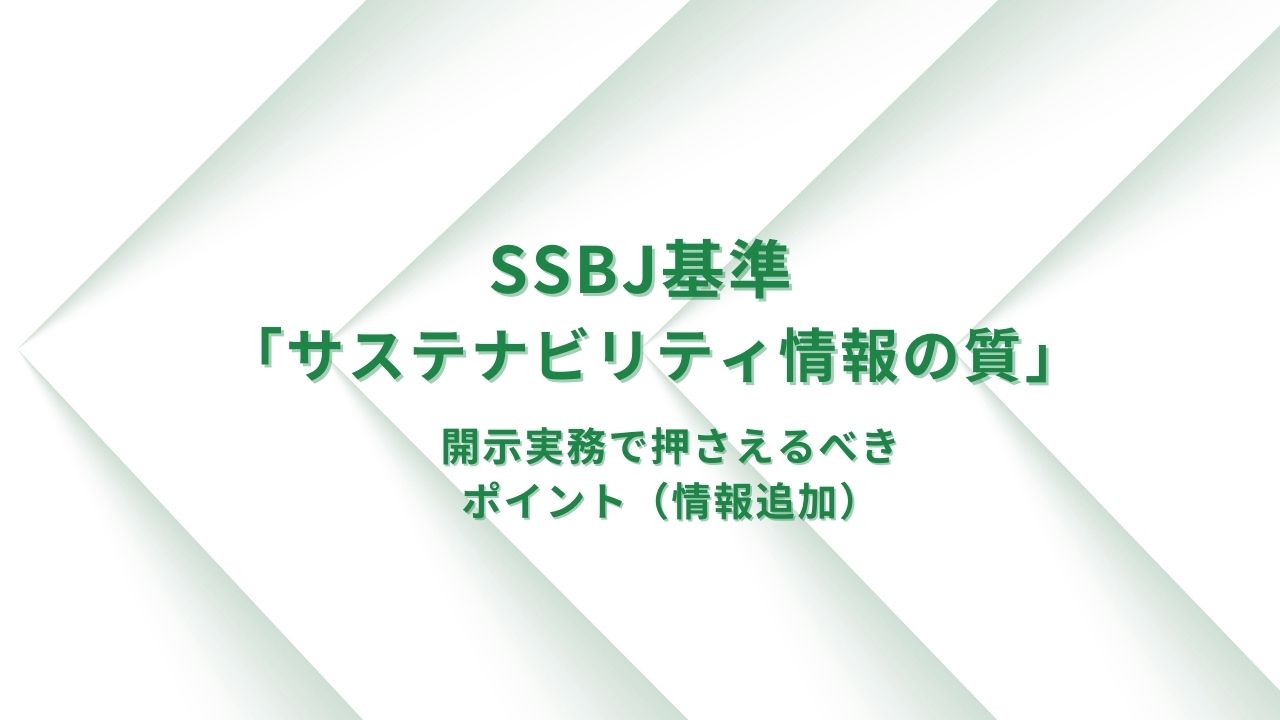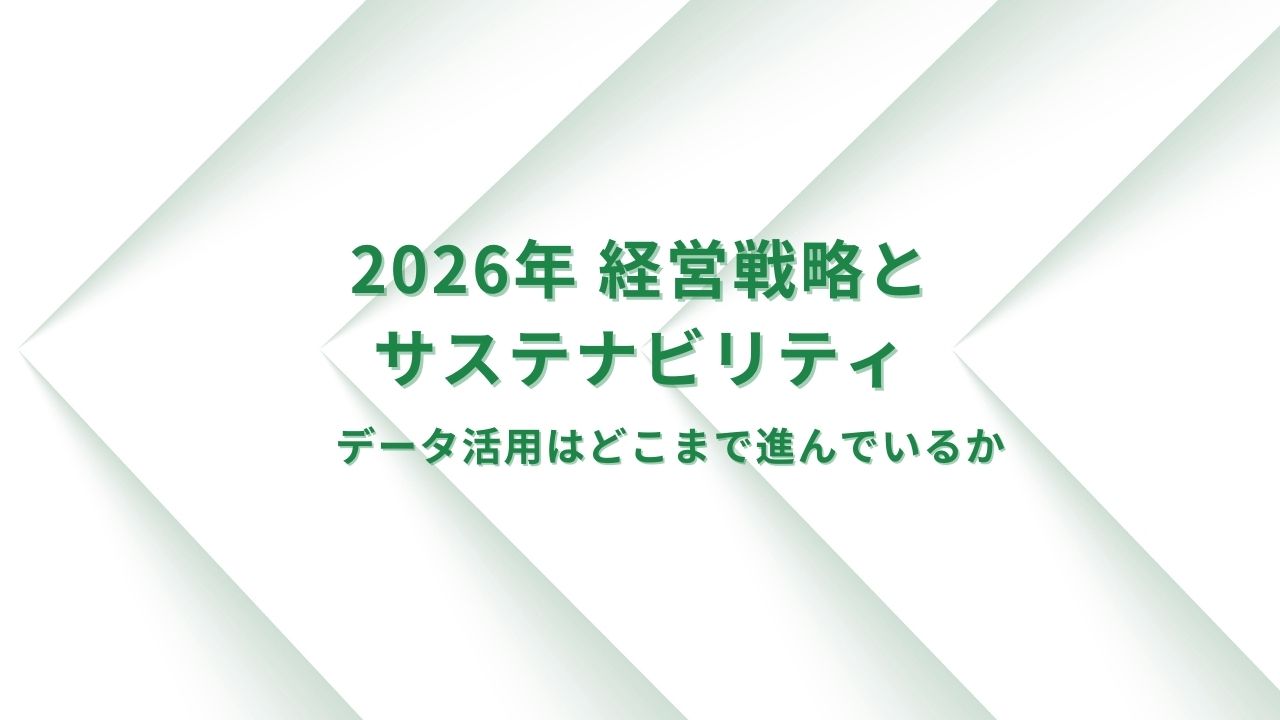TNFD・自然移行計画の5つの構成要素と先行事例/実践例の紹介
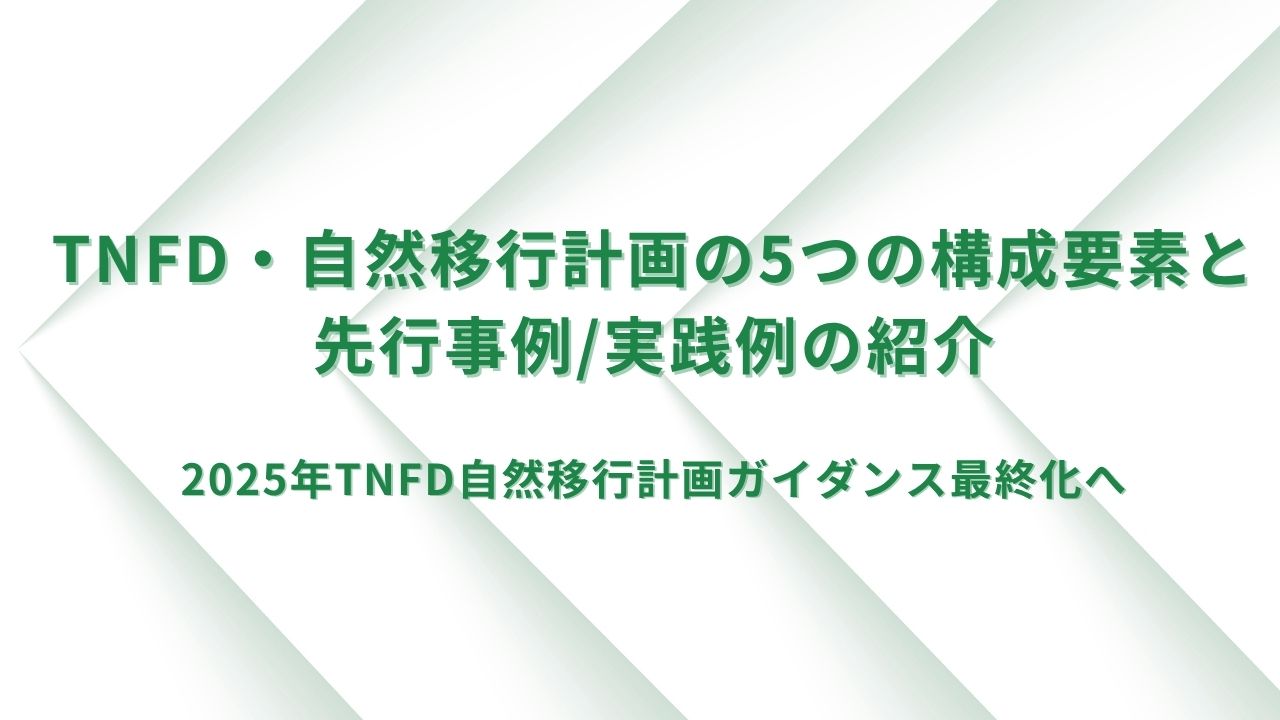
※2025年11月4日公開済みの記事にTNFDが発行した「Nature in transition plans」(2025)の内容を更新している。
自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)の最終提言公表から1年が経過し、自然資本に関連する開示が世界的に拡大している(2025年4月時点で、全世界562社のうち日本企業は154社である)。
この開示の広がりの中で、次なる焦点として注目されているのが「自然移行計画(Nature Transition Plan)」の開示である。国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)も、2025年9月・10月の会議で「自然資本・生物多様性に関する開示基準(BEES)」の一環として、投資家のニーズが高い自然移行計画の基準化について議論を進めているところだ。
本稿では、TNFDが最終化をした『Guidance on nature in transition plans』およびその前段となる『Discussion Paper on Nature Transition Plans』を参考に、自然移行計画として整備すべき5つの構成要素を整理する。また、実務的な観点から海外企業の先行事例を基に、自社の計画に応用できる実践的なポイントを提示する。「自然移行計画とは何か」「どの要素から着手すべきか」を明確にしていきたい。
※2025年11月5日更新
関連するオリジナル解説:TNFD開示を効果的に進めるには:投資家のニーズと開示のポイント
自然移行計画の概要
自然移行計画の定義
TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)は、2024年7月に公表した Discussion Paper on Nature Transition Plans において、自然移行計画(Nature Transition Plan)を次のように定義している。
「自然移行計画とは、企業の全体的な事業戦略の一部であり、グローバル生物多様性枠組(Global Biodiversity Framework)が示す“2030年までに生物多様性の損失を止め、2050年までに自然を回復軌道に乗せる”という移行に対応し、これに貢献するための目標・行動・説明責任・資源配分を示すものである。計画には、実体経済の変化を促す行動を優先的に含めるべきであり、その内容には以下が含まれる可能性がある:
負の影響の回避・削減、自然の保全・再生・修復、
自然損失の要因となるシステムの変革、
そして先住民族・地域コミュニティ・ステークホルダーとの協働。」
— TNFD Discussion Paper on Nature Transition PlansよりESG Journal作成
また、2025年11月に発行した「Guidance on nature in transition plans」では、”組織がGBF(昆明・モントリオール生物多様性枠組:Global Biodiversity Framework)という共通の指針のもと、戦略、行動、説明責任を果たすための計画(設計図)であり、リスクを回避するだけでなく、生態系と経済システム自体を実際に変革する行動に焦点を当てるもの” と定義されている。(Guidance on nature in transition plansよりESGJournal作成)
この定義が示すように、自然移行計画は単なる環境方針ではなく、企業の事業戦略の変革や具体的な進捗を伴う計画であると言える。企業が依存・影響する自然資本との関係を「保護」「再生」「変革」の観点から再構築するための行動計画である。つまり、「自然移行計画」とは、自然を損なわずに事業継続や成長を実現するための「経営計画」とも考えることができる。
LEAPアプローチとの関連
自然移行計画は、TNFDのLEAPアプローチ(Locate, Evaluate, Assess, Prepare)では、最終段階“Prepare”に位置づけられる。
LEAPアプローチでは、自社が依存・影響する自然資本を特定し、重要なリスクと機会を評価する。最後の“Prepare”フェーズでは、その分析結果をもとに、どのような目標・方針・行動を取るかを設計する。
この構造のとおり、企業は自然関連リスクを単なる分析結果として終わらせず、戦略・ガバナンス・資本配分と結びつけて経営判断に反映することが求められている。自然移行計画は分析の延長線上ではなく、実行を担う必要がある。
関連するオリジナル解説:TNFDが提唱するLEAPアプローチについてポイントを紹介
「気候移行計画」との違い
気候変動対応での移行計画と自然移行計画の主な違いは、共通のゴールの存在の有無だろう。気候変動では「ネットゼロ」という国際的な目標が共有されており、各企業はその実現に向けて削減シナリオを描くことができる。
一方、自然移行計画の場合、依存・影響の対象は企業によって異なるため「どこへ移行するか」を統一的に示すものではなく、自社が関わる自然資本の特性に応じて、“どう移行していくか”を設計する枠組みである。
自然移行計画は「環境を守るための計画」ではなく、企業が自らの事業モデルの中で自然との関係性を再定義する点が自然移行計画の核心である。
次に、移行計画策定における5つの要素とそれぞれの実務ポイント・海外事例ではどう示されているか、順に紹介していく。
つづきは無料会員登録(名前・メール・会社名だけ入力)を行うと閲覧可能!!
🔓会員登録の4つの特典
話題のサスティナビリティニュース配信
業務に役立つオリジナル解説
業務ですぐに実践!お役立ち資料
会員特別イベントのご案内!
すでに登録済みの方はログイン
執筆者紹介
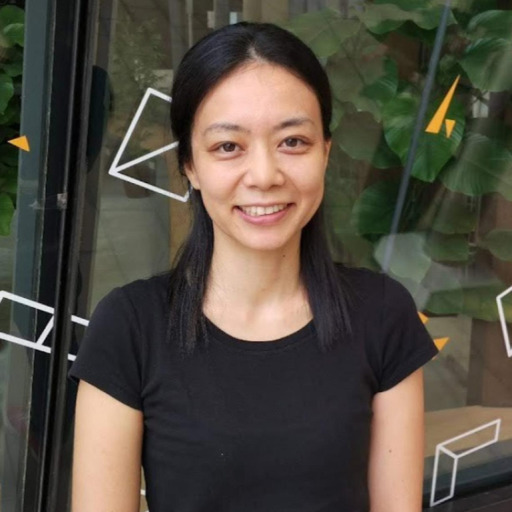 | 竹内 愛子 (ESG Journal 専属ライター) 大手会計事務所にてサステナビリティ推進や統合報告書作成にかかわるアドバイザリー業務に従事を経て、WEBディレクションや企画・サステナビリティ関連記事の執筆に転身。アジアの国際関係学に関する修士号を取得、タイタマサート大学留学。専門はアジア地域での持続可能な発展に関する開発経済学。 |