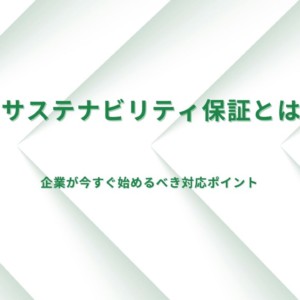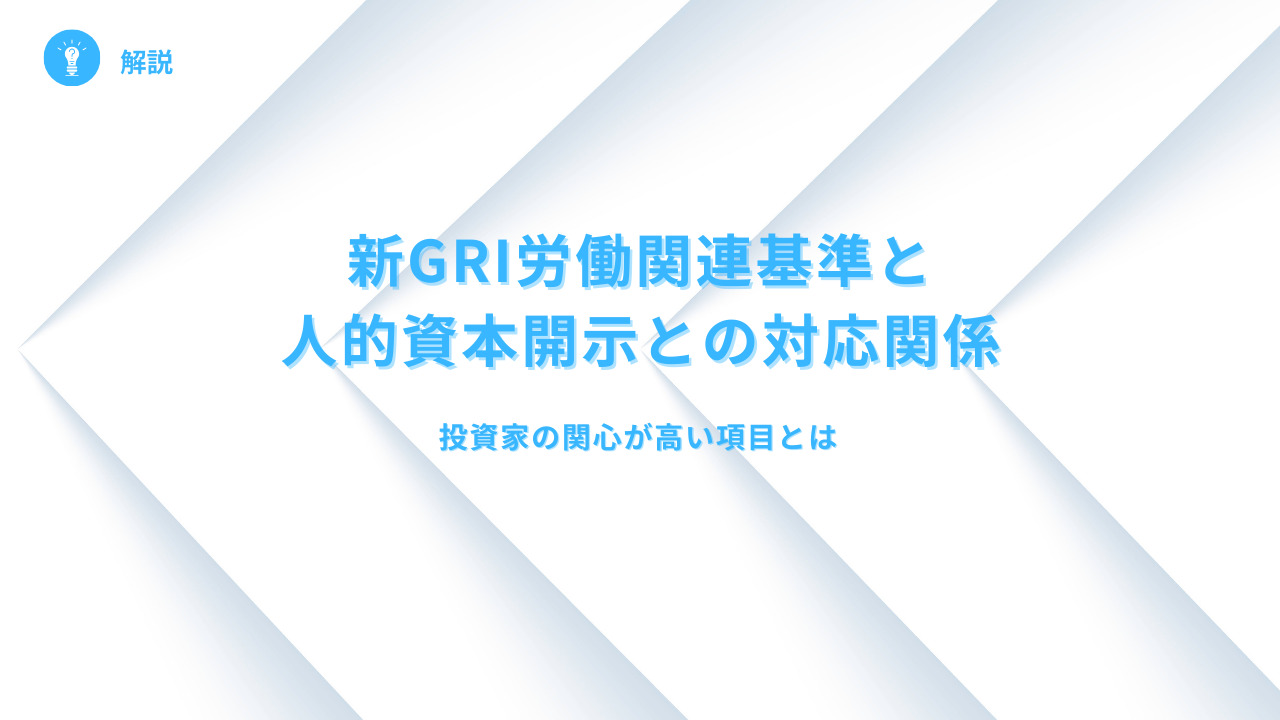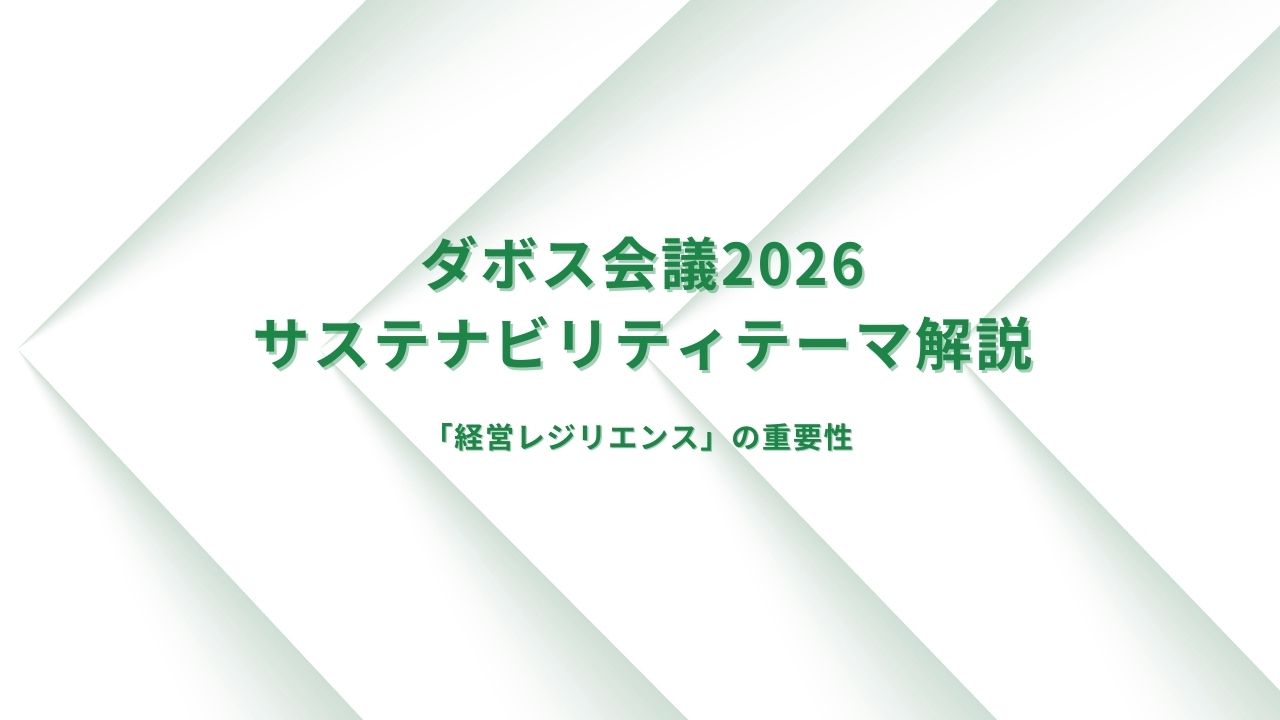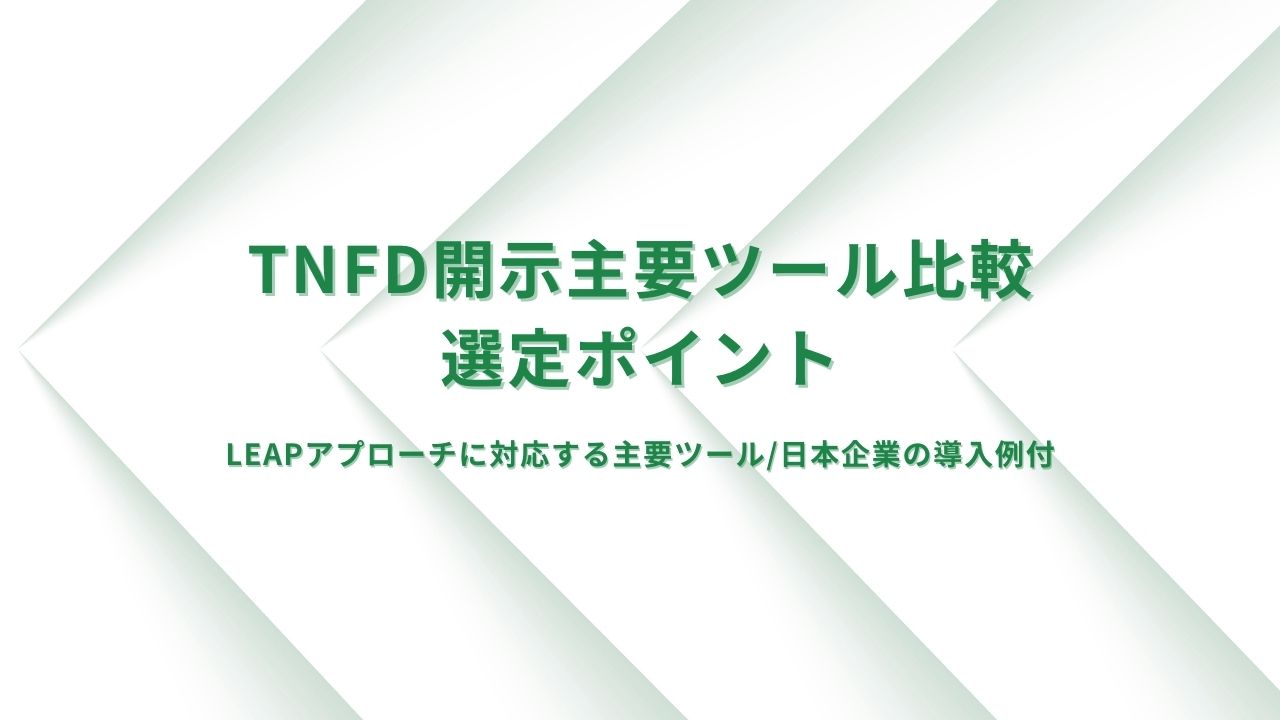TCFDをわかりやすく!実施手順と陥りがちなポイントを紹介
2022年から日本のプライム市場に上場する企業は、TCFDに準じた開示をすることが求められている。一方、TCFDの必要性は認識しているが、どのような手順であるか理解しにくい場合があるだろう。また、初年度の取り組みとして、TCFDのガイダンスのとおり進めたものの、これでよいのか不安という声も聞かれる。本稿では、TCFD開示の手順をわかりやすく解説するとともに、陥りがちなポイントについても説明する。
TCFDとは
TCFDは「Task force on Climate-related Financial Disclosures」の略であり、企業による気候変動関連の財務情報開示を推奨する組織である。G20の要請を受け、2016年に金融安定理事会(FSB)によって設立された。日本では「気候関連財務情報開示タスクフォース」と呼ばれている。
2017年6月に公表した最終報告書では、すべての企業に対し、2℃目標等の気候シナリオを用いて、自社の気候関連リスク・機械を評価し、経営戦略・リスクへの反映、その財務上の影響を把握、開示することを推奨している。気候関連のリスクを一貫性があり比較可能な形で報告することを目的としており、情報開示を行う企業、銀行、投資家に広く利用されている。
以降のコンテンツは無料会員登録を行うと閲覧可能になります。無料会員登録を行う
すでに登録済みの方はログイン画面へ