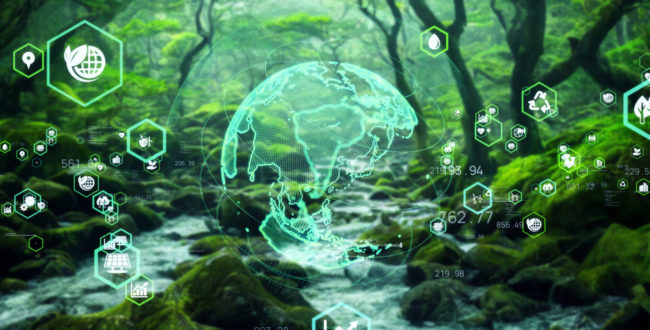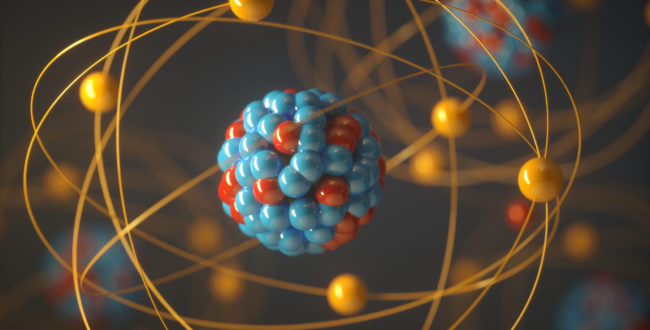国内の排出量取引制度(GX-ETS)、ベンチマークとグランドファザリングの割当水準案を提示

10月17日、経済産業省は、排出量取引制度(GX-ETS)の設計に関する事務局案を産業構造審議会で公表した。資料では、各業種のベンチマーク案の中間検討状況が共有されているほか、グランドファザリング(GF)方式による排出枠の割当水準案を初めて示すとともに、制度横断的な調整論点が整理されている。
業種横断的な論点
今回は、制度の実効性を担保する観点から「直接排出比率の補正」と「副生燃料の取扱い」が論点として挙げられていた。
① 直接排出比率に応じた割当補正
事業者によって自家発電(自家発)と購入電力(買電)の利用比率が異なるため、排出原単位に差が生じやすい。この課題に対応するため、直接排出と間接排出を合計してBMを策定し、割当算定時には「直接排出比率」を補正係数として反映させる方向で検討が進む想定がされている。
具体的には、割当量に「前年度の直接排出量/(直接+間接排出量)」を乗じて補正する方式が提案された。
② 副生燃料の適切な扱い
副生燃料は複数の業種で有効利用されており、その扱いに一貫したルールを設ける必要があるとしている。通常燃料と比較すると、排出原単位が異なる場合があるため、制度設計にあたっては副生燃料の利用を不利に扱わないよう配慮が求められる。具体的には、排出量算定や割当方法において、副生燃料の特性や利用実態を踏まえ、企業の有効利用の取組を阻害しない仕組みとする方向で検討が進められている。
ベンチマーク(BM)・グランドファザリング(GF)の割当水準案
① ベンチマーク(BM)方式
BMの割当水準は、業界の省エネ改善ペースを踏まえて段階的に引き下げる方式が採用される見通しだ。
省エネ法実績などから、業界全体が「トップランナー水準(上位15%)」に到達するには約10年を要するとされ、2030年度の目標水準は「上位32.5%」に設定することが提案された。
基準年度(2023〜2025年平均)では上位50%水準を採用し、2030年度まで線形的に引き下げる形で移行する。また、割当量は「生産量×目指す排出原単位」で算定されるが、業種によっては上位50%と32.5%の乖離が大きい場合もあり、制度開始当初の5年間は激変緩和措置の検討も求められている。
② グランドファザリング(GF)方式
GF方式では、基準排出量に一定の削減率を乗じて割当を減らしていく方式が取られる。
| 区分 | 年率削減率 | 想定根拠 |
|---|---|---|
| エネルギー起源CO₂ | 年率1.7% | 燃料転換や都市ガス化を前提とした削減ポテンシャル |
| プロセス由来CO₂ | 年率0.3% | 削減手段が限定的なため緩やかな改善を想定 |
今後の予定
今後、第5回会合(11月予定)に以下の取り組みを予定している。最終的な取りまとめは2025年12月以降に公表される見込みである。
- 早期削減やリーケージリスクへの配慮、研究開発投資へのインセンティブ設計、価格上限・下限の具体的水準、移行計画