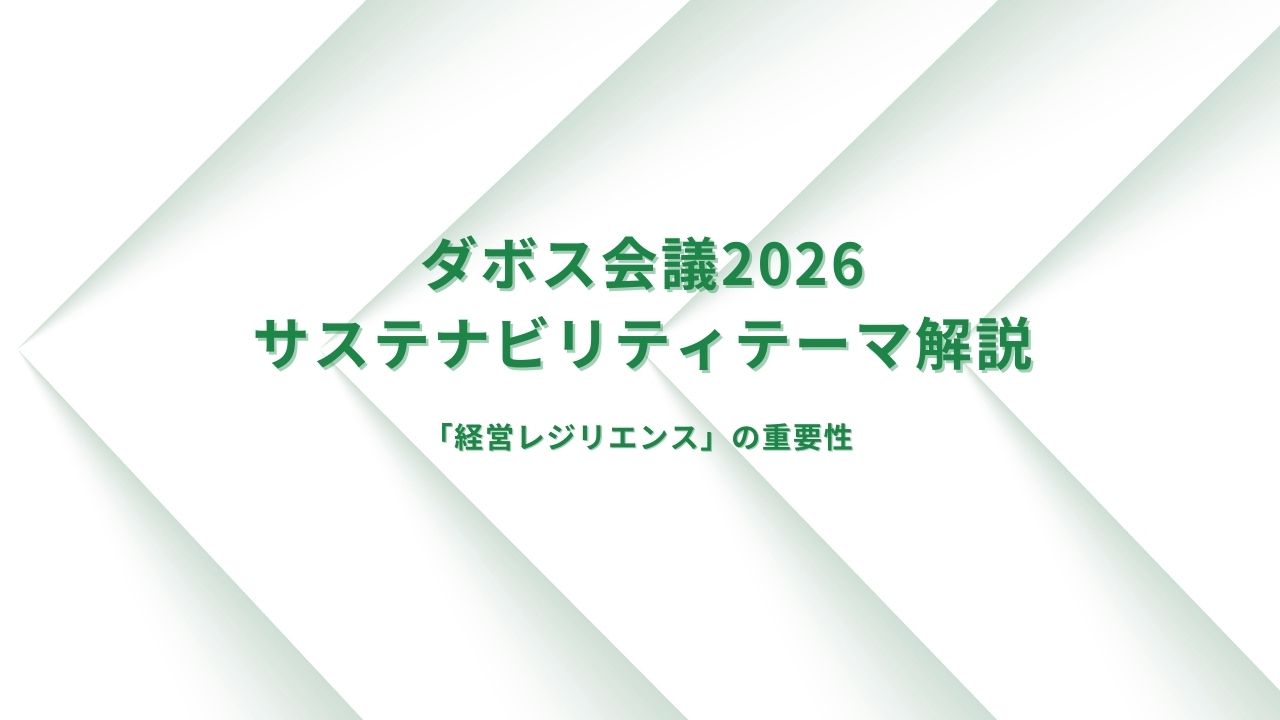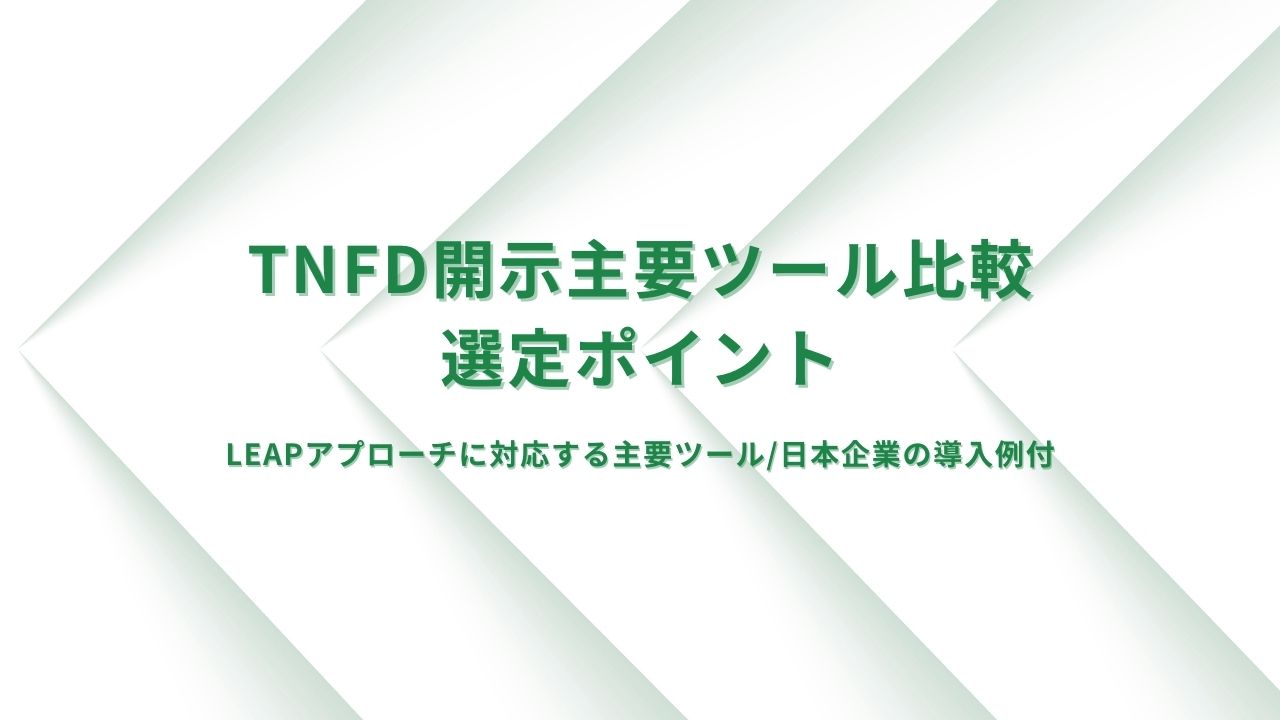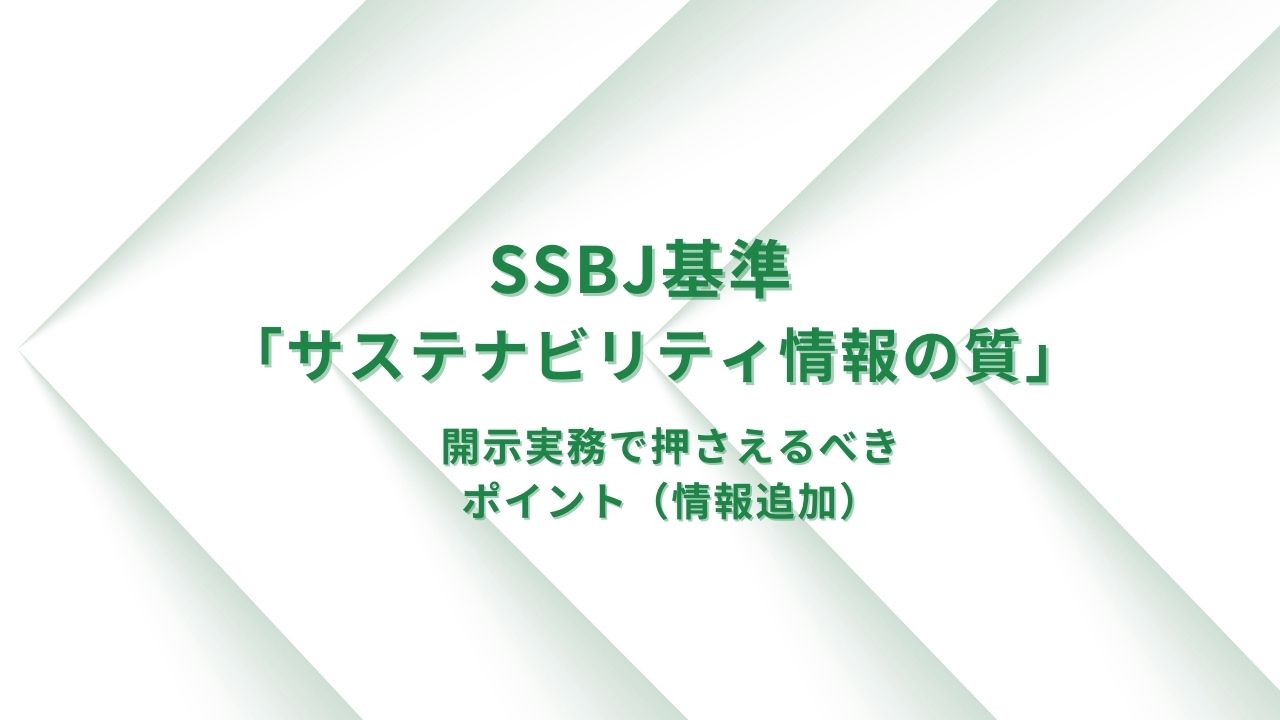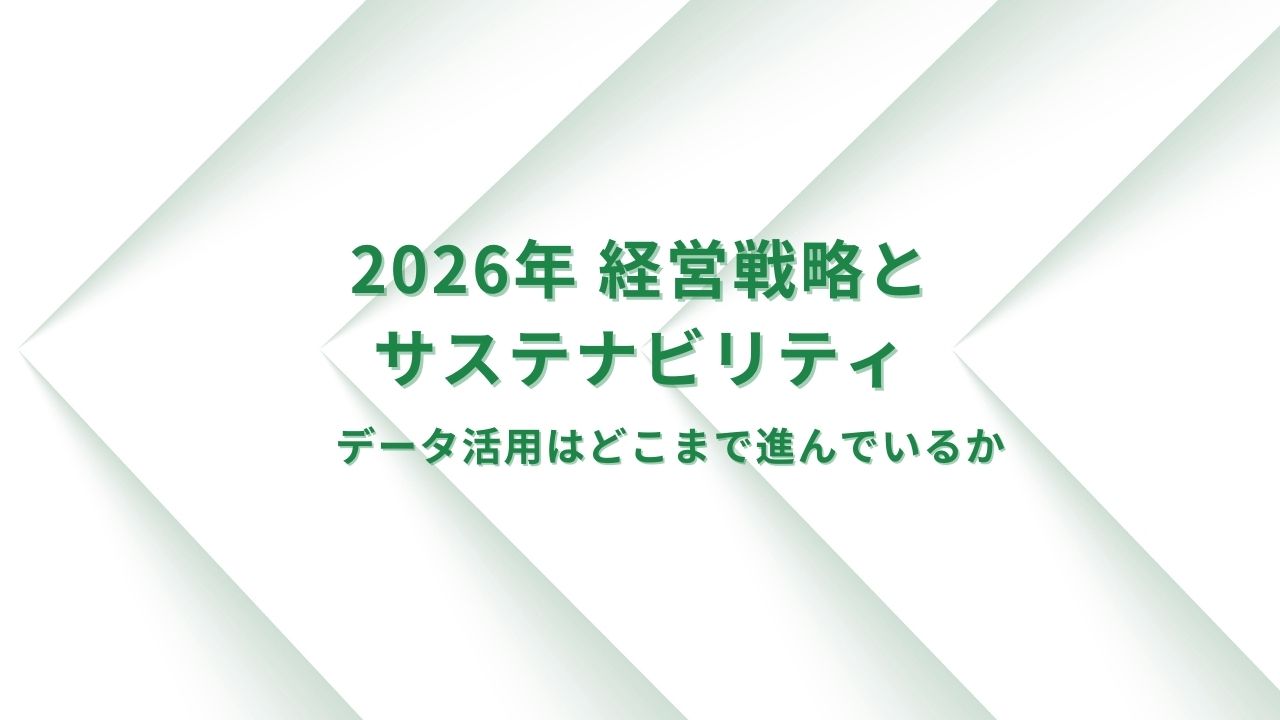スコープ3・カテゴリー11の算定方法は難しい?開示事例と解説!

2023年、ISSBによりGHG排出量の管理においてスコープ3のすべてのカテゴリーの算出が求められる予定だ。ISSBの基準は国際的な基準となるため、東京証券取引所のプライム市場で求められている基準とは異なる。しかし、国際的な評価機関や投資家は、スコープ3のすべてのカテゴリーを開示している企業と比較して、日本企業のESG情報を評価するようになるであろう。外部からの評価を維持・向上させるためにも、スコープ3の算出開示は重要である。
スコープ3およびカテゴリーとは
スコープ3について
スコープ3とは、企業がサプライチェーンにおける温室効果ガス(GHG)排出量を算定する際の、事業活動に関連した間接的な責任範囲のことである。サプライチェーン排出量は、スコープ1排出量・スコープ2排出量・スコープ3排出量の合計で計算できる。
| スコープ | 内容 |
| スコープ1 | 自社内部での燃料の燃焼等による直接排出 |
| スコープ2 | 電力会社などの他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出 |
| スコープ3 | 原材料の生産や輸送、ならびに、製品の使用や廃棄等での全体的な排出(スコープ1、スコープ2以外の間接排出) |

画像出典:排出量算定について|環境省
企業活動において、自社の上流や下流におけるGHG排出量(スコープ3)は、自社内の排出量(スコープ1,2)よりも多い場合が大半である。そのため、企業は自らの事業活動からの排出だけでなく、すべての事業の取引先企業やエンドユーザーの排出量も考慮したうえで、排出量の算定・削減をおこなう必要があるという見方が重視されるようになった。
また、各外部評価機関において、スコープ3に関する質問は一般化し始めている。たとえば、機関投資家向けの企業における環境活動の情報・評価であるCDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)では、すでにスコープ3設問が定着している。各企業が設定する温室効果ガス排出削減目標であるSBTi(Science Based Targetsイニシアティブ)では、スコープ3を含むサプライチェーン全体の削減目標を設定することが求められている。
以降のコンテンツは無料会員登録を行うと閲覧可能になります。無料会員登録を行う
すでに登録済みの方はログイン画面へ