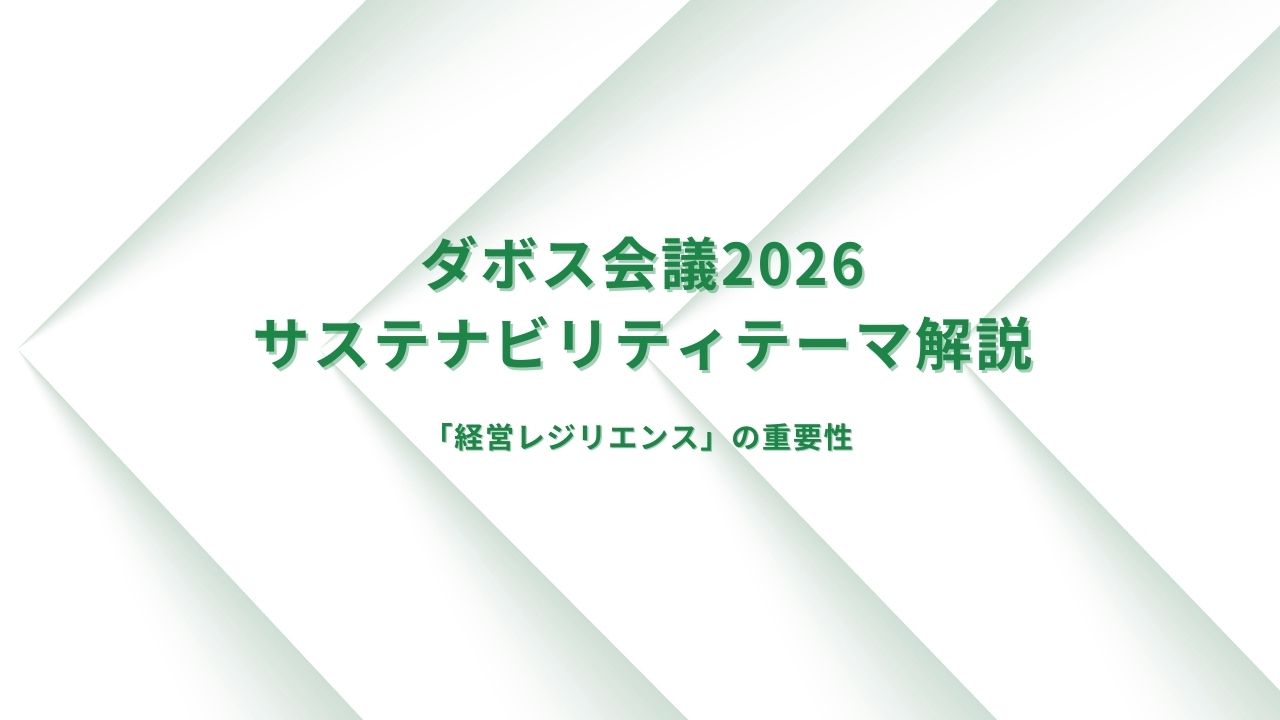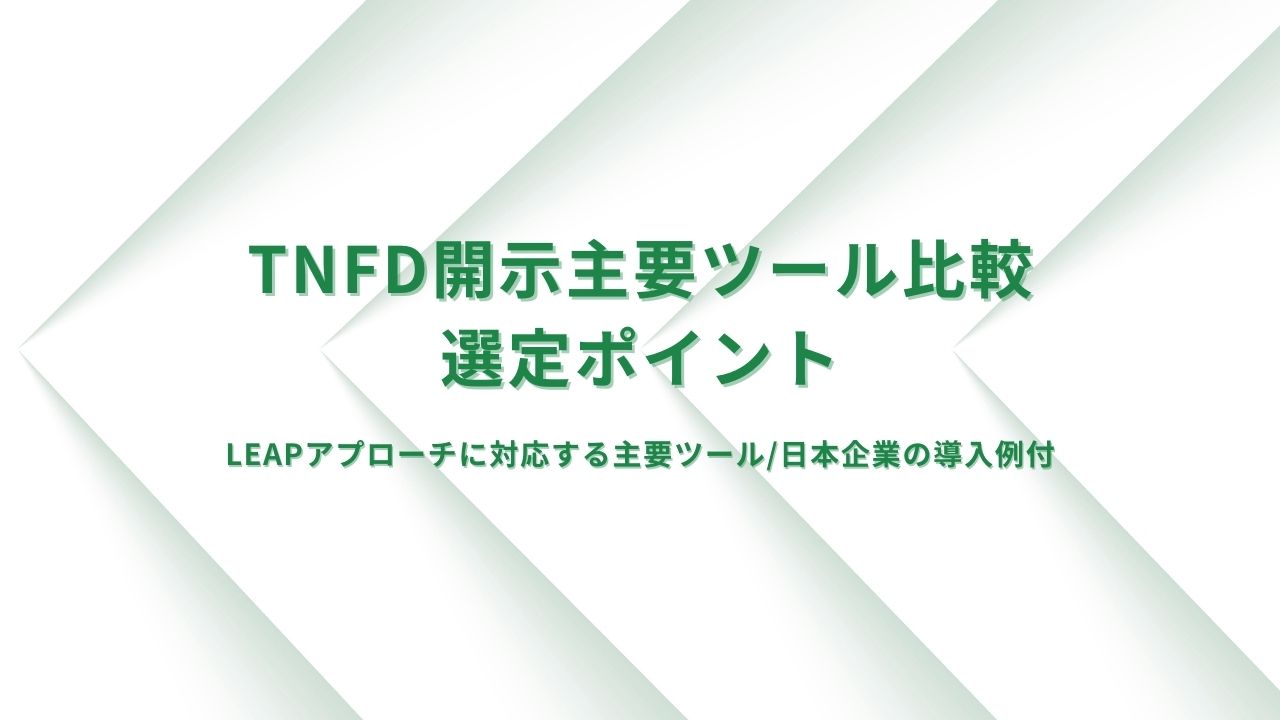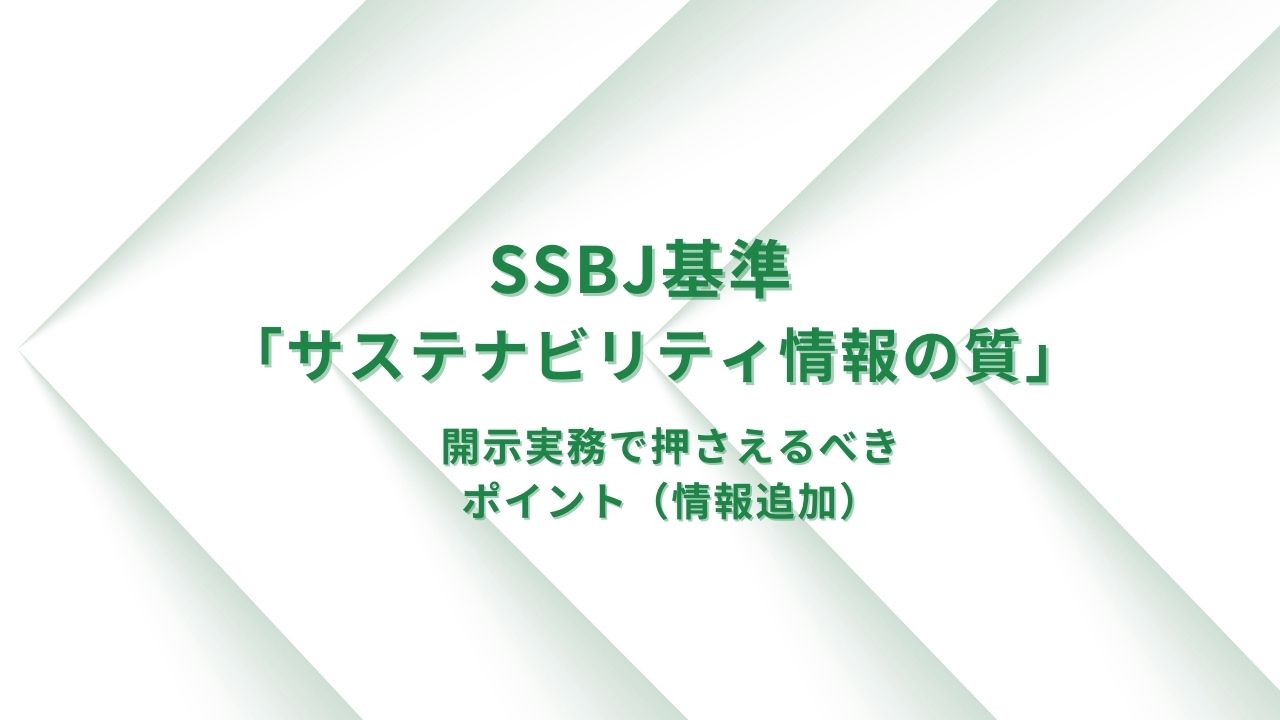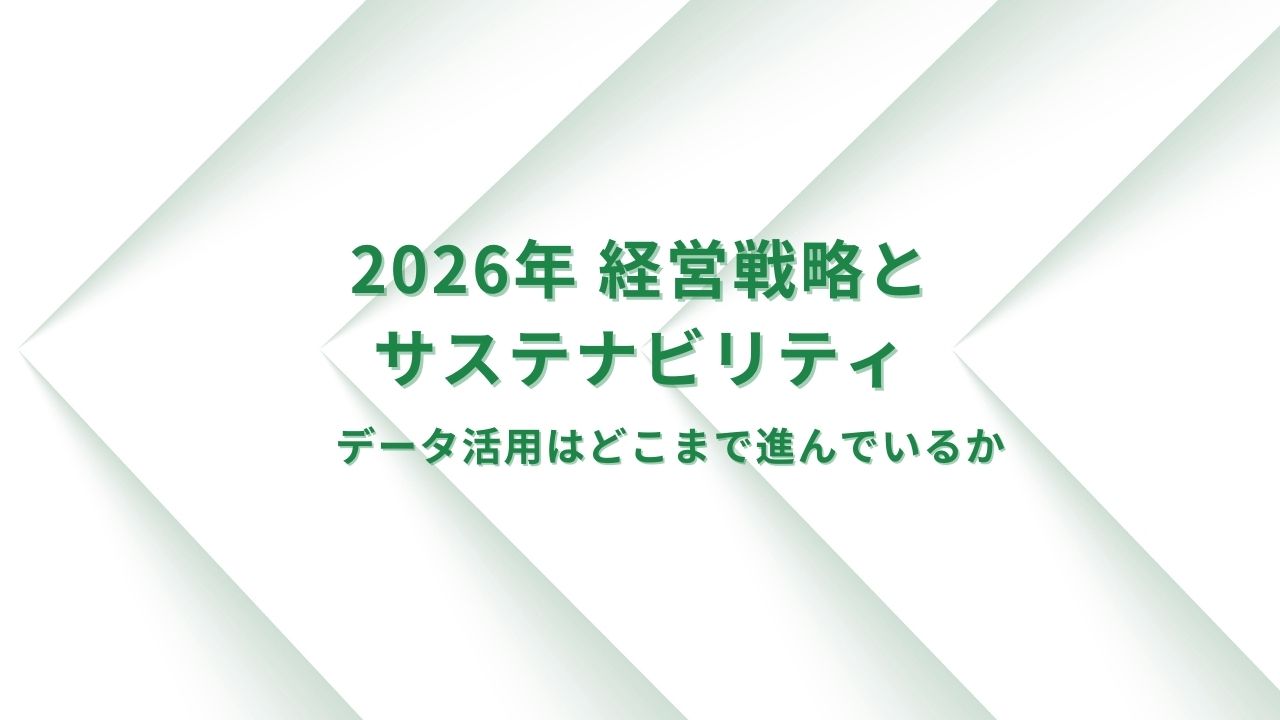SBTi・SBT認定とは?企業にもたらすメリットと実務的課題
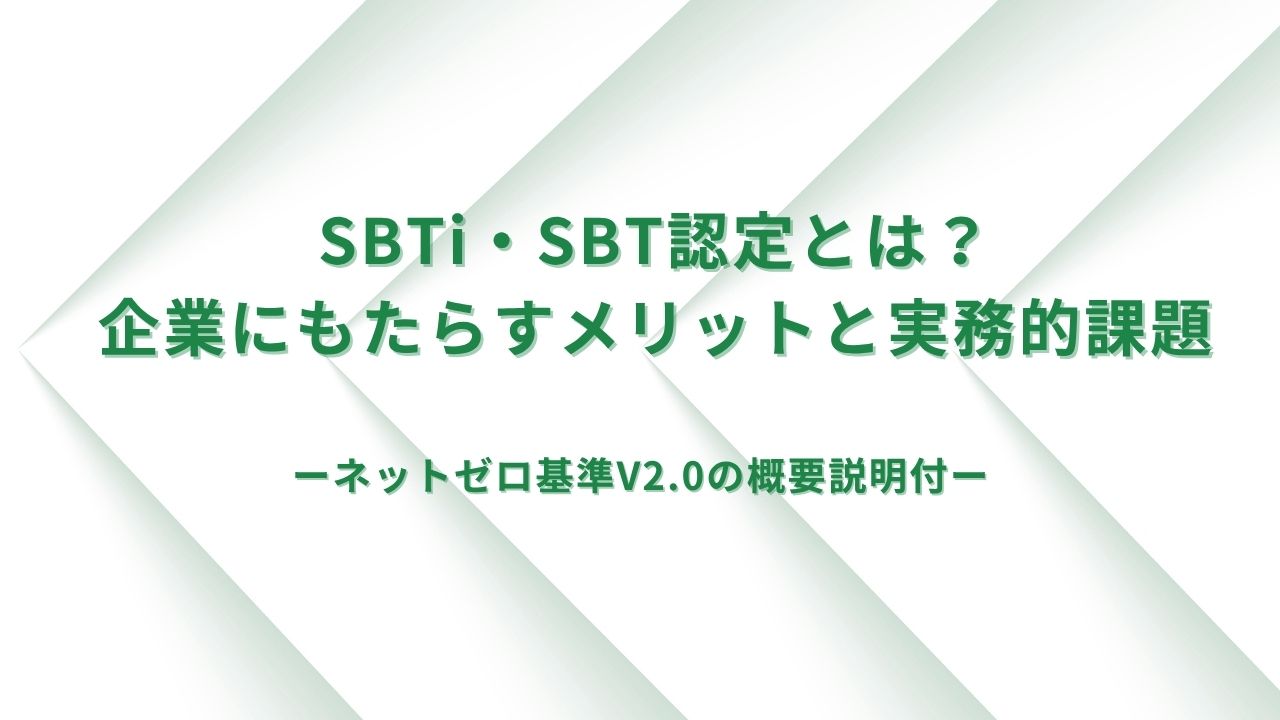
SBTi(Science Based Targets initiative)とは、2015年にCDP、UNGC、WRI、WWFが共同で設立した国際的イニシアチブ。SBTiによれば、「科学的根拠に基づいた温室効果ガス削減目標の設定」は、企業にとって国際的な標準となりつつある。
SBTiは企業の目標設定を審査・認定する仕組みとして「SBT認定」を提供している。この認定取得は脱炭素経営の客観的証明(基盤)として外部評価につながるとされている。
本稿では、SBTiとSBT認定の概要を整理し、認定取得がもたらすメリットと直面しやすい実務上の課題を示す。SBT認定のメリットとしては、投資家の評価向上だけではなく、自社のサステナブル経営においてもどのように活用できるかについて解説している。
また、ネットゼロ目標の実現における「カーボンクレジット・カーボンオフセット」実務上の留意点も紹介する。
関連するオリジナル解説>>>
>>>SBTiのネットゼロ基準の改訂案とは ?~ カーボンクレジットの扱いに明確な方針
つづきは無料会員登録(名前・メール・会社名だけ入力)を行うと閲覧可能!!
サステナビリティ実務に役立つ情報をもっと手に入れましょう。
🔐会員登録の4つの特典
定期便!新着のESGニュース
読み放題!スペシャリスト解説
速報!お役立ち資料・ツール
会員特別イベントのご案内!
すでに登録済みの方はログイン
執筆者紹介
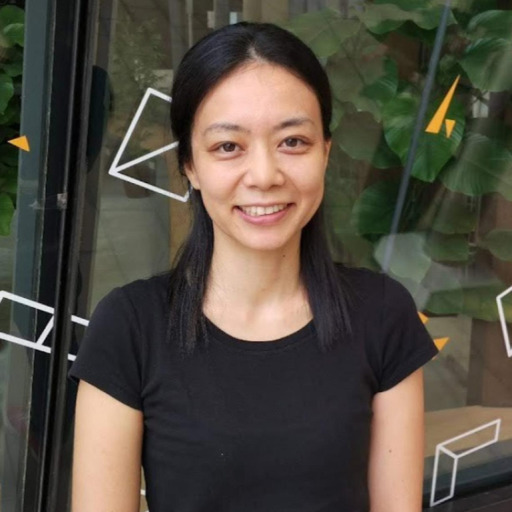 | 竹内 愛子 (ESG Journal 専属ライター) 大手会計事務所にてサステナビリティ推進や統合報告書作成にかかわるアドバイザリー業務に従事を経て、WEBディレクションや企画・サステナビリティ関連記事の執筆に転身。アジアの国際関係学に関する修士号を取得、タイタマサート大学留学。専門はアジア地域での持続可能な発展に関する開発経済学。 |