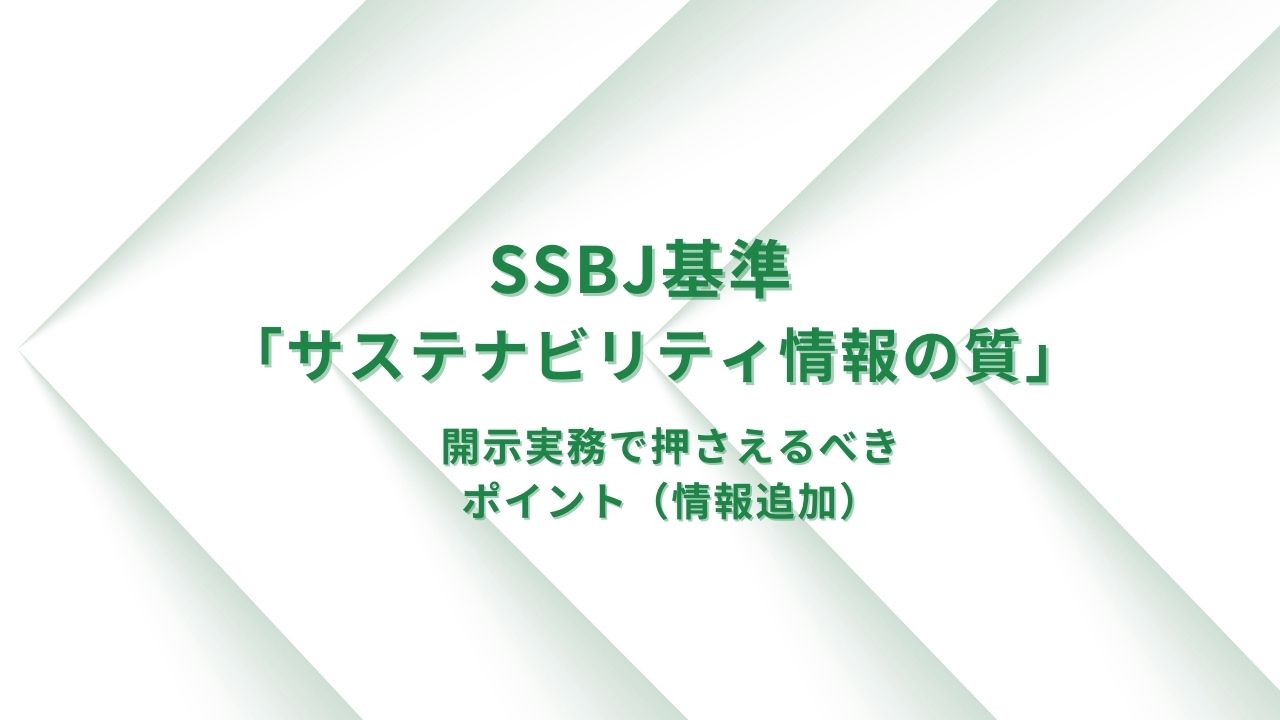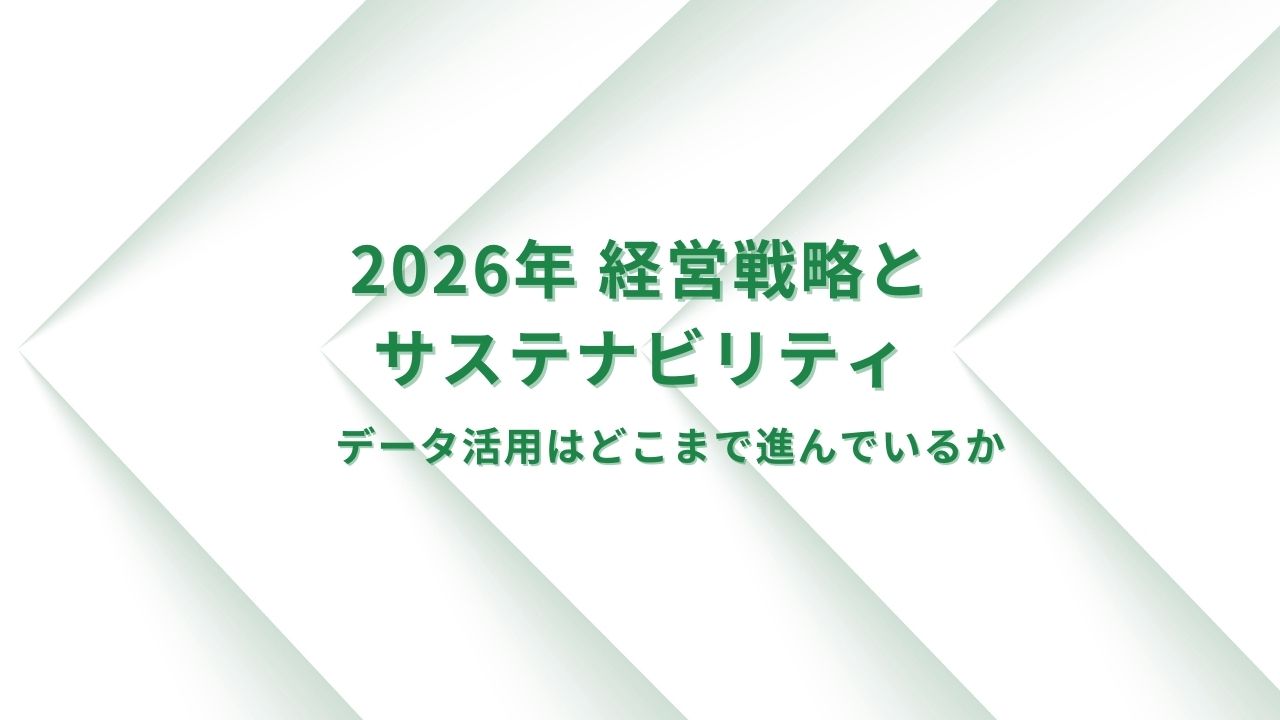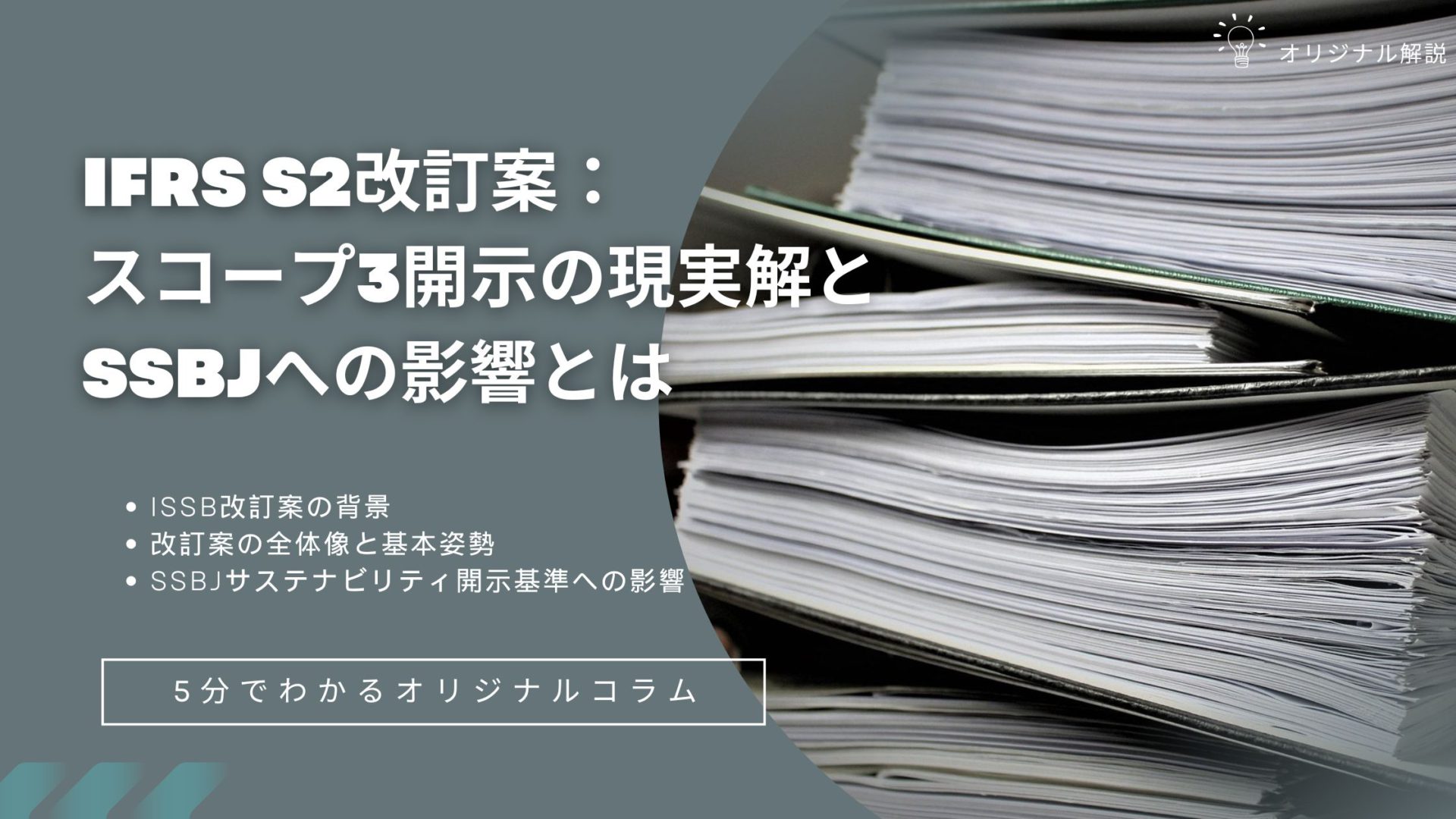スコープ3の算定方法をわかりやすく解説!カテゴリごとの一覧付
脱炭素の政策の一環として、GHG排出量の開示および削減が企業に求められている。特に、プライム市場に上場する企業は、GHGプロトコルのスコープ3を含む、サプライチェーン上のすべての排出量の開示が義務付けられている。しかし、スコープ3の開示は容易ではなく、着手が進みづらい実情もある。今後さらに規制が強化される可能性もあるため、どのように算定すればよいか改めて理解を深める必要があるだろう。
Contents
スコープ3とは?カテゴリーごとの活動例
スコープ3とは
スコープ3とは、企業がサプライチェーンにおける温室効果ガス(GHG)排出量を算定する際の、事業活動に関連した間接的な責任範囲のことである。サプライチェーン排出量は、スコープ1排出量(自社内の直接的な排出)・スコープ2排出量(自社内の間接的な排出)およびスコープ3排出量の合計で計算される。
| スコープ | 内容 |
| スコープ1 | 自社内部での燃料の燃焼等による直接排出 |
| スコープ2 | 電力会社などの他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出 |
| スコープ3 | 原材料の生産や輸送、ならびに、製品の使用や廃棄等での全体的な排出(スコープ1、スコープ2以外の間接排出) |

画像出典:排出量算定について|環境省
企業活動において、自社の上流や下流におけるGHG排出量(スコープ3)は、自社内の排出量(スコープ1,2)よりも多い場合が大半である。そのため、企業は自らの事業活動からの排出だけでなく、すべての事業の取引先企業やエンドユーザーの排出量も考慮したうえで、排出量の算定・削減をおこなう必要があるという見方が重視されるようになった。
以降のコンテンツは無料会員登録を行うと閲覧可能になります。無料会員登録を行う
すでに登録済みの方はログイン画面へ