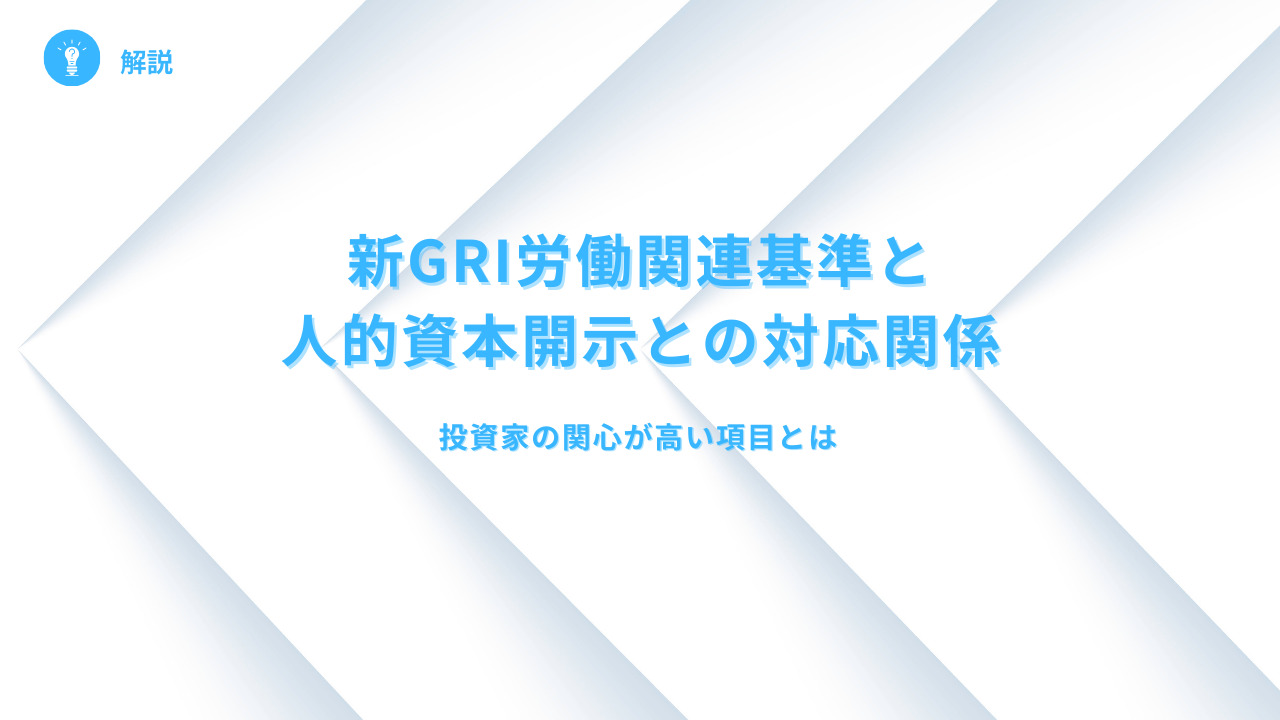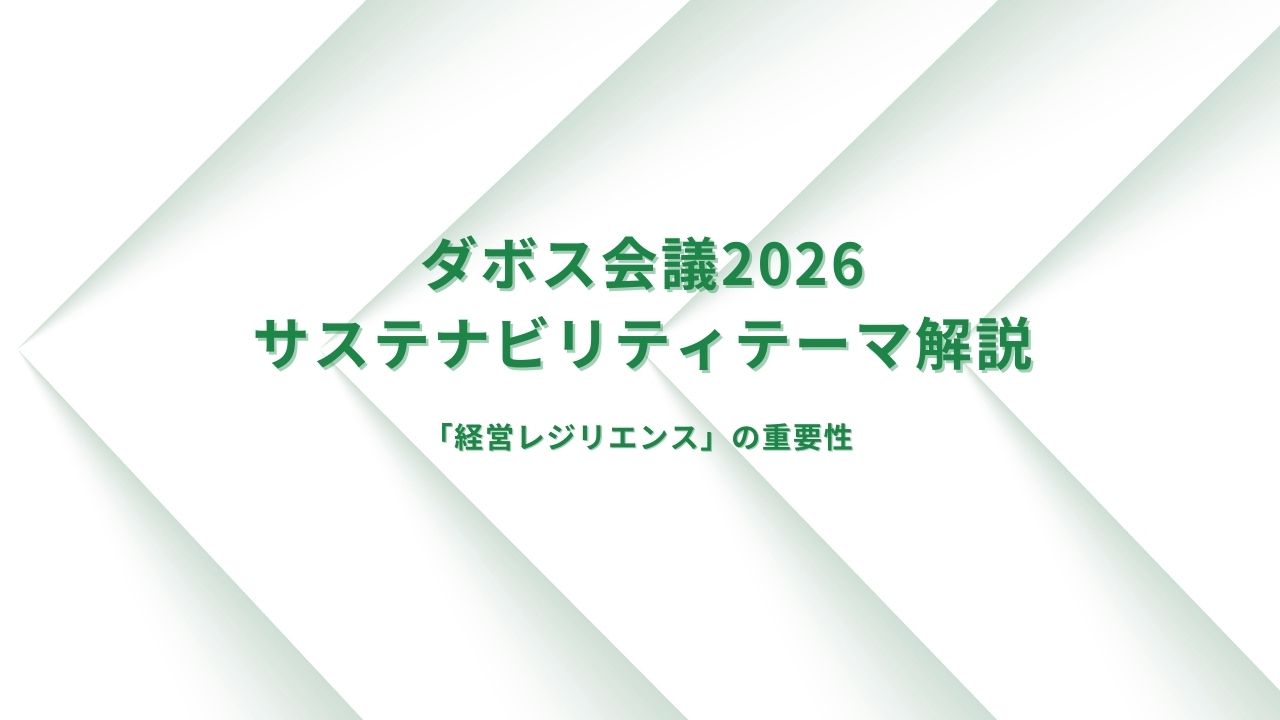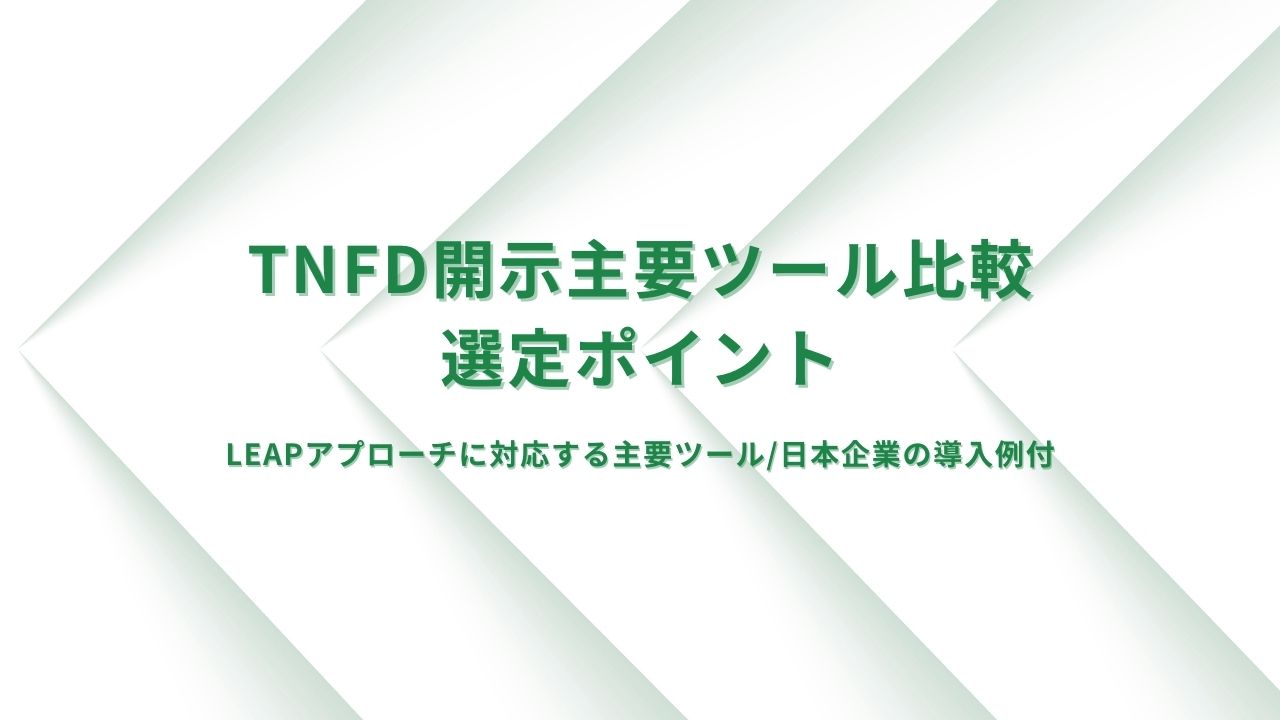<最新>ESG評価機関の概要:S&P (CSA), CDP, MSCI, FTSE, Sustainalytics・実務対応の視点(2025年版)

2025年上期、グローバルなサステナブル投資ファンドの資産残高は約3.5兆ドルに達し(Mornigstar,2025)、前年同期比で約10%増加した。一時は「反ESG」の動きから投資への懸念も広がったが、実際には顕著な改善を遂げていると言える。
また、企業のESGスコアと市場価値(EV/EBITDA倍数)との間に相関があるという調査分析も過去に示されており(デロイト 2023))、ESG評価は単なる「報告義務」ではなく、「価値創造の一要因」としての側面を持つとされている。
一方、ESG評価への対応は重要であるものの、実務的な負担が大きいことや、その成果が経営戦略にどう結びつくか見えにくいことも事実である。MIT(2022)の調査でも、評価結果のみを重視するのではなく、その背後にある方法論や指標設計の意図を理解する必要があると指摘されている。
本稿では、主要機関(S&P (CSA)、CDP、MSCI、FTSE、Sustainalytics)の概要を改めて整理する。また、ESG評価対応を企業価値向上のプロセスとして活用するための視点と実務ポイントについても提示する。
|ESG評価機関概要
ESG評価機関では、各社の方針に基づき開示情報や質問票を用いて評価を実施している。
|ESG評価機関とは
企業の環境・社会・ガバナンスに関する取り組みを独自の基準で分析し、投資家や金融機関に対して非財務リスクと機会の情報を提供する組織である。これらの評価は、上場指数(例:DJSI、FTSE4Good)や投資判断に活用されている。
投資家にとっては比較可能性と説明責任の確保が重要であり、企業にとってはリスク管理と資本市場での信頼性向上が重要である。ESG評価は、「格付け」として受け止めるのではなく、自社の経営方針や開示体制を客観的に見直す機会として活用することも可能である。
|主要な評価機関の概要
主要なESG評価機関は、それぞれ評価方法・データソースや調査方法が異なる。 企業がどの評価に重点を置くかを判断するためには、各機関の構造を把握しておくことが重要だ。
| 評価機関名 | 特徴 |
|---|---|
| S&P Global Corporate Sustainability Assessment(CSA) | 企業への質問票を中心に、ガバナンス・環境・社会分野の取組を定量化 Dow Jones Sustainability Indices(旧DJSI)の構成銘柄選定に利用 参考:S&P Global CSA 2025 Methodology Updates |
| CDP | 投資家・機関向けに環境情報を開示・格付けする世界最大の開示プラットフォーム 気候変動・水・森林分野を対象に、質問票や公開情報で企業の対応をA〜Dスコアで評価 参考:CDP 2025 Disclosure Overview |
| MSCI | 業界別にリスクとマネジメント体制を分析し、ACWI ESG ユニバーサル指数などに活用 2025年資料では、AIと自然言語処理(NLP)によるデータ収集・検証の自動化を明記 GPIFが採用するESGセレクト・リーダーズ指数にも利用 参考:MSCI Sustainability Solutions Brochure |
| FTSE | ESGパフォーマンスを総合的にスコア化し、FTSE Blossom Japan Index などの指数算定に使用 GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が採用しているESG投資指標の基礎データ 参考:FTSE Russell Japan ESG Index |
| Sustainalytics | ESGリスクの大きさと対応力に焦点を当て、公開情報から企業のリスクマネジメント力を定量評価 投資家がリスクエクスポージャーを理解するための指標として活用 参考:Morningstar Sustainalytics |
2025年、主要機関では評価項目や方法論の更新が進んでいる。たとえば、S&P Global の Corporate Sustainability Assessment(CSA) では、「贈収賄・腐敗防止(Anti-Bribery and Corruption)」など、ガバナンス関連指標を強化するなど、企業の実効的な管理体制の有無を問う設問が追加された。
また、CDP ではISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の開示基準との整合を図る形に移行、MSCIでは、AIおよび代替データを活用してESG評価情報の収集・分析精度を高めているなど、各社の評価項目の更新が進んでいる。
|ESG評価がもたらす経営への影響(メリット)
ESG評価への対応は、単なる“スコア獲得の作業”だけではなく、作業を通じて情報の整備・経営体制の明確化・資金調達力の向上など、企業経営に実質的な効果をもたらす可能性があると言える。
以下では、主な三つの視点からそのESG評価による経営へのメリットを整理する。
※本項はあくまでESG Journal編集部の意見でありシェルパ・アンド・カンパニーの考えを示すものではない。
|評価対応と制度対応の共通項
ESG評価に対応する過程で整備される情報は、結果的に制度開示の体制を整えることにつながると考えられる。たとえば、CDPの質問票は、ISSBとの整合を強化し、気候変動・水・森林といったテーマを横断的に扱う設計に改訂されている。
また、ESG評価に向け整備したデータ管理の仕組みがある場合(例:評価項目と開示情報のギャップ分析など)、各国の開示制度対応にも転用できる点が多くある。こうした基盤があることで、重複作業の削減や開示の一貫性向上という効果を見込める。データ管理を軸に「評価」と「制度対応」が両立できるだろう。
次に、ガバナンス・企業価値・資金調達など、どのようなメリットがあるか説明しつつ、自社に応じた評価機関の優先順位や実務ポイントについて考察する。
つづきは無料会員登録(名前・メール・会社名だけ入力)を行うと閲覧可能!!
🔓会員登録の4つの特典
話題のサステナビリティニュース
業務に役立つオリジナル解説
業務ですぐに実践!お役立ち資料
会員特別イベントのご案内!
すでに登録済みの方はログイン
執筆者紹介
竹内 愛子 (ESG Journal 専属ライター)
大手会計事務所にてサステナビリティ推進や統合報告書作成にかかわるアドバイザリー業務に従事を経て、WEBディレクションや企画・サステナビリティ関連記事の執筆に転身。アジアの国際関係学に関する修士号を取得、タイタマサート大学留学。専門はアジア地域での持続可能な発展に関する開発経済学。