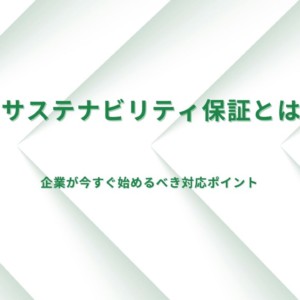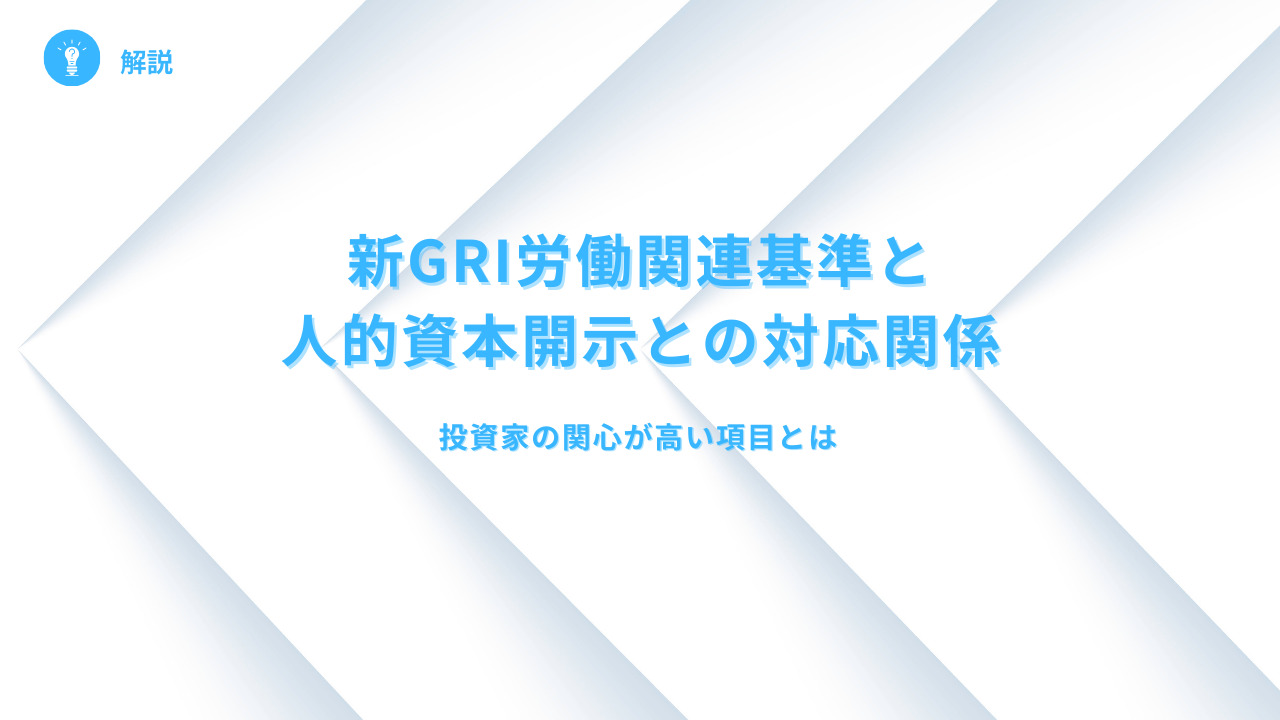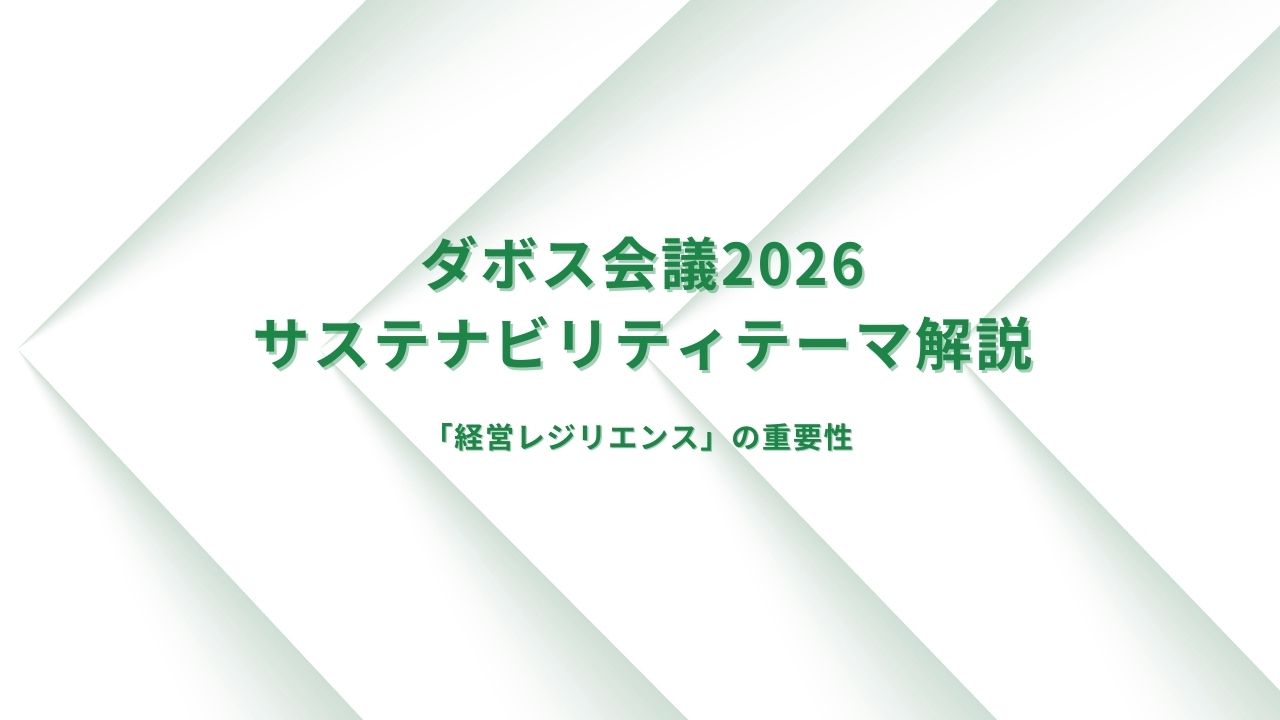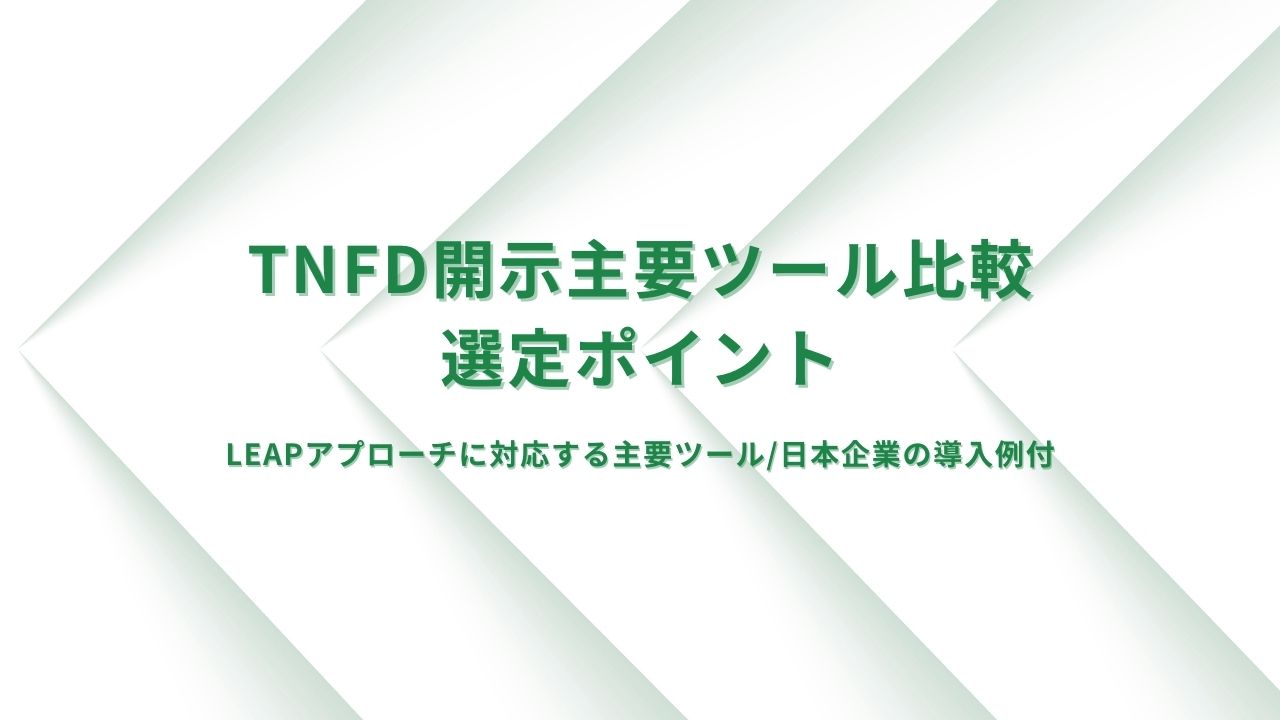AI時代のサステナビリティ情報開示のポイント ー現状チェック項目付ー
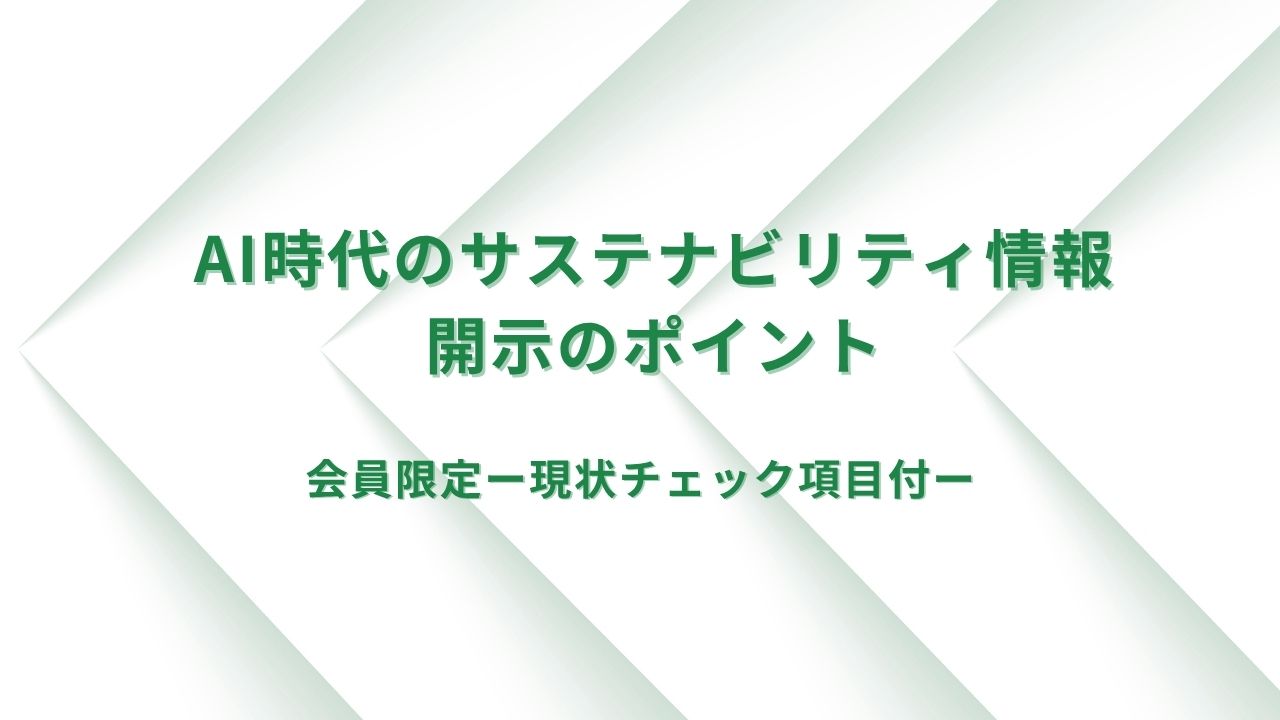
サステナビリティ情報開示は、アナリスト(人間)が読むことを前提とされた構造になっているが、近年は主要な評価機関がESG評価や投資分析にAIを導入し始めた。これにより、開示情報は「AIに正しく理解される」ことが不可欠となった。
今後ますますAIの活用がサスティナビリティ情報開示においても進むと思われるが、どのようにすれば「AIが読みやすい(機械可読性)」か具体的に理解しづらいことがあるだろう。
本稿では、現状の開示とAI時代の開示の違いから、ESG評価機関におけるAI活用について整理しながら、AIに読まれる開示のポイントを紹介する。機械可読性には、構造化されたデータが重要だが、どのように構造化するかについて説明している。
AI時代におけるサスティナビリティ情報開示とは
サスティナビリティ報告書においても、今後さらに進むであろう「AI評価」への対応への想定は重要だ。従来の開示とAI時代の開示ではどのような点において違いがあるのか、下記の表とおり整理している。
AI時代の開示では、AIモデルの実装において「情報を効率的に解析」できるよう、定量的で構造化されたデータを提供する必要があるだろう。
つづきは無料会員登録(名前・メール・会社名だけ入力)を行うと閲覧可能!!
🔓会員登録の4つの特典
定期便!新着のESGニュース
読み放題!スペシャリスト解説
速報!お役立ち資料・ツール
会員特別イベントのご案内!
すでに登録済みの方はログイン
執筆者紹介
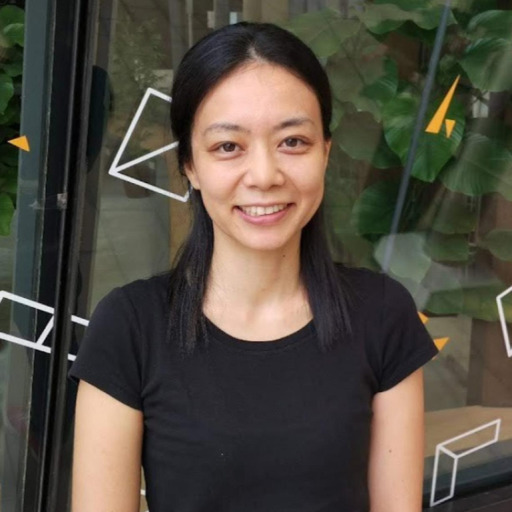 | 竹内 愛子 (ESG Journal 専属ライター) 大手会計事務所にてサステナビリティ推進や統合報告書作成にかかわるアドバイザリー業務に従事を経て、WEBディレクションや企画・サステナビリティ関連記事の執筆に転身。アジアの国際関係学に関する修士号を取得、タイタマサート大学留学。専門はアジア地域での持続可能な発展に関する開発経済学。 |