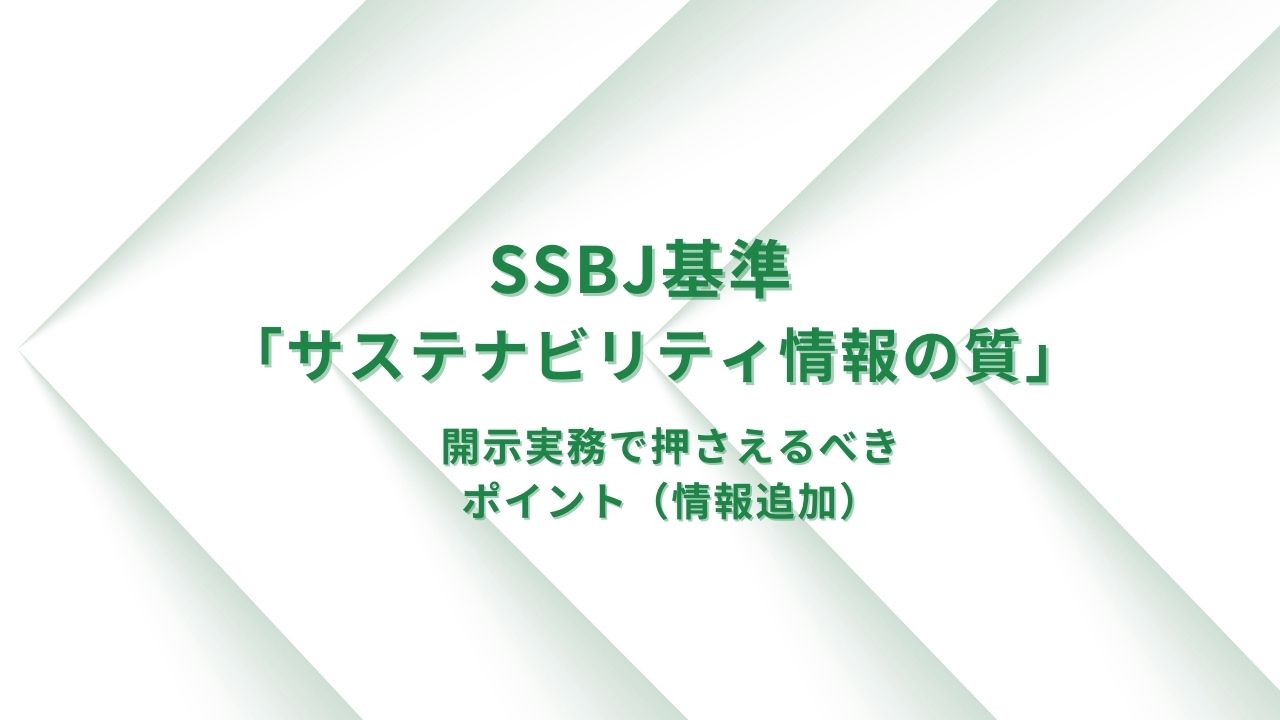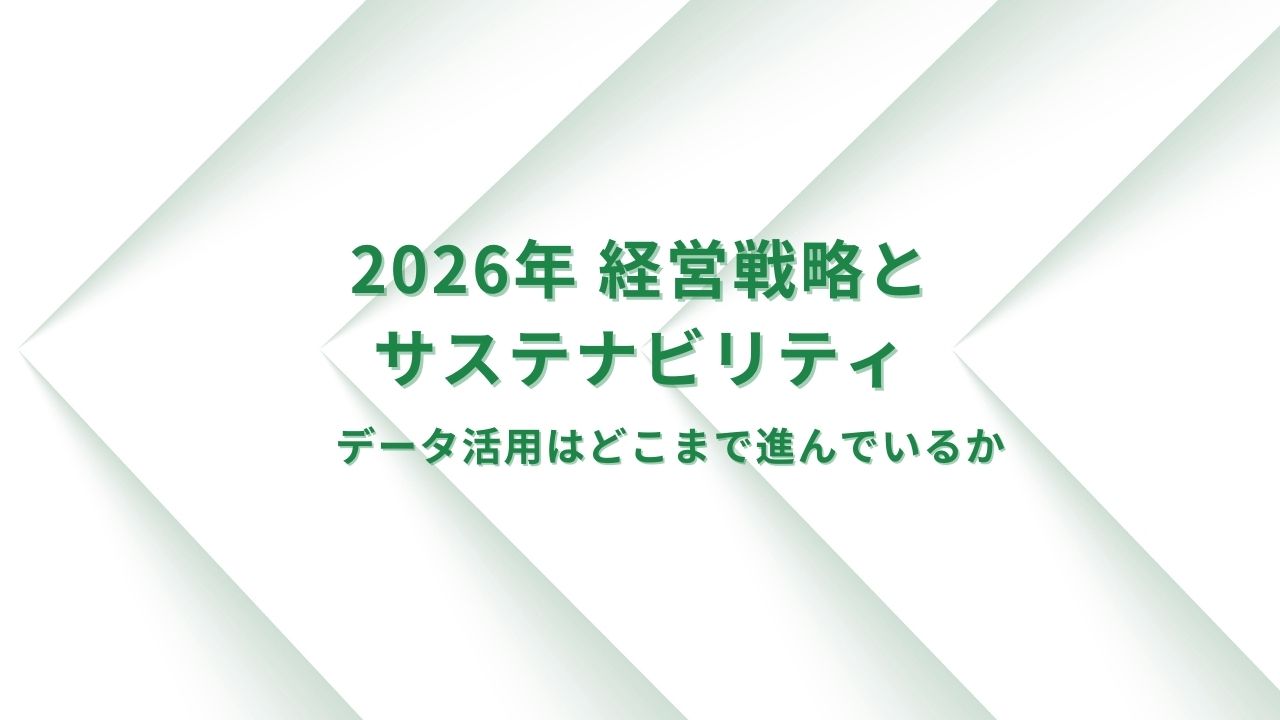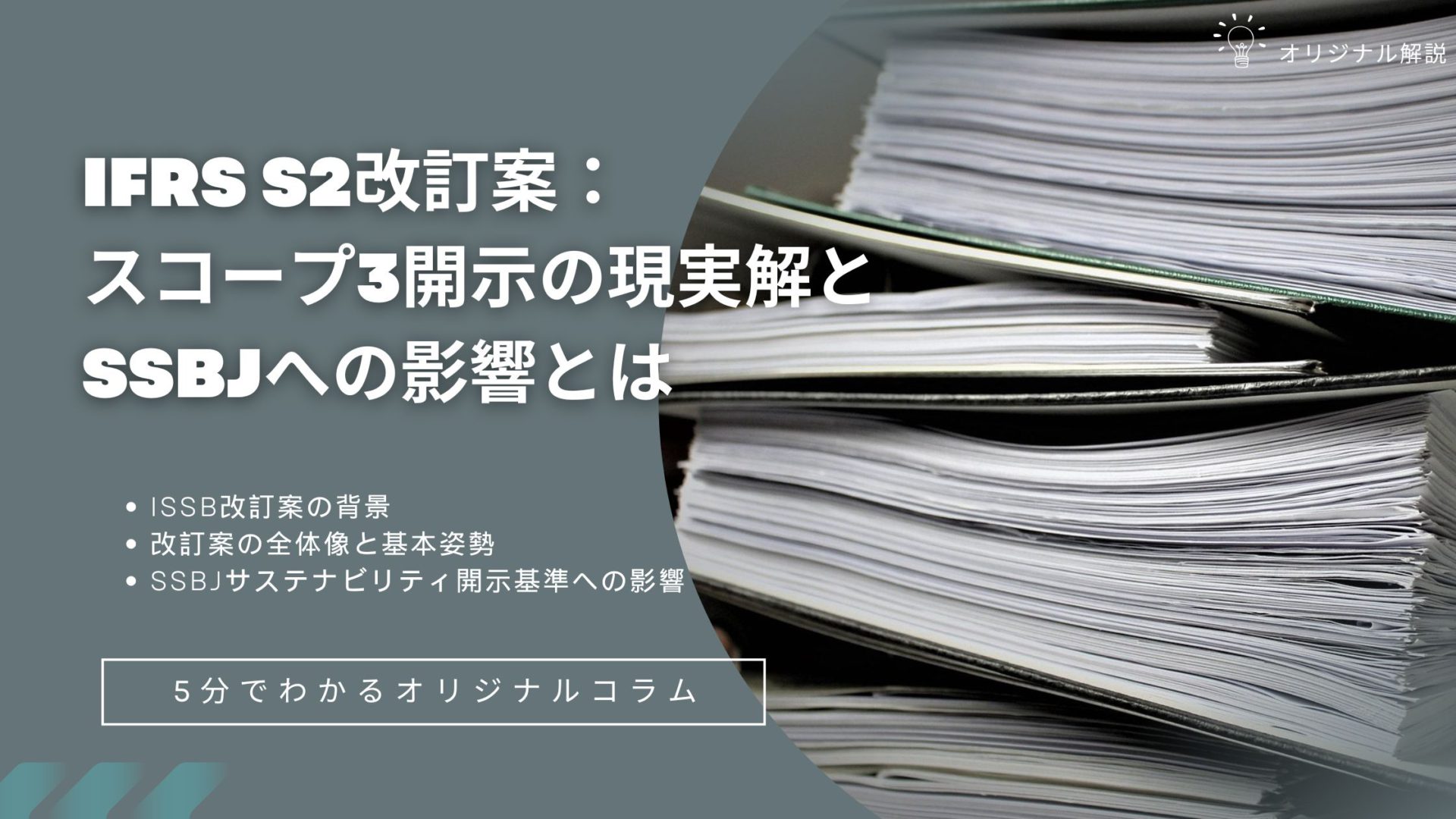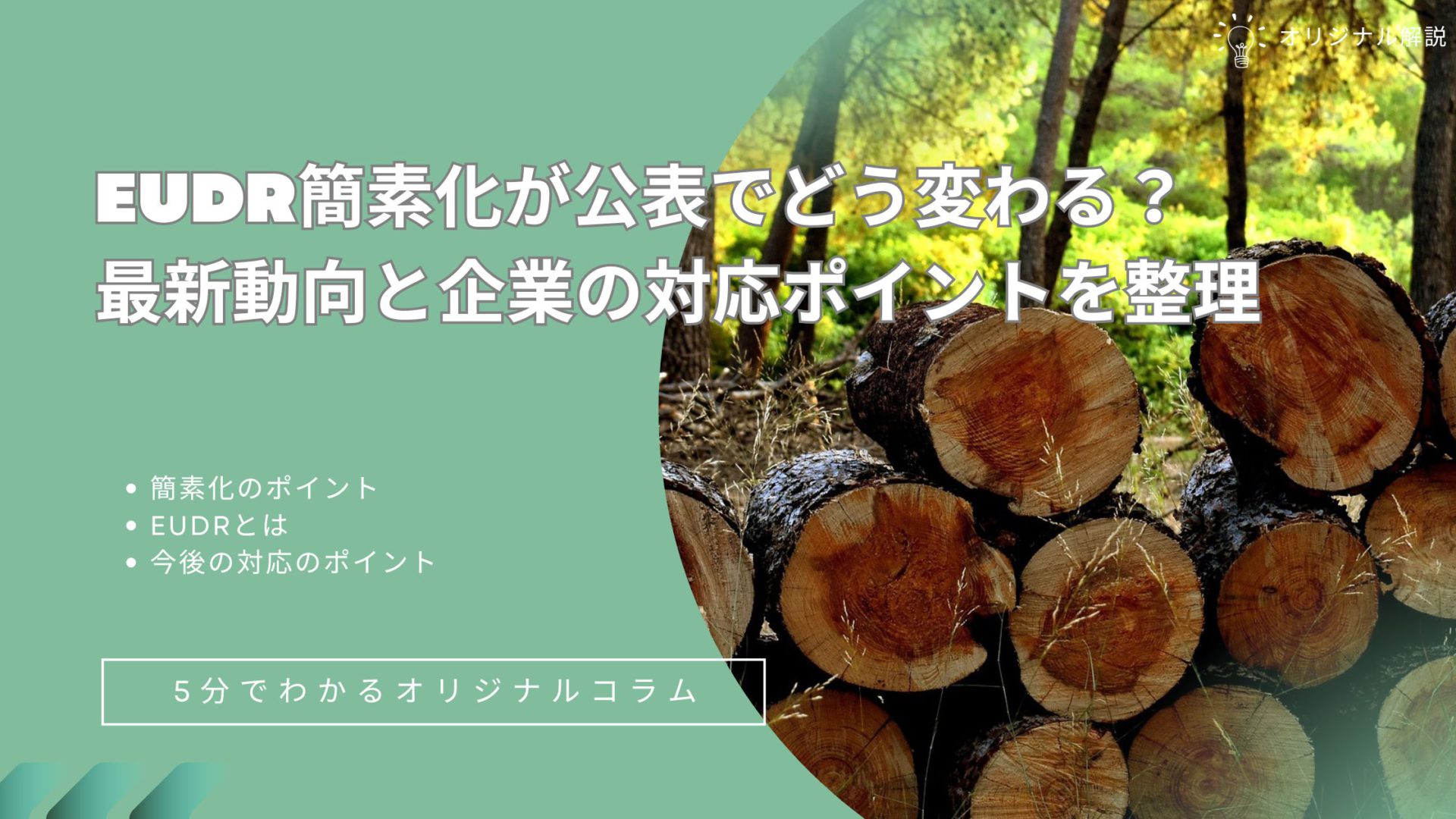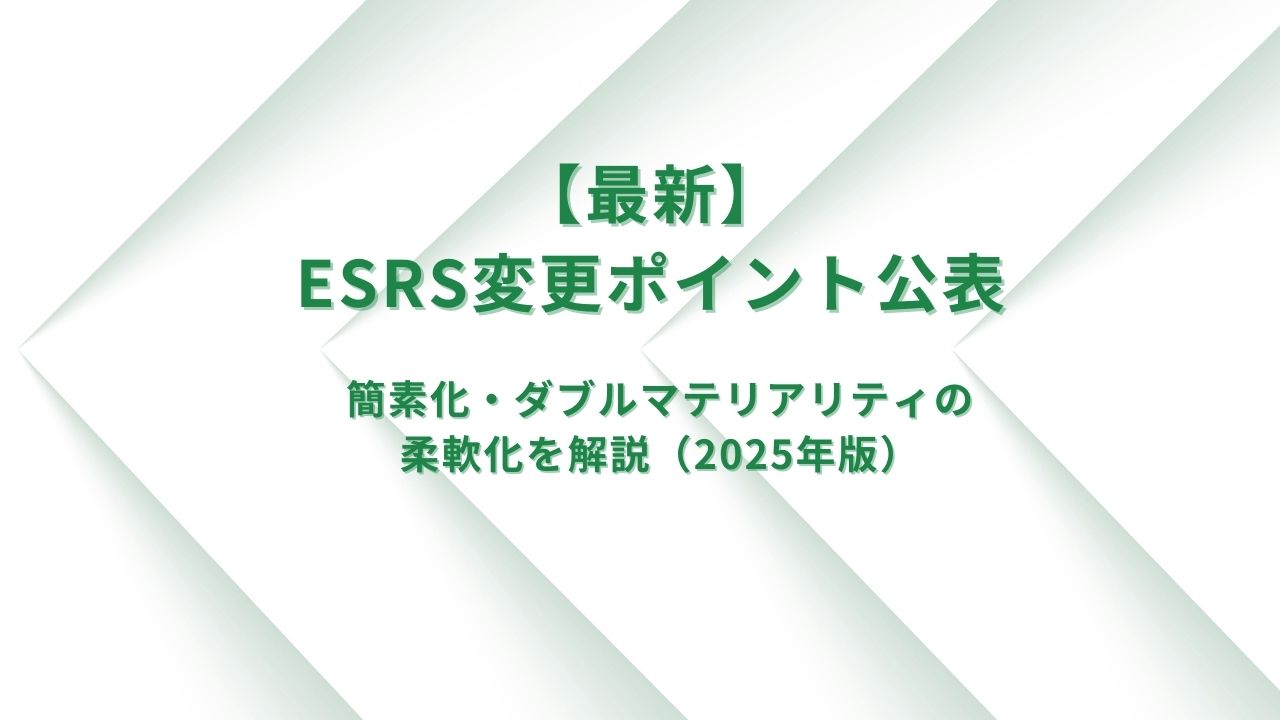TNFDの開示にはどんな内容が求められるのか?ベータ版フレームワークv0.4からポイントを抽出。

2023年9月には、TNFDのフレームワークが完成し公開される予定である。国際的に、企業の自然資本(生物多様性)への影響や依存についての情報開示の可能性が高まりつつある。一部、先進的な企業はすでに開示を進めているが、どのようなことを開示すればよいのか具体的にわからない場合もあるだろう。ここでは、TNFDの最新版のフレームワークからポイントを絞って解説する。
TNFDの概要
TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)とは、業績に影響を及ぼし得る「自然資本」について、企業や金融機関が情報開示する際に必要な、枠組みを構築するための組織、またはそのフレームワークのことを指す。日本語では「自然関連財務情報開示タスクフォース」と訳される。
TNFDは2021年6月に、自然環境の安定や保護、特に「生物多様性」が社会の安定や企業の業績に与える影響を把握することを目的として設立された。
以降のコンテンツは無料会員登録を行うと閲覧可能になります。無料会員登録を行う
すでに登録済みの方はログイン画面へ