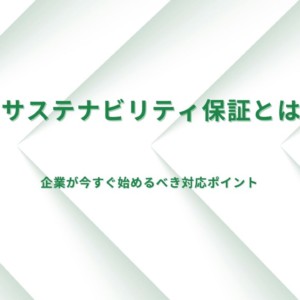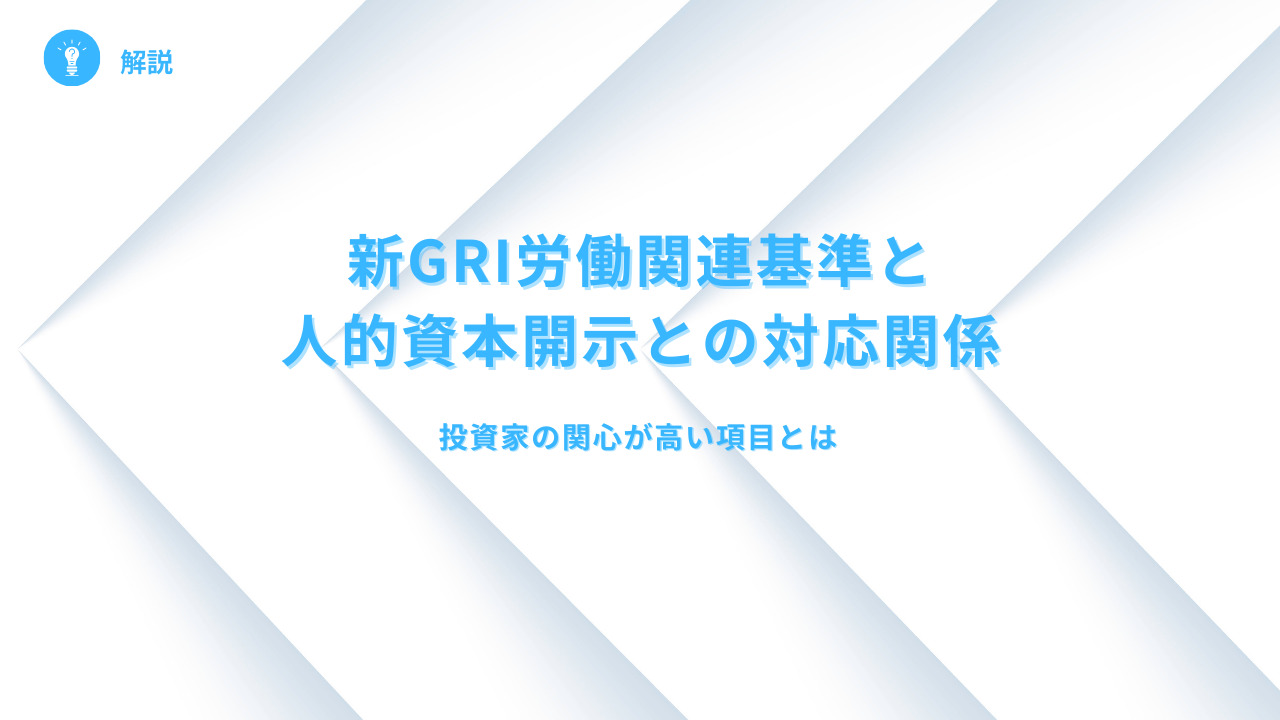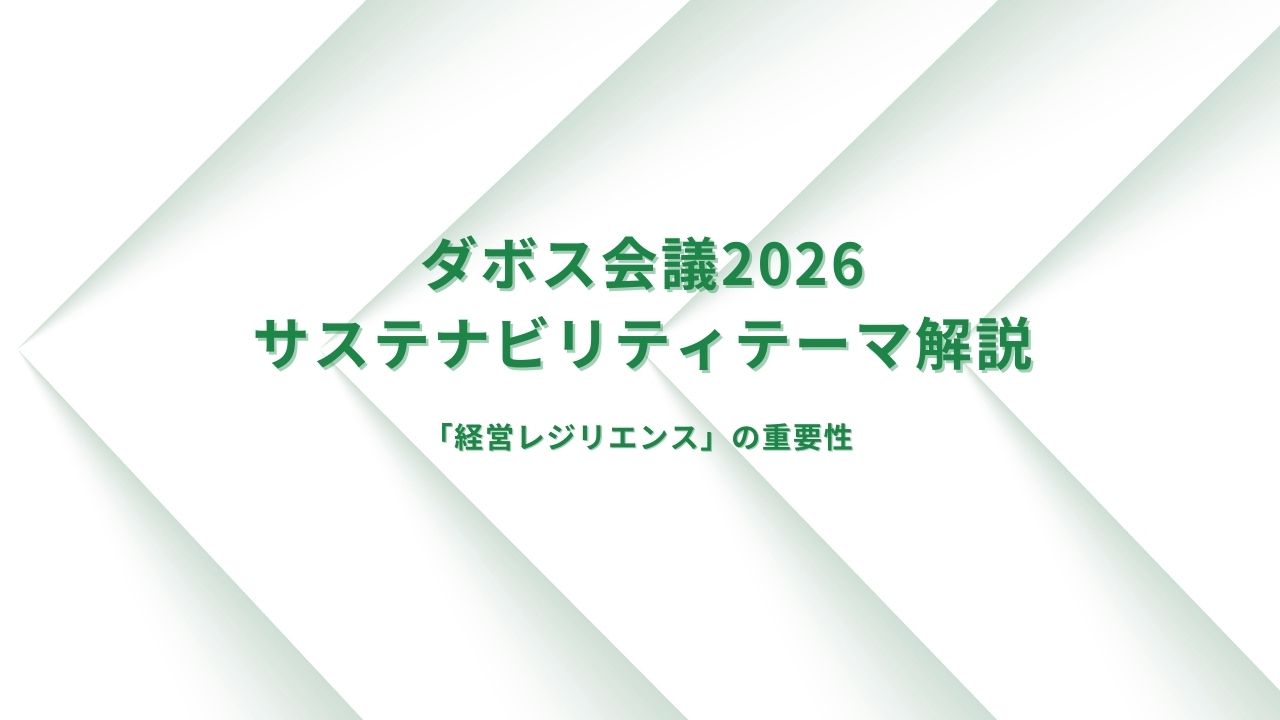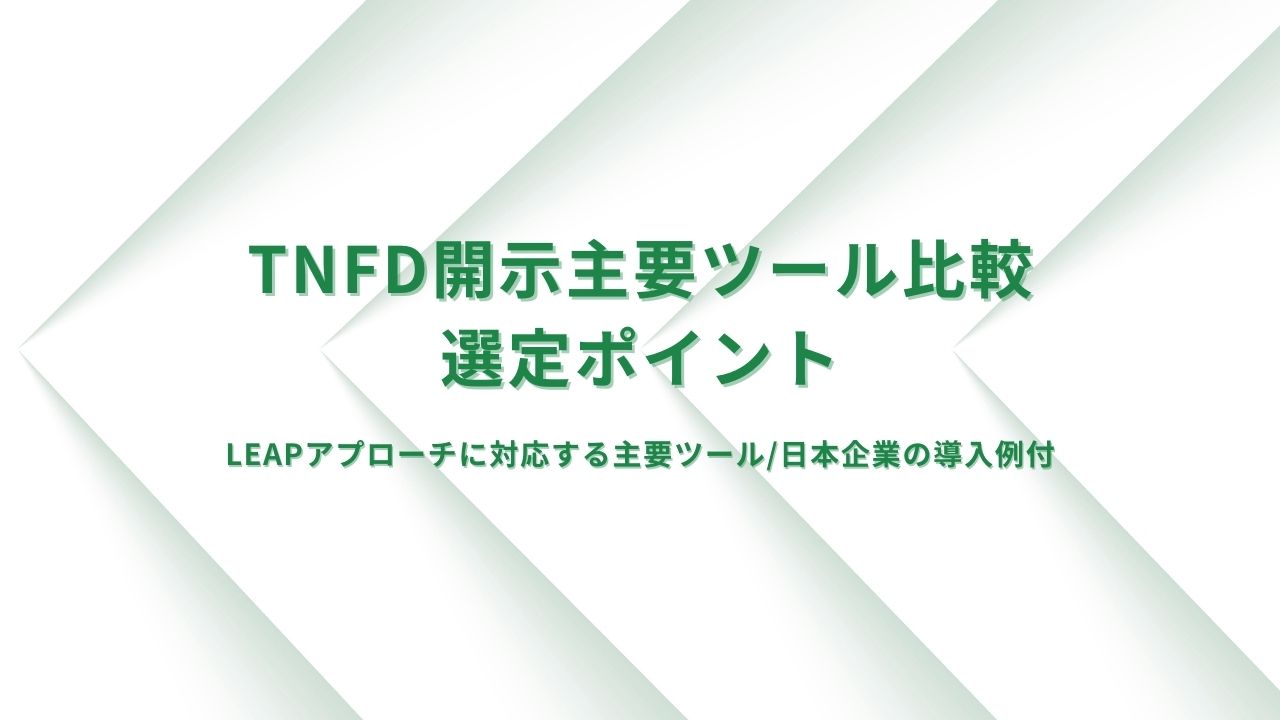人権デューデリジェンスとは何をすればよいか。海外事例から学ぶ。

人権デューデリジェンスとは、事業活動の中で人権を侵害するような行為がないか調査して対応することである。事例を用いて、サスティナブルの課題として大企業を中心に取り組みが進みつつある新しい取り組みを紹介する。人権デューデリジェンスは今後、日本でも法制化される可能性もある重要な概念だ。制度化されて、慌てて対応する前に事前に知識をインプットしておくことをおすすめしたい。
Contents
人権デューデリジェンスとは?
人権デューデリジェンスの定義
人権デューデリジェンス(以下、人権DD)とは、人権リスクを抑えることを目的とした企業活動だ。人権DDに取り組む企業は、その事業活動において、まず強制労働やハラスメントなどの人権リスク・人権を侵害するような行為がないか調査。そして起こりうるリスクが発生しないよう、詳細な分析・対策の策定のもと、具体的なアクションを実施する。
以降のコンテンツは無料会員登録を行うと閲覧可能になります。無料会員登録を行う
すでに登録済みの方はログイン画面へ