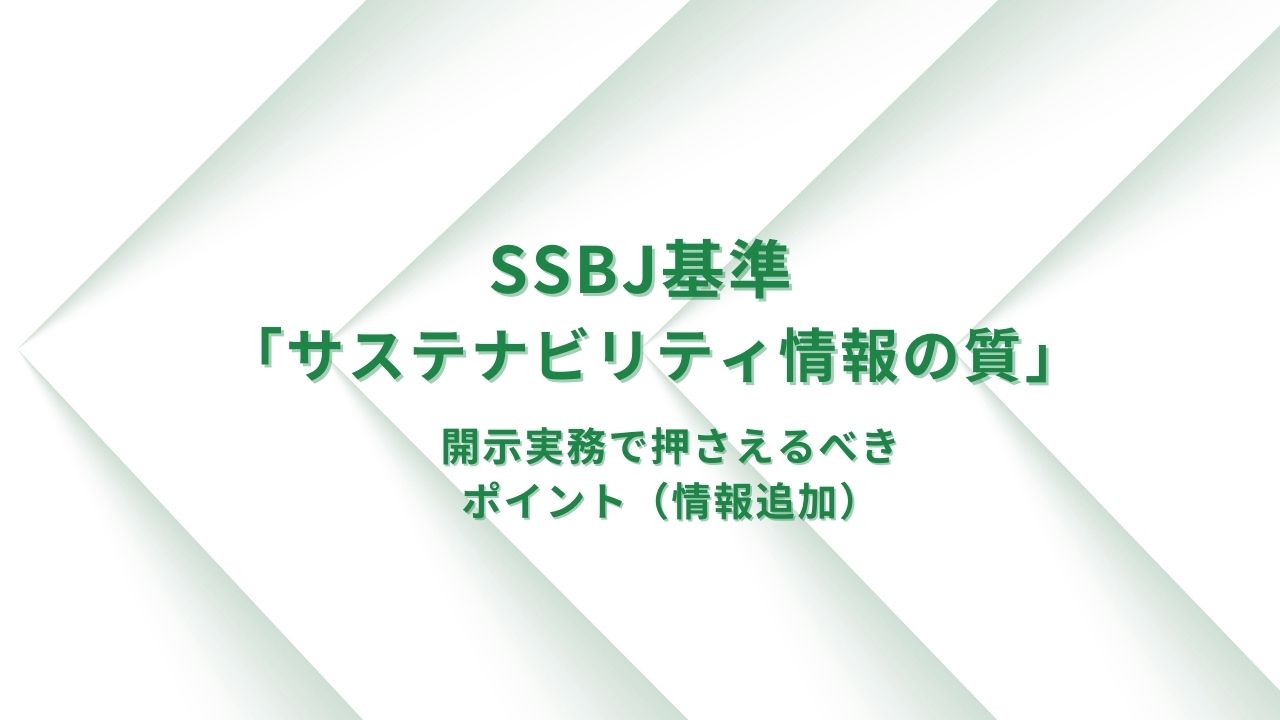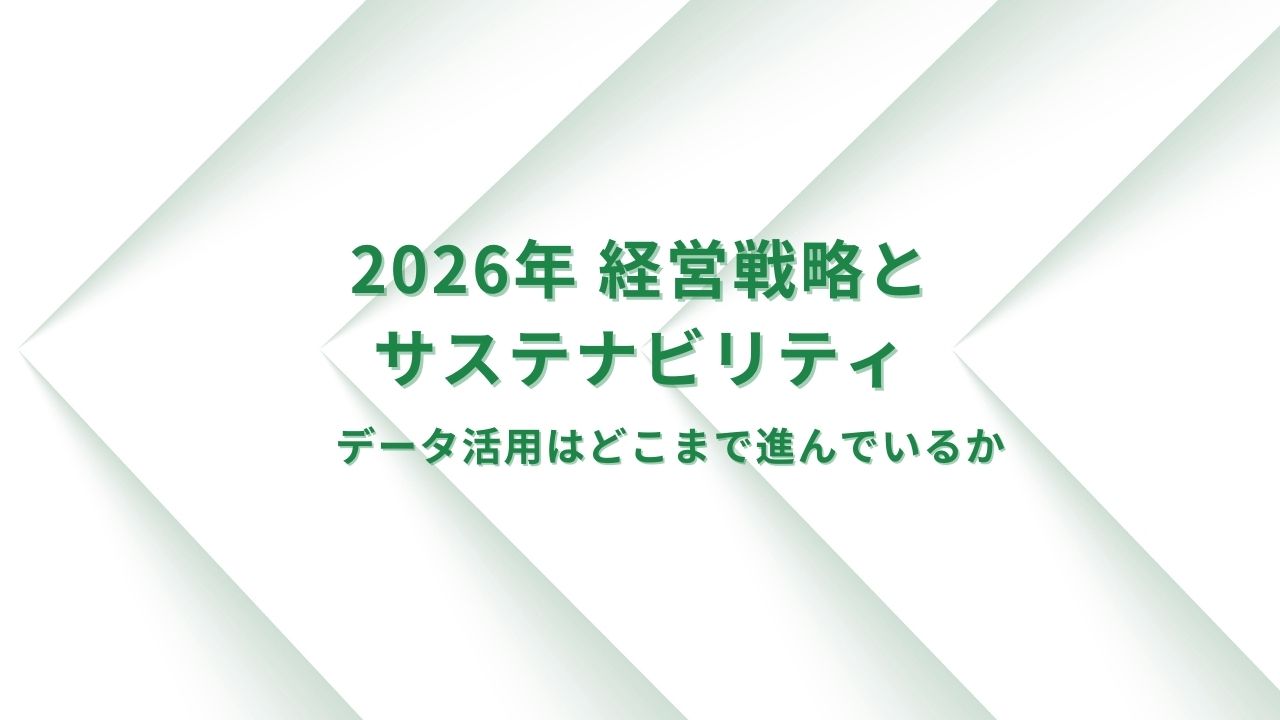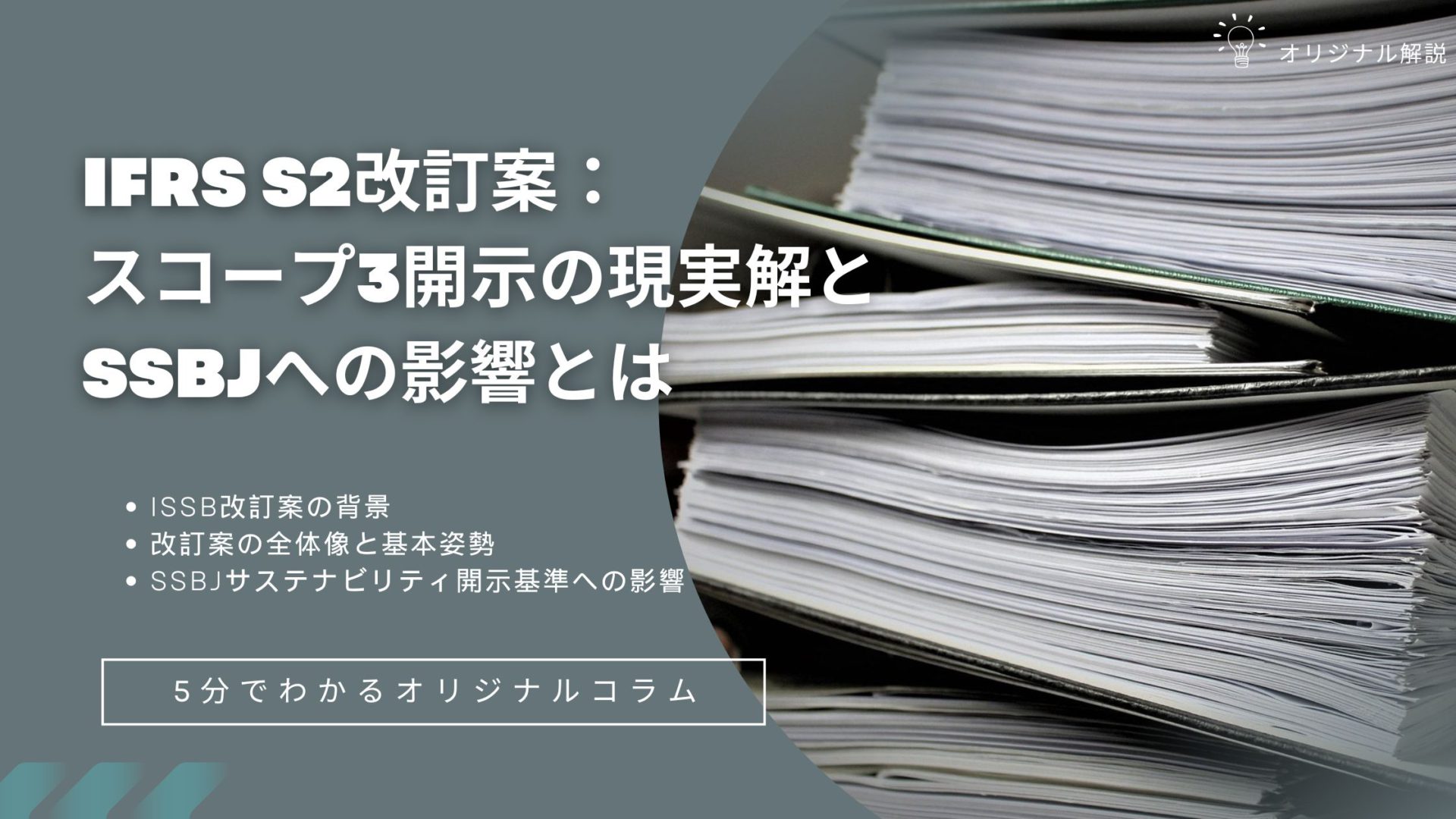サスティナビリティ情報開示基準(ISSB,CSRD)統一され進展!欧州、米国・日本の基準の動向を紹介
サスティナビリティ(非財務情報)に関する情報開示が主流化しているものの、これまで「国際的に共通」した定義や概念は存在していないのが実情である。各企業は、様々な外部機関や評価機関の基準を参照しながら、情報開示をしているのが現状だ。それぞれが個別最適に実施してきており、一部では「任意」であったサスティナビリティ関連情報開示だが、欧州、米国、日本において、基準統一や制度化の動向が見られるようになった。本稿では、基準統一や制度化の動向の概要について紹介する。
(参考)「サステナビリティ開示規制最新動向解説」をESGジャーナル内で無料ダウンロード
サスティナビリティの情報開示の変遷ー乱立から統一へー
サスティナビリティ開示基準というとGRIやISO26000などを想像するだろうか。サステナブル部門の担当者なら実感があるだろうが、2000年以降、様々な基準が乱立している。
最も古くに発行され世界的な認知度が高いのは、2000年発行のGRI(Global Reporting Initiative)のガイドライン、そして2002年のCDP(Carbon Disclosure Project)だろう。2013年のIIRC(International Integrated Reporting Council)による統合報告や、2017年のTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)と、まさに乱立状態である。
こうした乱立状態にあるのは、国際的に「ESG情報」に対する投資家の関心の高まりがある。投資家が、企業のサスティナビリティへの取り組みが企業価値に与える影響を重視するというニーズに応えるために、様々な外部機関が基準を次々に発行し、乱立化が進んだ。
以降のコンテンツは無料会員登録を行うと閲覧可能になります。無料会員登録を行う
すでに登録済みの方はログイン画面へ