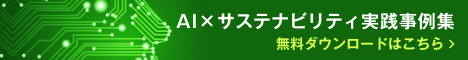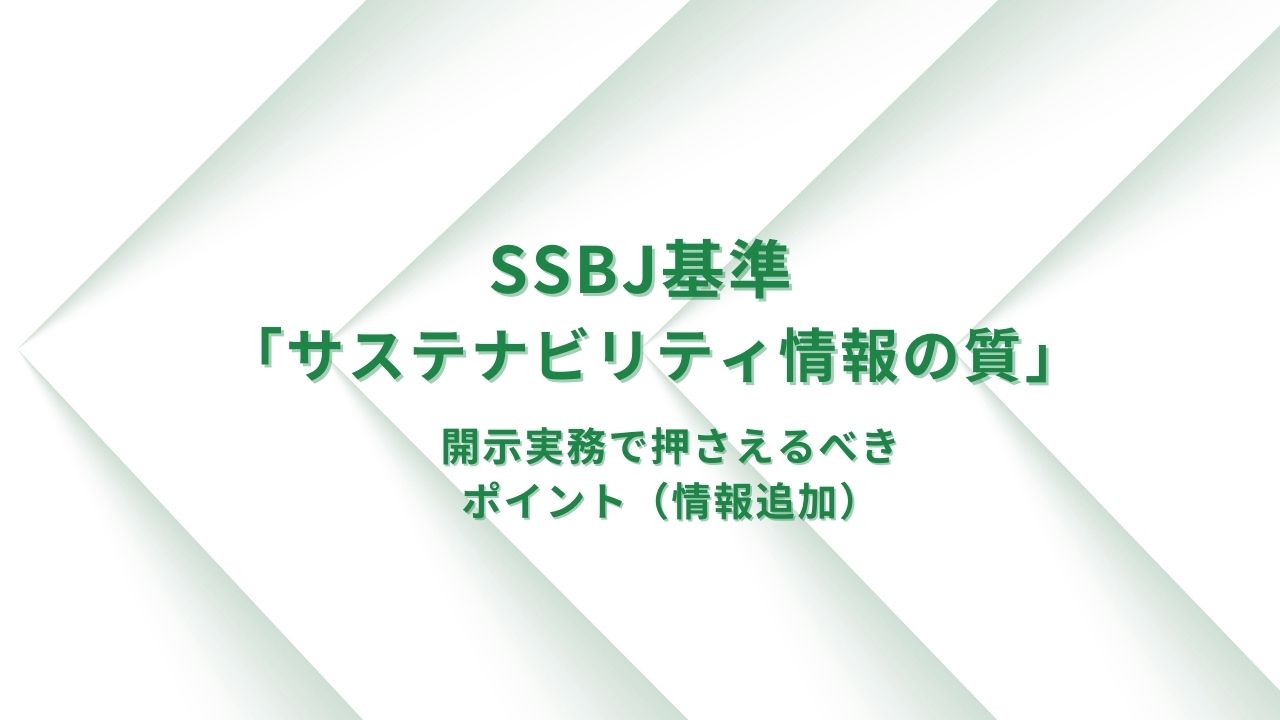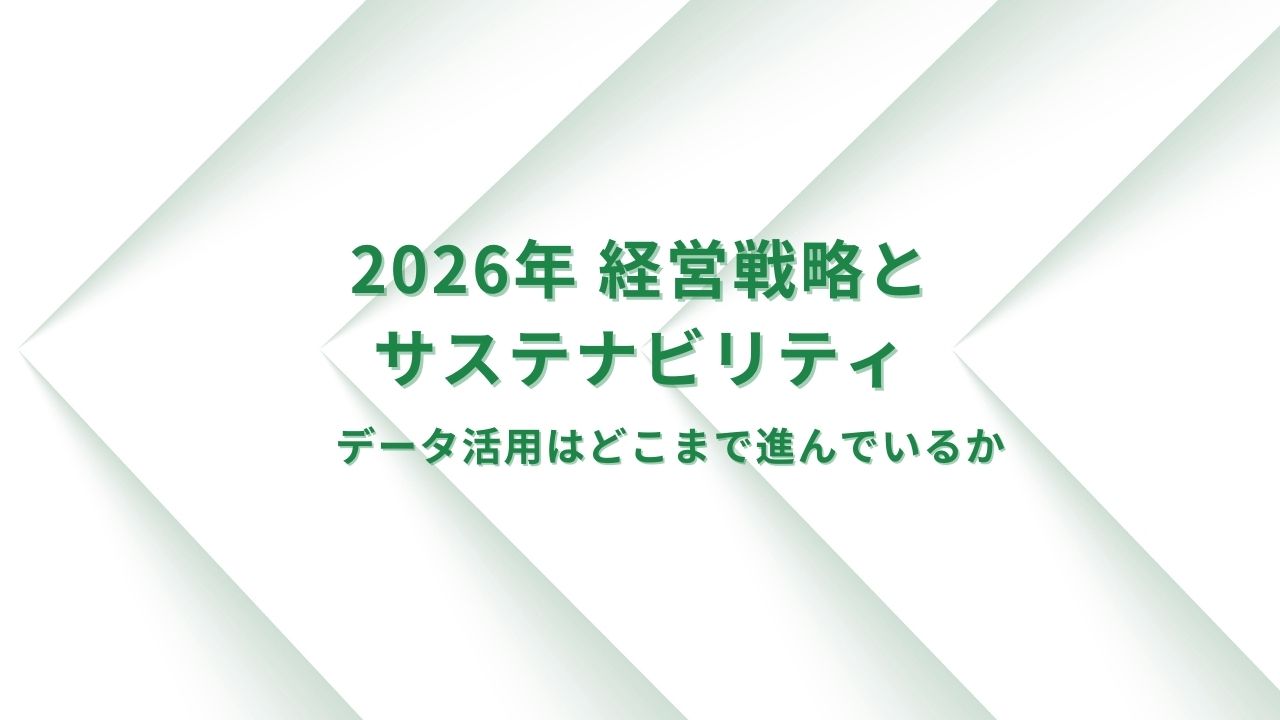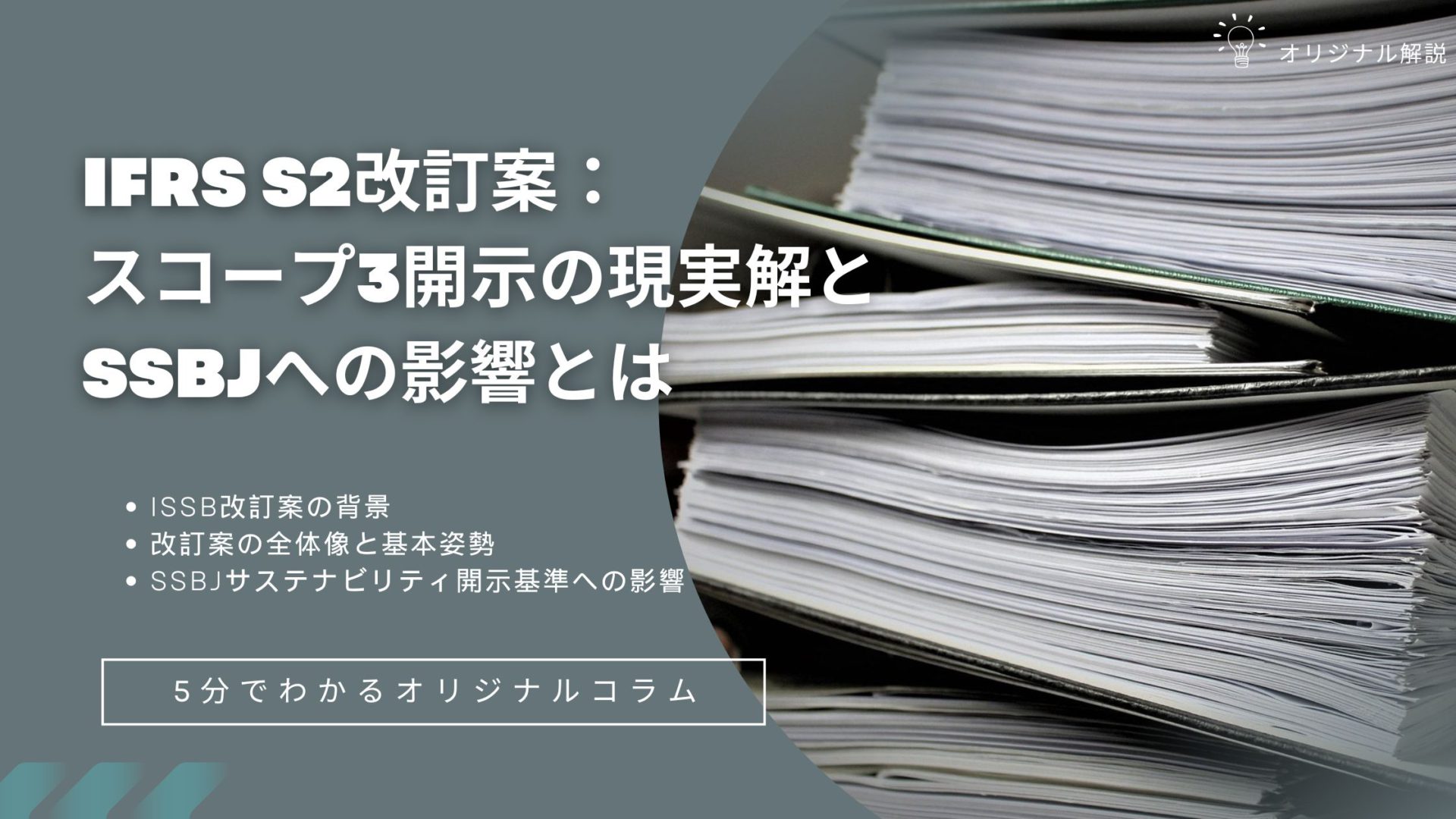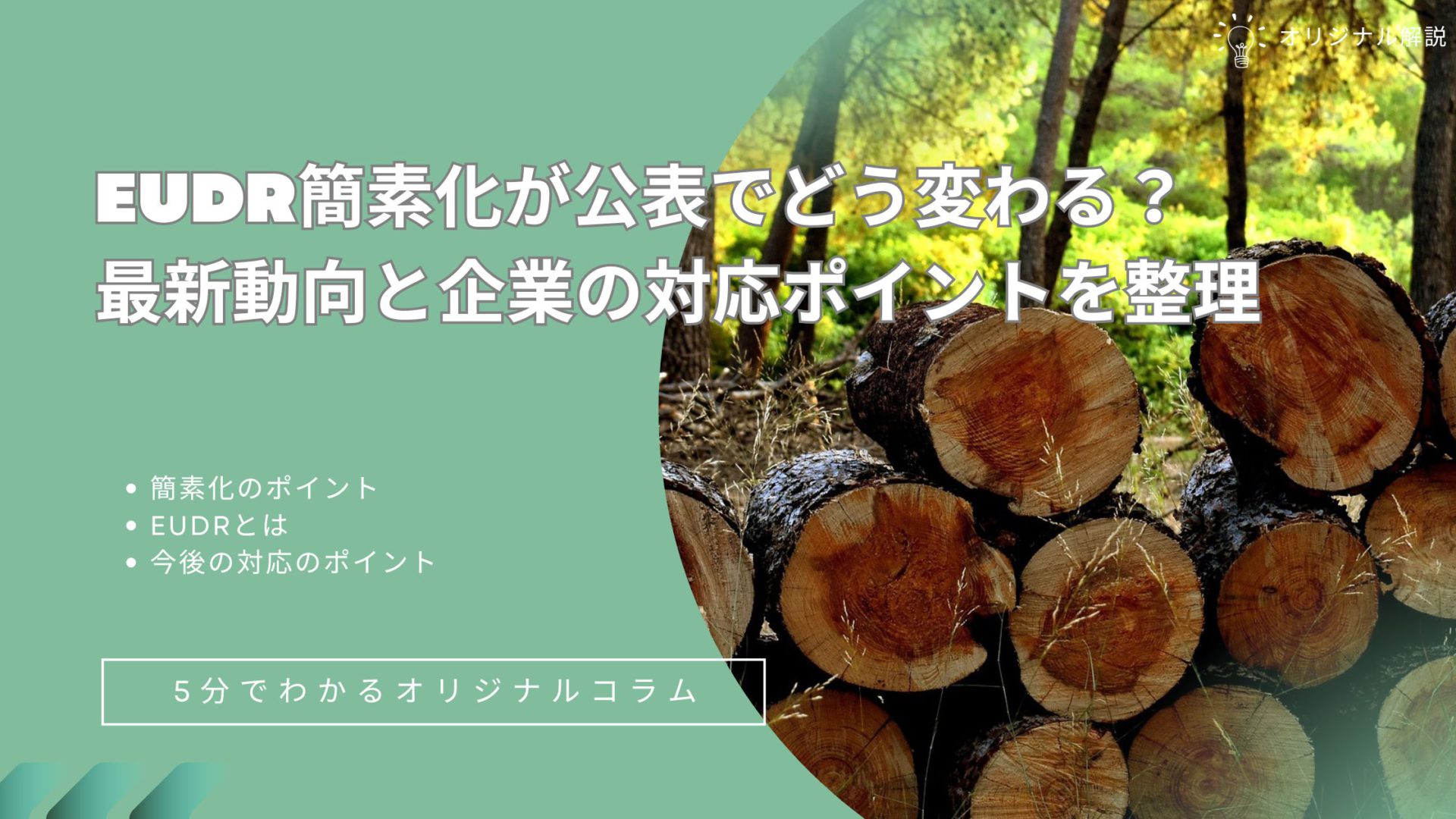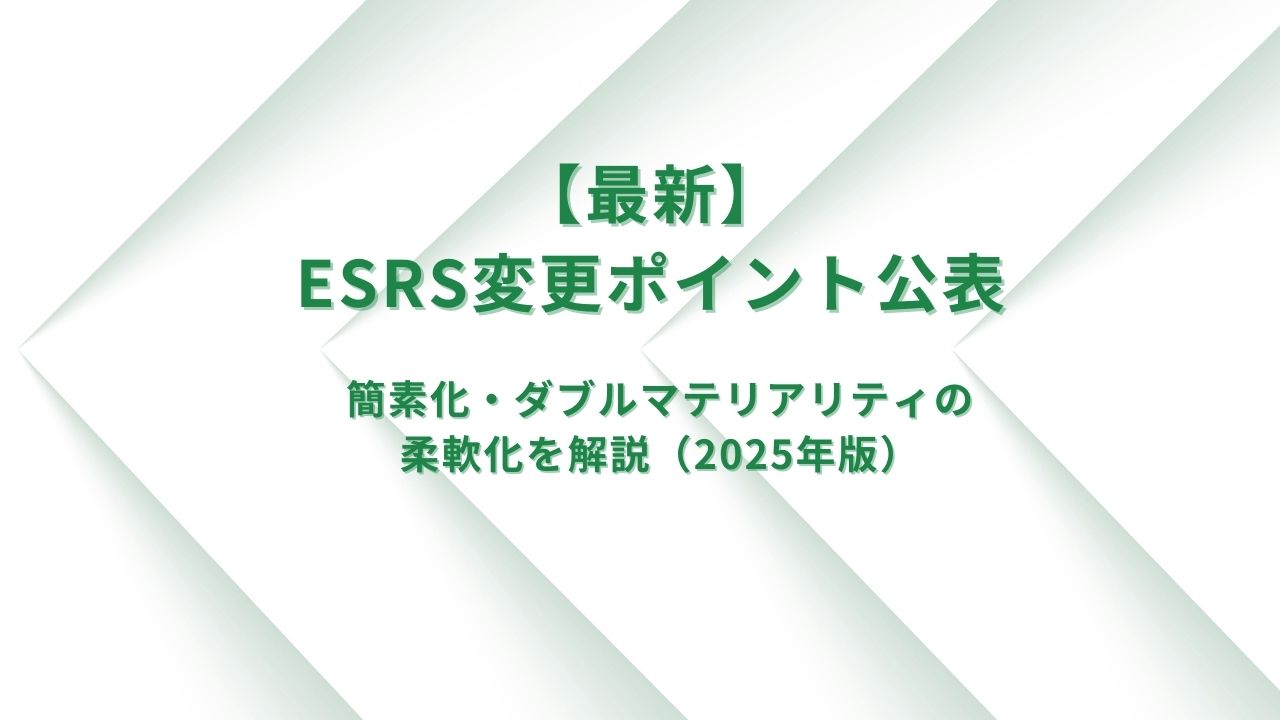人権デューデリジェンスの進め方、押さえておきたい基本手順 。

人権デューデリジェンスの進め方は、方針の策定後、対象とする範囲の特定、リスク評価の順で行われることが多い。そして、評価結果に基づき、対応策の策定を行う。その後、対応策は徐々に内容を高めていきつつ、初年度は実施内容を開示する。以降は、重大なリスクの開示やリスク評価対応のサイクルを回していくというプロセスがシンプルな手順であるといわれている。
Contents
人権デューデリジェンスが求められる背景
人権デューデリジェンス(以下、人権DD)に関する動きは各国で活発化しており、日本でも進展が見られている。ここでは、人権DDの潮流を紹介する。
人権デューデリジェンスとは
人権DDとは、人権リスクを抑えることを目的とした企業活動を指す。人権DDに取り組む企業は、その事業活動において、まず強制労働やハラスメントなどの人権問題にかかわるリスク・人権を侵害するような行為がないか調査する。そして起こりうるリスクが発生しないよう、詳細な分析・対策の策定のもと、具体的なアクションを実施する。
企業は子会社・関連会社を含む自社グループだけではなく、サプライチェーン上で発生しうる人権リスクに対しても対応しなければならない。もし人権リスクの高い取引先と事業を行っていれば、その企業は人権リスクに対処していないとしてみなされうるからだ。
つづきは無料会員登録(名前・メール・会社名だけ入力)を行うと閲覧可能!!
会員登録の4つの特典
定期便!新着のESGニュース
読み放題!スペシャリスト解説
速報!お役立ち資料・ツール
会員特別イベントのご案内!
すでに登録済みの方はログイン画面