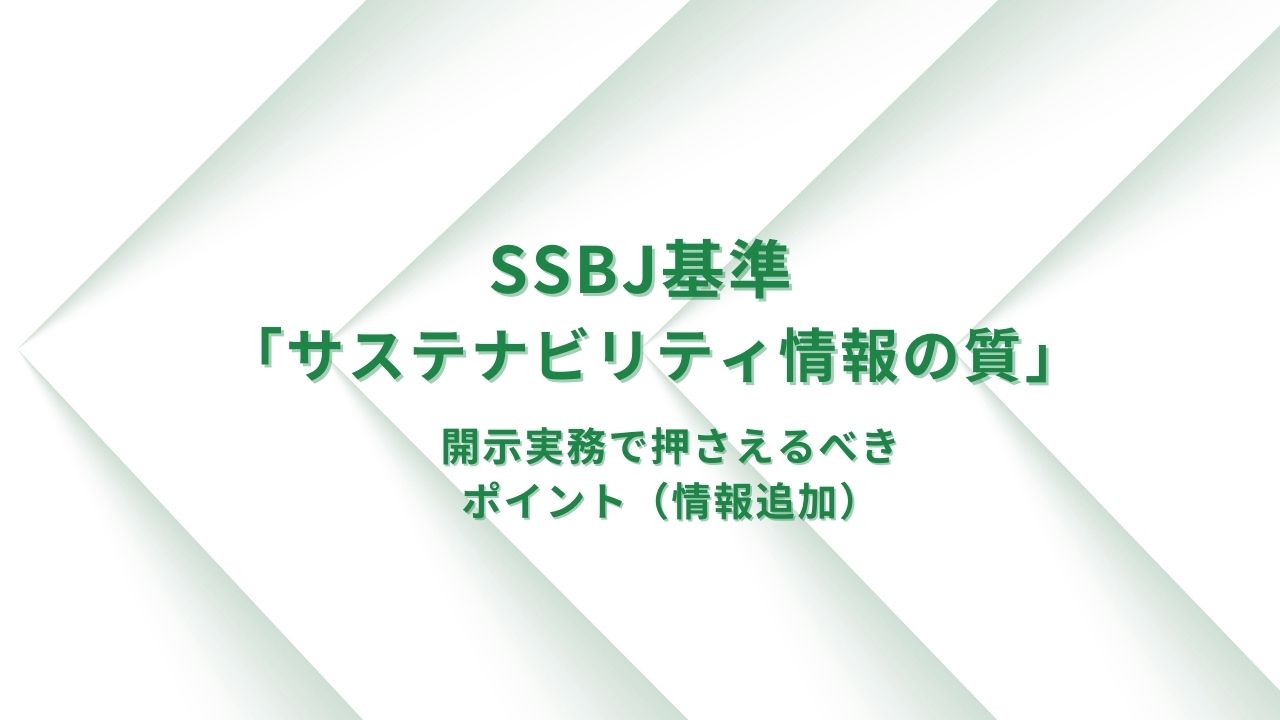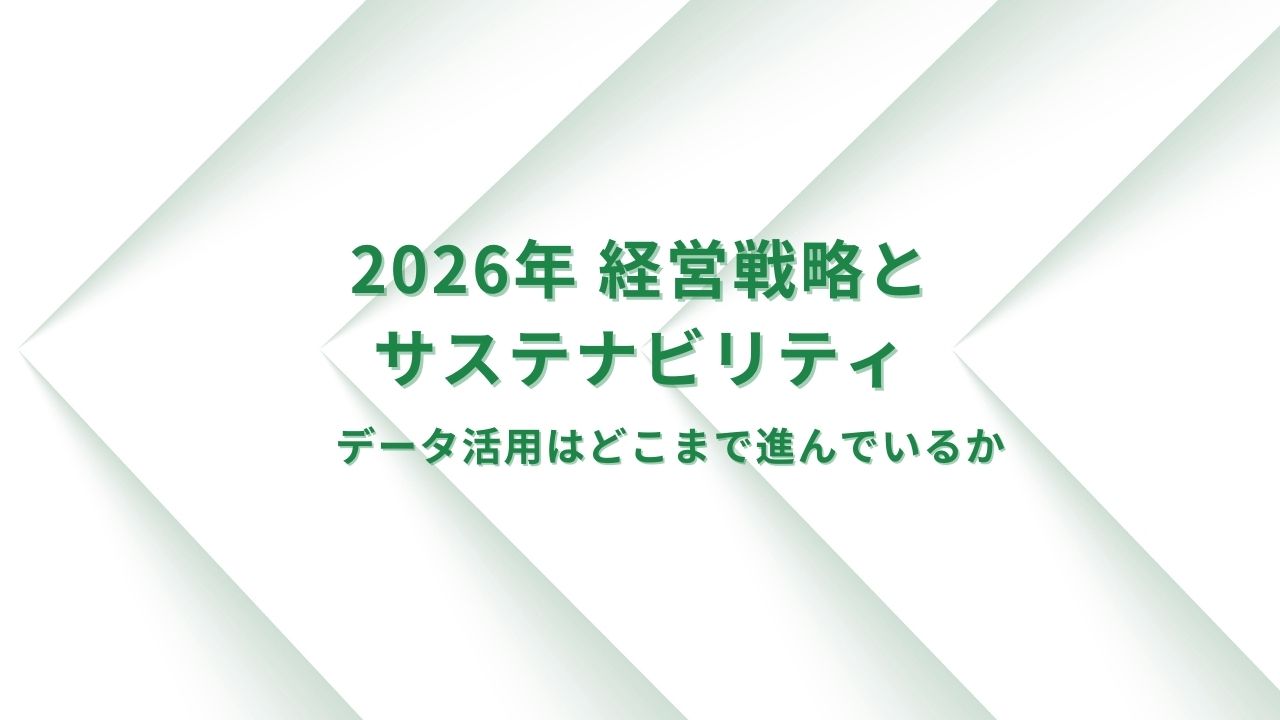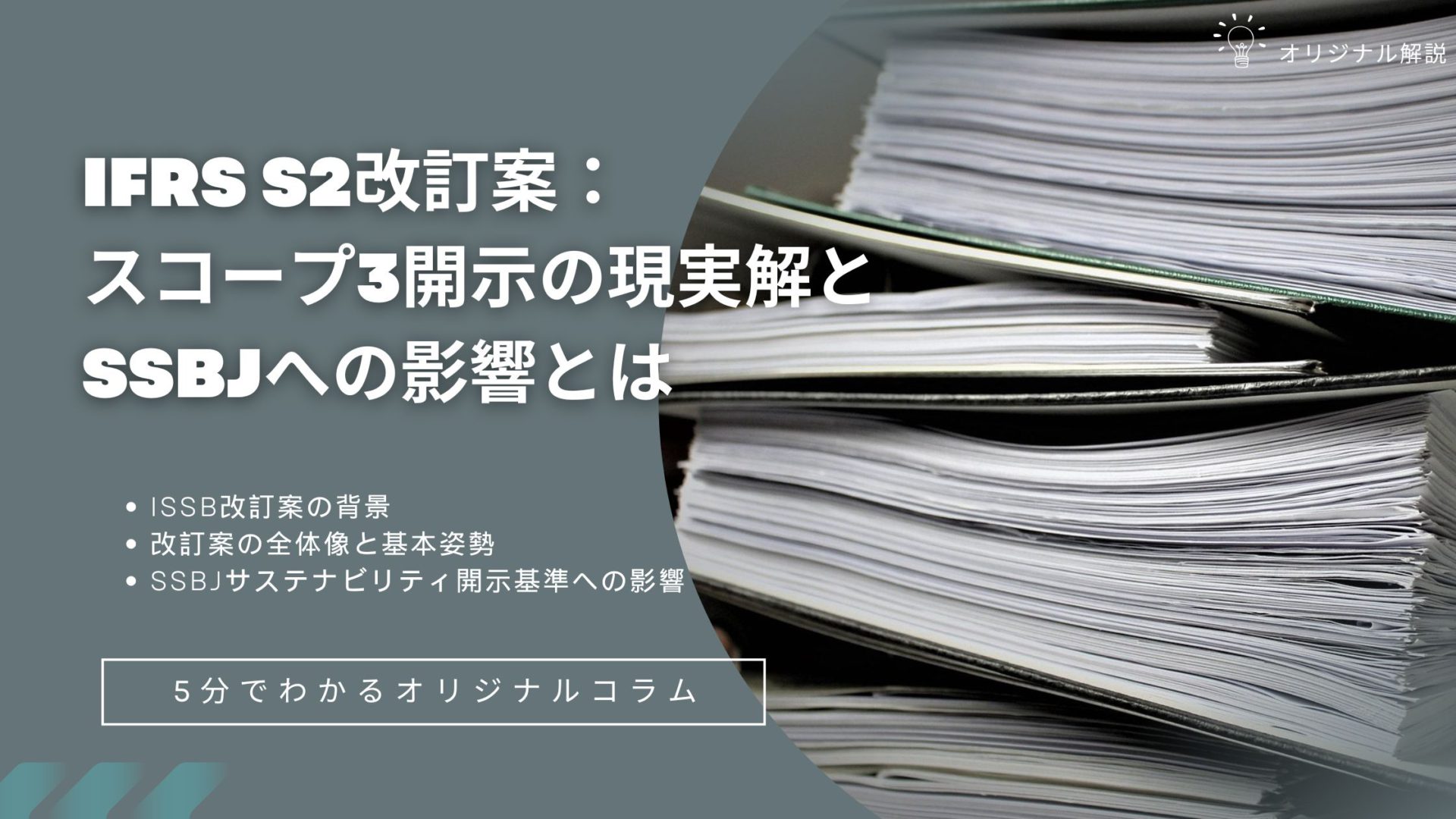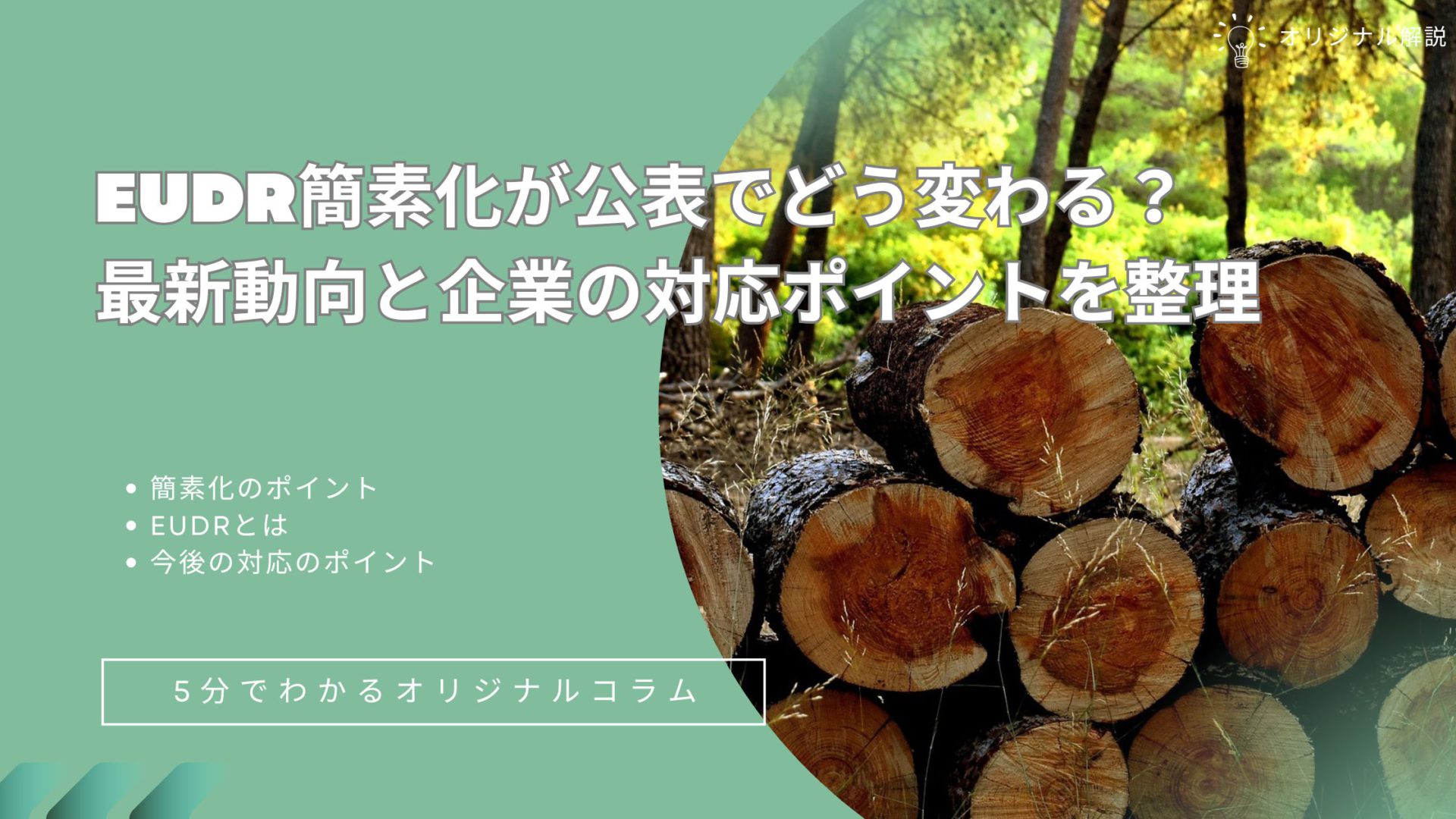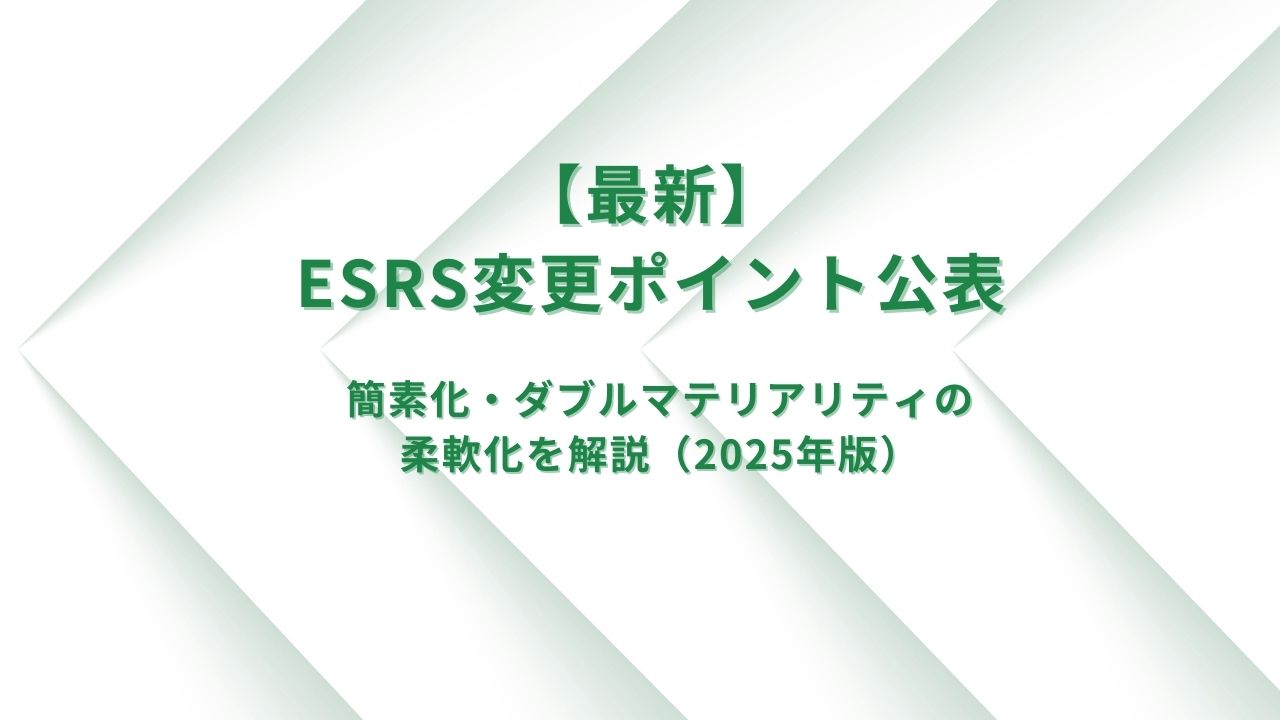複雑化する制度を整理:課題別サステナビリティ情報開示の進め方
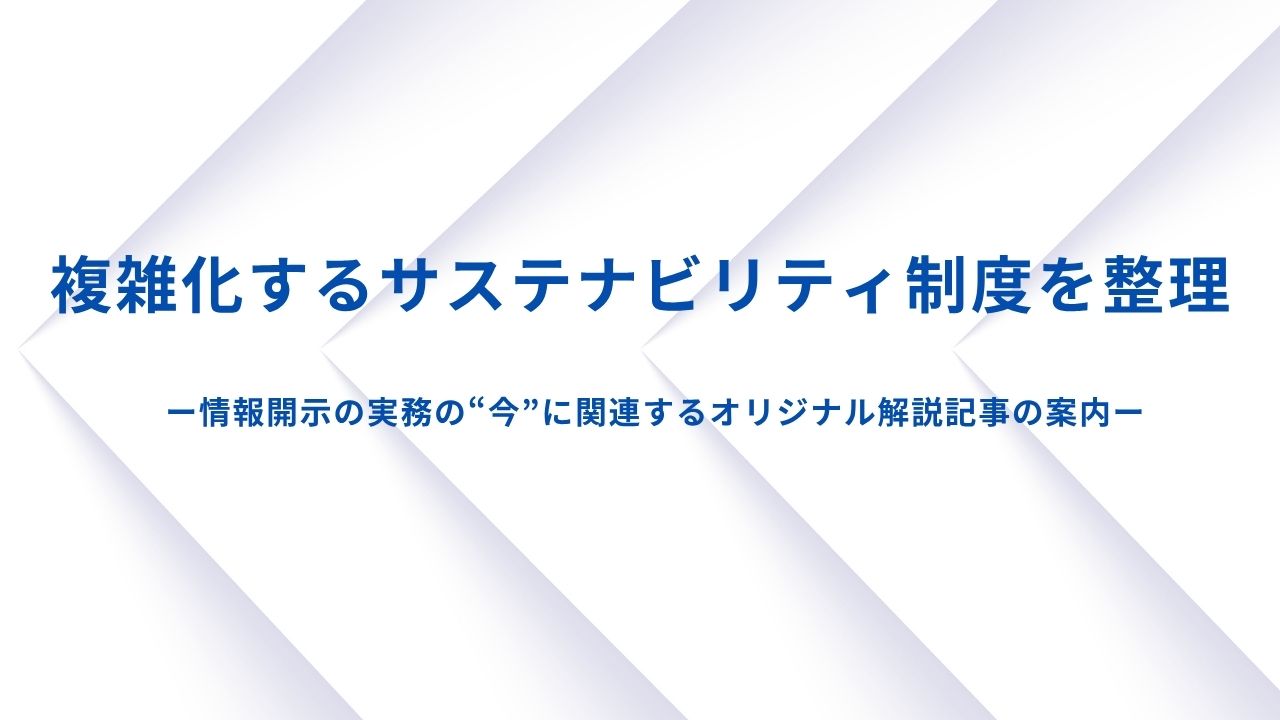
サステナビリティ情報開示の実務の“今”に応じたオリジナル解説記事のご案内
サステナビリティ情報開示に関する制度や基準は、GRI、ISSB、TCFD、ESRS、GHGプロトコル、TNFD……それぞれの基準やフレームワークは、重なり合いながら制度化されていくなかで、「自社にとってどの基準が重要なのか」「どこから着手すべきなのか」が見えづらくなっている企業も少なくないだろう。
また、企業によっては体制やリソースの面で一度にすべての領域に対応することが難しく、優先順位や進め方に悩むケースがある。特に、専任部門が少人数である場合、負荷を分散しながら段階的に対応を進める視点が現実的かつ重要となる。
本記事では、自社の情報開示に関する課題を切り口に、関連する基準やフレームワークを整理している。それぞれのテーマに対応したオリジナル解説(コラム)も紹介しているため、目的に応じて自社の実務に役立ててほしい。
以下は、主な5つの課題である:
- サステナビリティ報告全般の質を高めたい
- 財務的に重要な情報に特化して開示したい
- 気候変動リスクを戦略的かつ定量的に把握したい
- 日本企業として制度対応を進めたい
- トピック別に対応を見直したい(自然資本・人的資本・人権など)
気になるテーマや自社の課題に近い章から読み進め、オリジナル解説を実務のヒントとして活用していただきたい。
サステナビリティ報告全般の質を高めたい
サステナビリティ情報開示の全般的な質の向上を目指すのであれば、まずは国際的な開示基準のGRIを改めて見直すことが有効であろう。また、現行のESRS(欧州サステナビリティ報告基準)は、人的資本や人権、調達、ガバナンスといった非財務領域を幅広くカバーするフレームワークとして、開示の構造や優先順位を整理する手がかりになる。GRIは、企業が「自らの活動が社会・環境にどのような影響を与えているか(アウトサイド・インの視点)」を可視化するための枠組みを提供する。
ただし、現行のESRSについては、オムニバス草案の発表以降は適用対象が限定的となり、項目削減が進んでいるが、非財務領域における情報の網羅性や粒度を確認する「辞書的な資料」として実務に活用できるだろう。
まずは、こうした基準の構成や論点を俯瞰し、自社の現状と照らし合わせながら、優先して取り組むべきテーマを明らかにすることが重要である。
実施ポイント
- GRIやESRSの主要トピック(気候変動、人的資本、人権、サプライチェーンなど)の粒度を確認するだけでも十分。
- すでに社内にある人事・調達・労務統計などを「開示に使える情報」として見直す。
補足説明
GRIは、自社のサステナビリティ活動全体を見渡すための「最初の地図」として適している。項目数が多く感じられるが、すべてを開示する必要はなく、自社に関連性のあるテーマに絞って取り組むだけで開示の質は向上する。
関連コラム
財務的に重要な情報に特化して開示したい
投資家や資本市場を意識した開示の質を高めたいと考える企業にとっては、財務マテリアリティに特化した国際基準を起点に、自社にとっての重要情報を見極めることが有効である。
こうした目的において参照すべきは、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)のIFRS S1/S2および、SASBスタンダードであろう。
SASBスタンダードは、業種ごとに異なる財務的影響の大きいESG課題を特定したものであり、実務上はの参考資料とされている。
まずは、自社の属する業種におけるマテリアリティ項目を確認し、現在の開示と比較することから着手するとよいだろう。これにより、投資家との対話の軸や、開示の粒度を調整する起点を得ることができる。
実施ポイント
- ISSB/SASBの基準構成と業種別マテリアリティを確認する
- 自社の開示項目との対応状況(開示済・未対応)を簡単に棚卸しする
補足説明
ISSBは、「投資家にとって意思決定に資する情報」を特定し、開示することを目的としている。日本ではこの基準をベースに、SSBJが上場企業向けの国内準拠基準が策定されており整合性が高い。
関連コラム・お役立ち資料
- 2025年版|主要 5 大評価機関の解説(S&P(CSA), CDP, MSCI, FTSE,Sustainalytics
気候変動リスクを戦略的かつ定量的に把握したい
気候変動が企業に及ぼす影響を戦略的に把握し、開示の質を高めるには、定性的な経営判断と、定量的な温室効果ガス排出量の管理とを両輪で整えることが重要である。
この点において、まず取り組むべきは、TCFD提言およびIFRS S2(気候関連開示基準)の内容を踏まえた情報開示の棚卸しである。また、それを支える基礎データとして、GHGプロトコルに基づく排出量算定の体制構築も欠かせない。
TCFDは、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4本柱で構成され、企業の気候関連リスクの捉え方と対応方針を明示する枠組みを提供する。IFRS S2はこれに準拠しつつ、スコープ1・2・3の排出量の開示や、シナリオ分析の透明性、指標の裏付けとなる定量的根拠の整備を求めている。
一方、排出量算定に関しては、GHGプロトコルが事実上の国際基準となっており、スコープ1(自社の直接排出)とスコープ2(購入電力等による間接排出)から着手するのが一般的である。スコープ3(バリューチェーン全体)については、推計値でも構わないため、まずは可能な範囲で算定方法を定めることが現実的な一歩となる。
実施ポイント
- TCFDの4本柱に沿って、自社の開示内容と開示していない項目を整理する
- GHGプロトコルに基づき、スコープ1・2の排出量を概算でも算定してみる
- スコープ3については、対象カテゴリの全体像を把握し、推計方法の目処を立てる
補足説明
気候変動に関する開示は、単なる報告業務ではなく、経営判断や中長期戦略との整合が問われる領域である。そのため、サステナビリティ部門単独ではなく、経営企画・リスク管理部門との連携が必要になる。また、排出量算定は、最初から精緻な実測値を揃えるのは難しい。ただし、どの排出がどのカテゴリに当てはまるかを理解し、どの程度の精度で算定できるかを説明できる状態を目指すことが、制度対応や社内啓発の第一歩となるだろう。
関連コラム導
日本企業として制度対応を進めたい
サステナビリティ情報開示への対応を制度的な観点から進めたい企業にとって、まず確認すべきは、日本国内における開示制度の動向である。
有価証券報告書へのサステナビリティ情報開示、SSBJのサスティナビリティ開示基準などの制度対応を充実させることが重要だ。
また、脱炭素に向けた政策的枠組みである「GX排出量取引制度(GX-ETS)」への対応も必要である。これらの制度は、気候変動関連の開示義務そのものを課すわけではないが、TCFDやISSBに基づいた情報整理が前提とされている点には留意が必要だろう。
こうした制度への対応を考える際には、まず「自社がどの制度に該当し得るか」「今後義務化される可能性があるのは何か」を明確にすることが、無駄のない実務設計につながる。
実施ポイント
- SSBJ基準と有価証券報告書での開示項目の重複など要件の関係性を整理する
- GX-ETSへの参加・非参加にかかわらず、制度の構成と基本用語を把握する
- 他社の対応状況(有価証券報告書、GX対応レポート等)を調査し、自社とのギャップを確認する
補足説明
日本企業の多くは、すでに任意でTCFDに準拠した開示を行っているが、今後は制度的な開示枠組みの中で、その水準をどう位置づけるかが問われる。また、GX移行計画に関しては、2026年度からの発効が予定されており、早期に情報収集と社内合意形成を進めておくことが、後の対応負荷を軽減する鍵となる。
関連コラム・お役立ち資料
トピック別に対応を見直したい(自然資本、人権、人的資本など)
制度対応や全体的な開示体制がある程度整ってきた企業にとって、次に直面するのがトピック別・テーマ別の深化であろう。
具体的には、TNFD(自然資本)、人的資本、ビジネスと人権、バリューチェーン管理、人権デューデリジェンス、サステナブル調達など、分野横断的な課題にどう取り組むかが問われるようになってきている。
これらの領域はいずれも、一部の制度(例:ESRS、GRI、OECDガイドライン)では明確に開示要件が定義されているものの、現時点で必ずしも開示義務があるわけではない。そのため、開示やリスク管理の深度において企業ごとの取り組みの差が生まれやすい領域である。
まずは、すべてを網羅しようとするのではなく、自社にとって影響が大きいテーマを一つ選び、情報収集・関係部門との対話・開示方針の整理といった初期ステップから始めるのが現実的である。
実施ポイント
- 自社が影響を与える可能性が高い/依存しているテーマ(自然、人権、労働など)を一つ選ぶ
- そのテーマに関連する基準(例:GRI 304、ESRS E4、ILOなど)やガイドラインを確認する
- 社内の該当部門(人事、調達、サプライチェーン管理など)と情報交換を始める
補足説明
自然資本に関しては、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)が2023年に最終版フレームワークを公表し、「Locate–Evaluate–Assess–Prepare(LEAP)」というアプローチを提案しているので理解を深めておくとよいだろう。
また、ビジネスと人権に関しては、人権デューデリジェンス指針(外務省)、OECDガイドライン、TISFD(不平等・社会関連財務情報開示タスクフォース)など、制度・規範が整理されてきており、いずれも中長期的には企業の対応が求められる領域である。
関連コラム
執筆者紹介
 | ESG Journal 編集部 専門知識を備えたライター陣と鋭い視点を持つ編集チーム。国内外の最新動向の発信と独自の解説。企業のサステナビリティ情報開示の向上を目指す実践的な資料と価値ある情報の提供。3000人を超えるサステナビリティ担当者や関心の高い会員に支持される情報源。持続可能な未来を支える情報基盤。 |