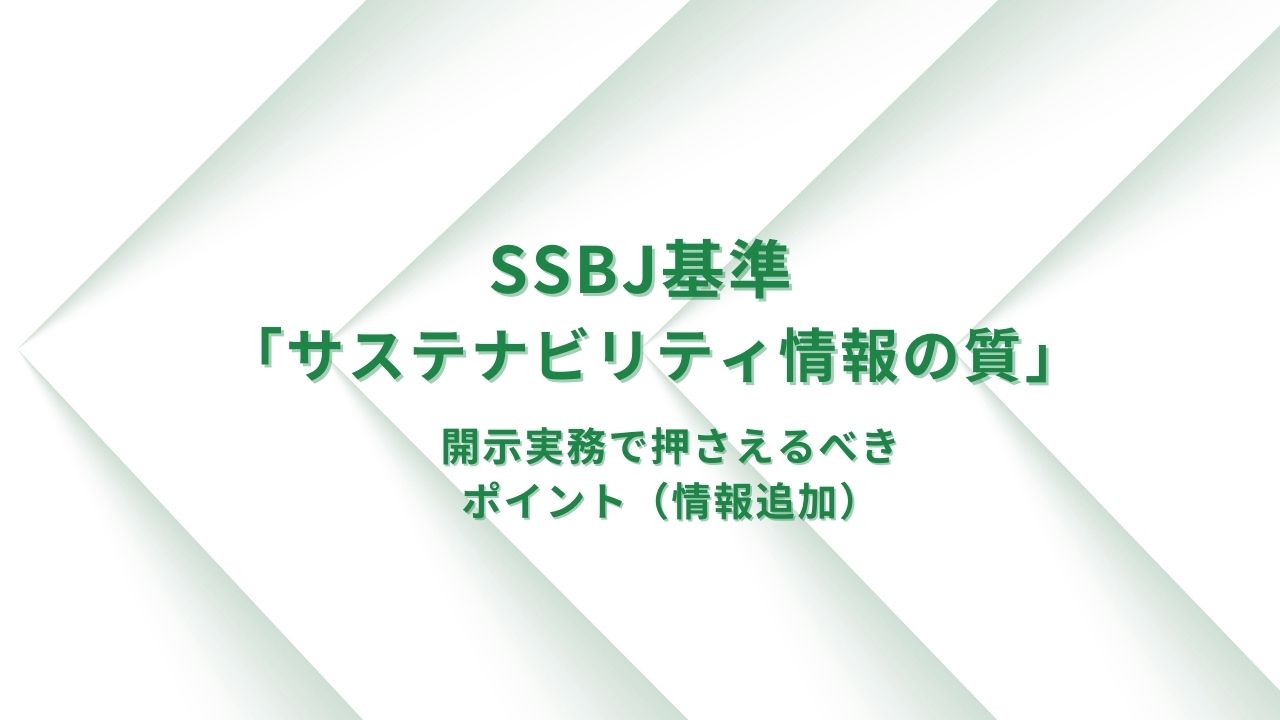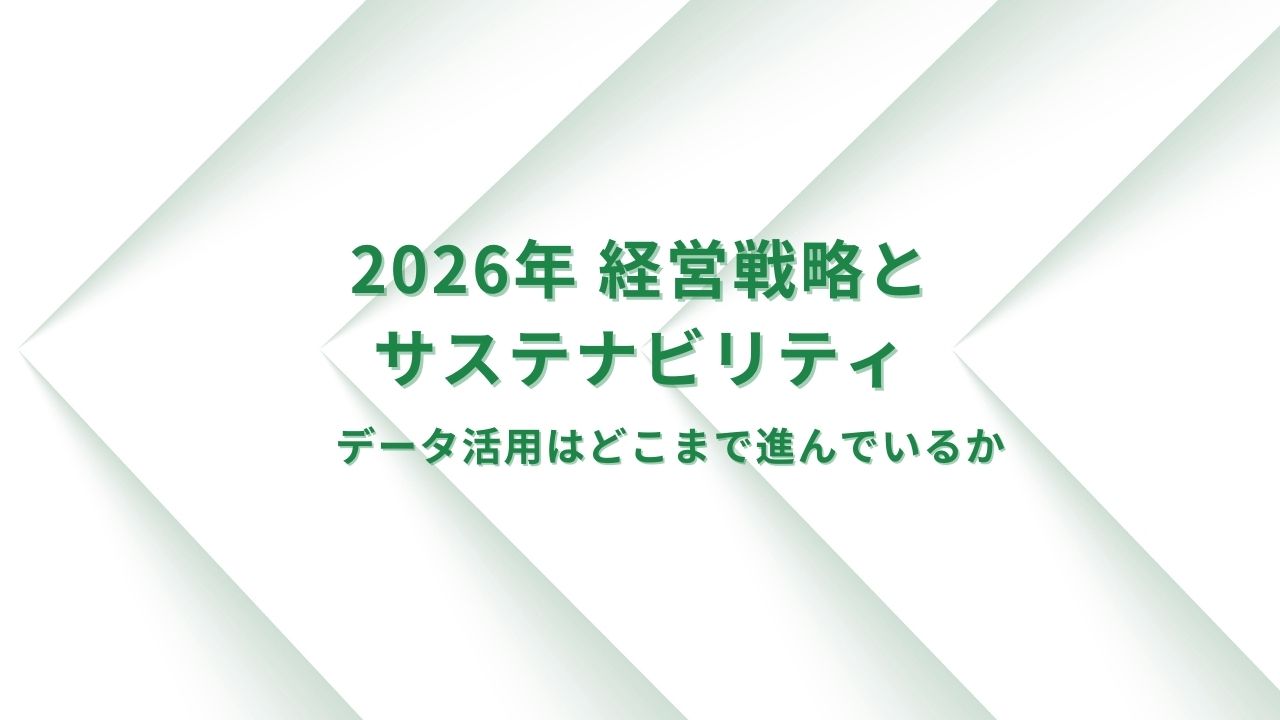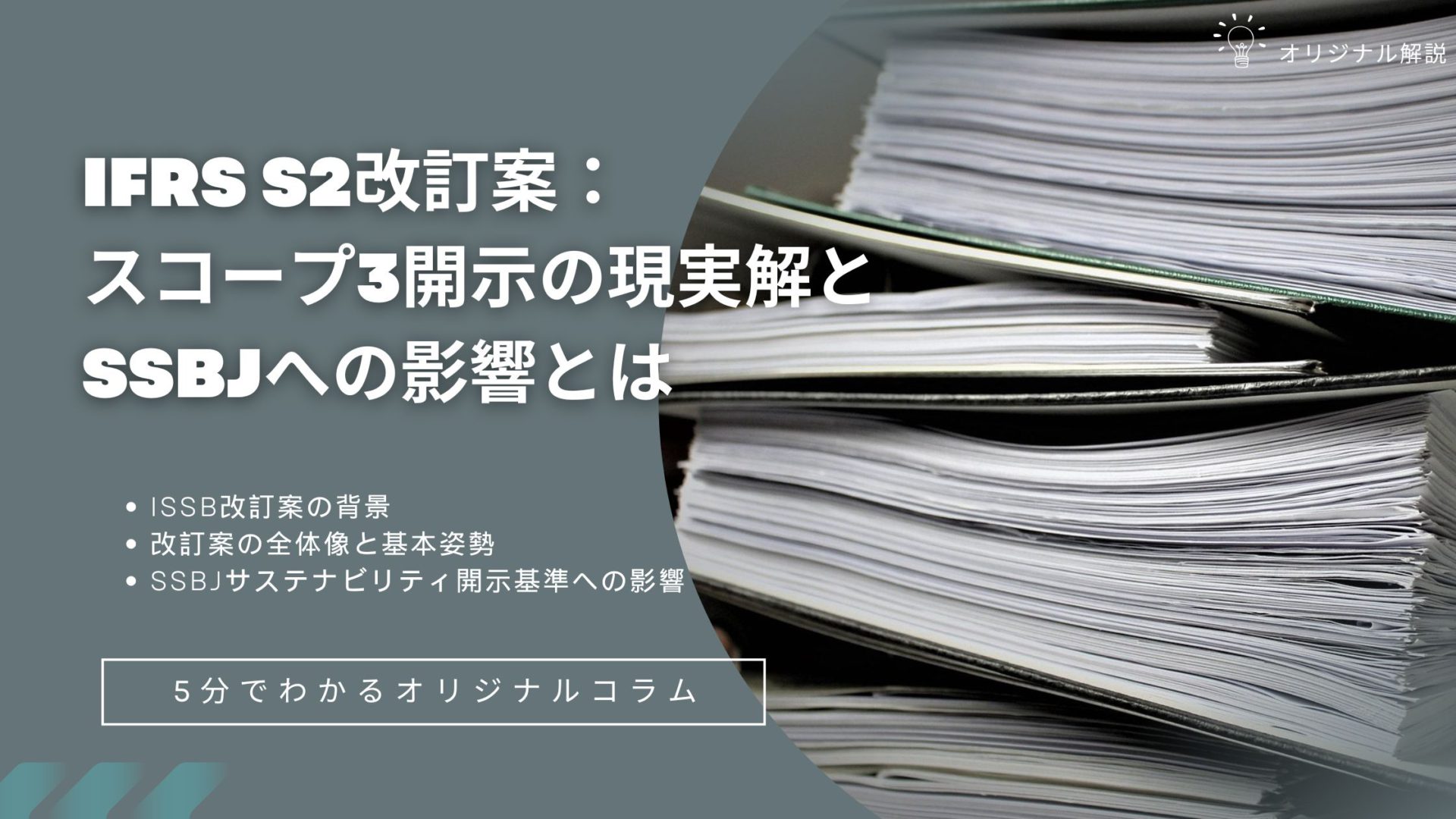ESGスコアとは?サステナブル担当者が知っておくべき基本的知識を解説
近年、企業に投資する観点として「ESGスコア」の重要度が高まっている。2020年代以降、世界的にESGへの取り組みへの関心はさらに高まっているものの、その基準は様々な評価機関によって異なり、スコアにもばらつきがある点が課題とされている。これを受け、欧米では基準統一化の動きが進展している他、ESGスコアを意識した情報開示も主流化している中、ESGスコアへの正しい認識ができているか不安な場合もあるだろう。本稿では、ESGスコアの基本的な概念および評価機関など、改めて情報を整理しつつ、自社の経営に寄与する評価の選定を考える観点について紹介する。
Contents
ESGスコアとは
ESGスコア/評価項目
ESGスコアとは、企業によるESG活動の取り組み度を示す数値である。環境・社会問題の解決に貢献する活動を経営に取り込み、中長期的に取り組む企業は、ESGスコアが相対的に高い。
ESGスコアは、シンクタンクや評価会社などが算出している。多くは、同セクターの複数社間等で比較可能なESGスコアランキングとして発表される。
ESGスコアは、算出方法によって以下の2つに区分される。
- 統合型:特定のテーマに偏らず、ESGの全要素を総合的に評価
- テーマ型:投資先の特徴的な取り組みを評価し、特定のテーマについてスコアリング
投資家がESGスコアを利用するようになった背景には、ESG投資の普及がある。ESGスコアは非財務情報が可視化されているため、効率的なESG投資先の選定が可能だ。
以降のコンテンツは無料会員登録を行うと閲覧可能になります。無料会員登録を行う
すでに登録済みの方はログイン画面へ