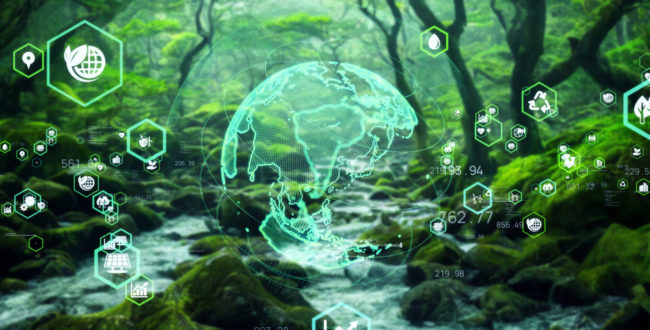東京の電力需給、2026年夏に「極めて厳しい」見通し

10月31日、経済産業省資源エネルギー庁は総合資源エネルギー調査会の電力・ガス事業分科会小委員会で、2025年度夏季の電力需給実績と今冬以降の見通しを報告した。その中で、2026年度夏季の需給見通し(速報値)が示され、特に東京エリアでは、安定供給に必要とされる予備率3%を大きく下回る「極めて厳しい」状況となる見込みであることが明らかになった。
報告によると、2026年8月の東京エリアの最小予備率は0.9%にとどまり、今年度と比べて6.3ポイント低下する見通しだ。安定供給の目安となる3%を大きく下回るこの数値は、10年に一度の厳気象条件を想定した需要が発生した場合を前提としている。厳しい見通しとなった背景には、供給力と需要の双方に構造的な要因がある。複数の大型火力発電所が年間を通じて補修停止になることに加え、他の火力発電所でも休止が重なり、2025年8月に比べて東京エリアの供給力が約256万キロワット減少する。一方で、需要面では気温上昇や経済活動の増加などにより、広域予備率の算定時と比べて約125万キロワット増加する見通しで、需給バランスはおよそ400万キロワット分悪化することになる。
資源エネルギー庁はこうした状況を踏まえ、東京エリアで最低限の予備率3%を確保するため、直近の対策を参考におよそ120万キロワット分の供給力を新たに公募するなど、機動的な対応策を速やかに講じる方針を示した。
2025年度冬季については、全エリアで厳寒条件下でも安定供給に最低限必要な予備率3%を確保できる見通しだ。ただし、一部の地域では予備率が4%台にとどまり、引き続き厳しい需給環境が続く。昨年度には10%以上の予備率を確保できていたが、今冬は発電機の廃止や故障による停止などが相次いでおり、供給力が大幅に低下しているという。また、大手電力会社のLNG(液化天然ガス)在庫は10月26日時点で197万トンと、過去5年平均を下回る水準にある。政府は、家庭や企業への一律の節電要請は行わない方針だが、供給力がさらに低下した場合には緊急対応を実施するとしており、状況に応じて電力ひっ迫注意報・警報の発令準備も進めている。
資源エネルギー庁は中長期的な課題として、日本の電力供給が構造的な転換期を迎えていることを指摘した。老朽化した設備や非効率な石炭火力発電所の休廃止が進む一方、長期脱炭素電源オークションによって導入される新設LNG火力の稼働は2029年以降と見込まれており、それまでの数年間は特に夏季・冬季の高需要期に需給の逼迫が続く可能性があるという。
政府は、こうした構造的課題に対応するため、安全性を最優先に女川2号機や島根2号機など原子力発電所の再稼働を進めるほか、東北—東京、北海道—本州、中部—関西といった主要連系線の増強を推進する方針を示した。また、短期的な対策として、追加的な供給力の確保や需給調整手段の強化など、柔軟な対応策を引き続き検討していくとしている。