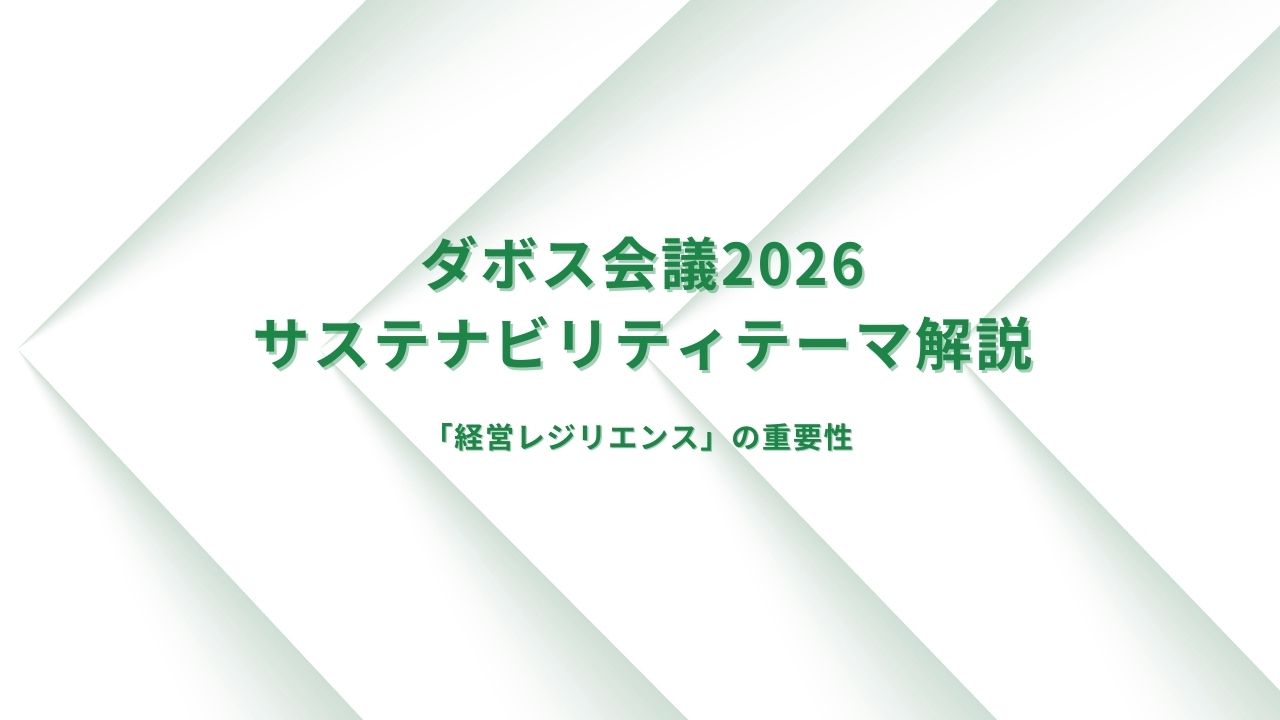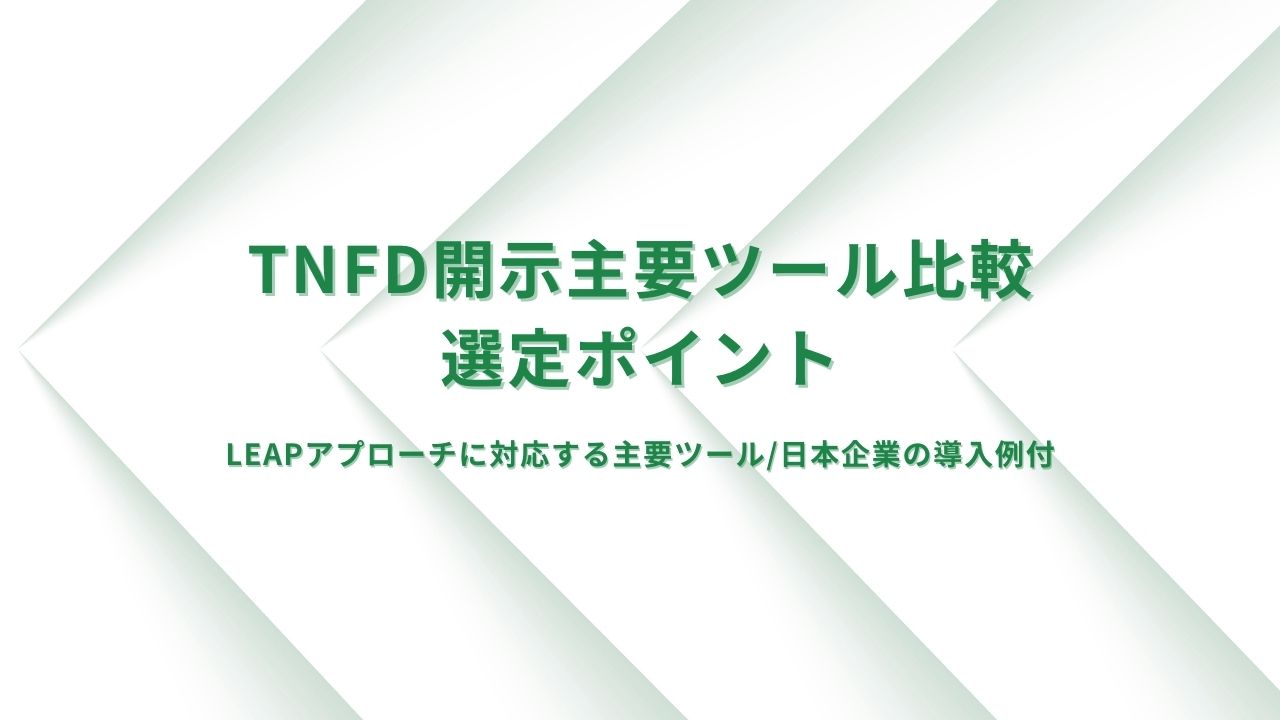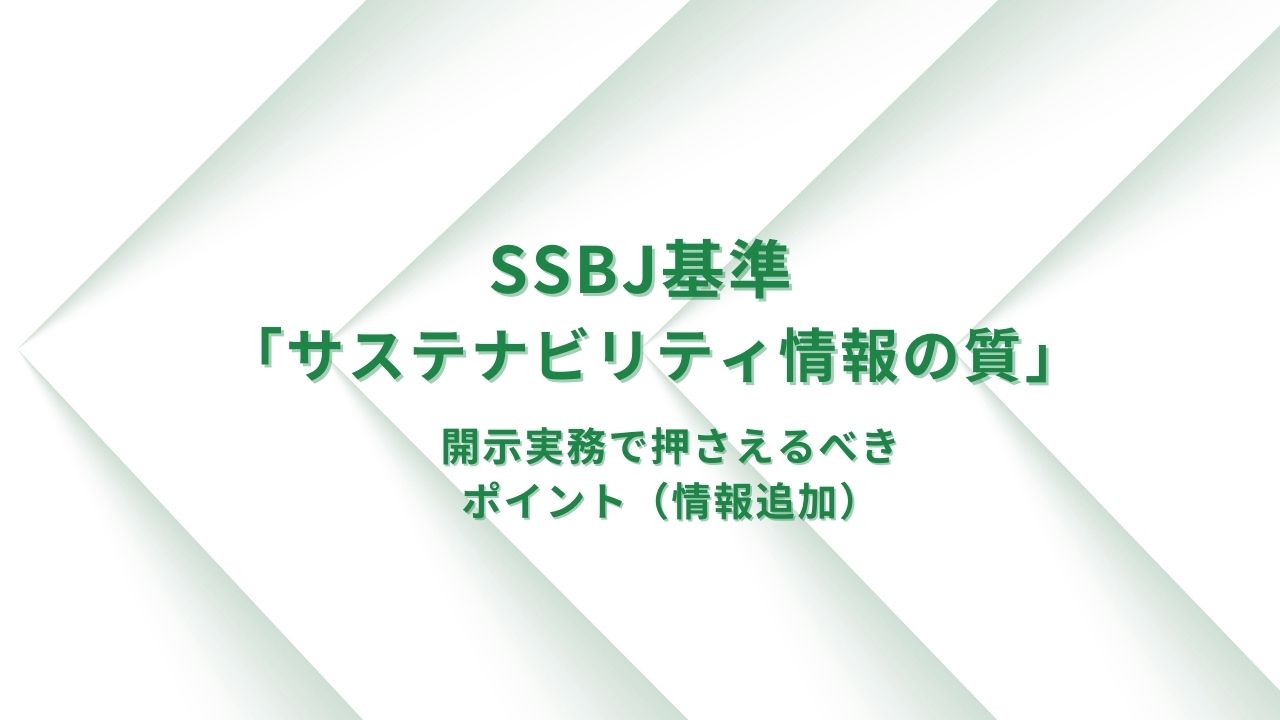2025年・COP30開幕!サステナビリティ経営・実務における注目テーマ整理/実務への影響解説
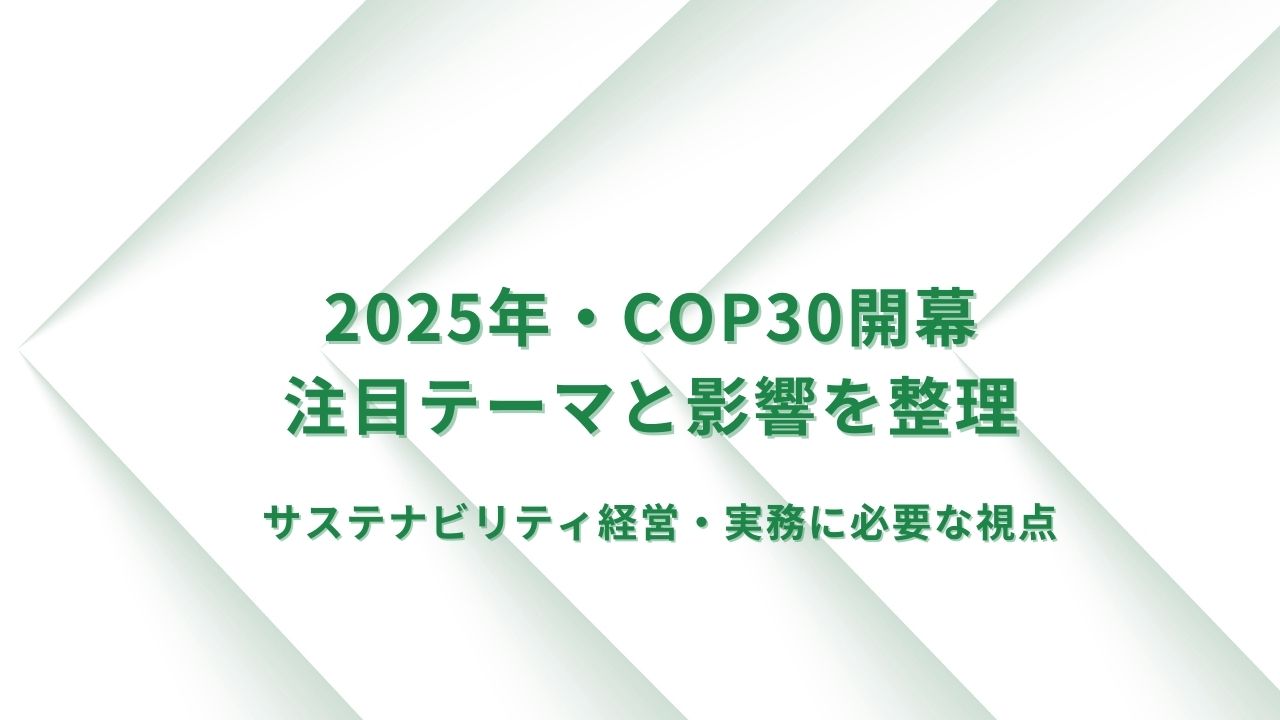
11月10日から21日まで、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の第30回締約国会議(COP30)がブラジル・ベレンで開幕する。「気候変動対策の国際的な会議」であり、パリ協定が採択された2015年からちょうど10年が経つ。
10月28日にはBill Gatesが「地球の気温上昇が1.5°に収まる確率は低いため、気温上昇の制御(気候変動対策)だけにとらわれず、人々の福祉・レジリエンスにフォーカスすべきだ」とコメントを発表し、気候変動だけでなくその影響にかかる認識が拡大したとして話題になった。
これまで世界各国の温室効果ガス排出削減の約束(NDC)が十分でないとされてきた背景から、パリ協定で掲げられた「1.5°目標」の達成が危うい現実になりつつあるとも言える。
本稿では、過去のCOPがどのように企業の気候変動対策や適応に影響してきたのかポイントを整理し、今回のCOP30で企業のサステナビリティ経営の実務において注目すべきポイントを解説する。なお、COP30の終了後には、議論などの結果を踏まえた続編も公開予定である。ぜひこの機会に理解を深めてほしい。
COPの概要とCOP30の議題
COP(COP30)とは、UNFCCC(国連気候変動枠組条約)の枠組みのもとに開かれる年次会議であり、現在約198の締約国が参加している。
COP29までの主な議題は気候変動の緩和、適応、そしてこれらに向けた資金や技術協力であった。2015年に開かれたCOP21でパリ協定が採択されて以来、各国は国が決定する貢献(NDC)を5年ごとに提出し、気温上昇を1.5度〜2度に抑えるという世界共通目標に向けて行動を迫られている。
近年のCOPは、政府代表者や気候変動専門家のみならず、企業・市民社会・自治体・投資家といった「交渉テーブルには座らないが、実際に行動を起こす」非国家アクターの参加が増えている。
実際、今年のCOP30では、これらのステークホルダーに向けた「行動アジェンダ(Action Agenda)」が前面に出ており、彼らの主導的気候変動アクション(voluntary climate action)が条約や協定で決まったことを実践に繋げる重要な役割を持っている。
一方、COP30ではこれまでの対応を考えるというフェーズから「実績」を求めるフェーズに変容しつつある。また、気候変動対応の認識にも広がりを見せつつある。以降、COP30における主な議題や新たな論点について整理していく。
つづきは無料会員登録(名前・メール・会社名だけ入力)を行うと閲覧可能!!
🔓会員登録の4つの特典
話題のサスティナビリティニュース配信
業務に役立つオリジナル解説
業務ですぐに実践!お役立ち資料
会員特別イベントのご案内!
すでに登録済みの方はログイン
執筆者紹介
 | マルティネス リリアナ (スペシャリストライター) サステナビリティ学修士。シンクタンクにて海洋・大気環境に関する政策の策定支援を行う。国際海事機関(IMO)ではTechnical Advisorとして国際議論への参加経験を積み、その後、気候変動課題を中心に企業向けにコンサルティングを行う。非財務情報開示フレームワークからサステナビリティの国際動向まで幅広くコラムやホワイトペーパーで解説。 |