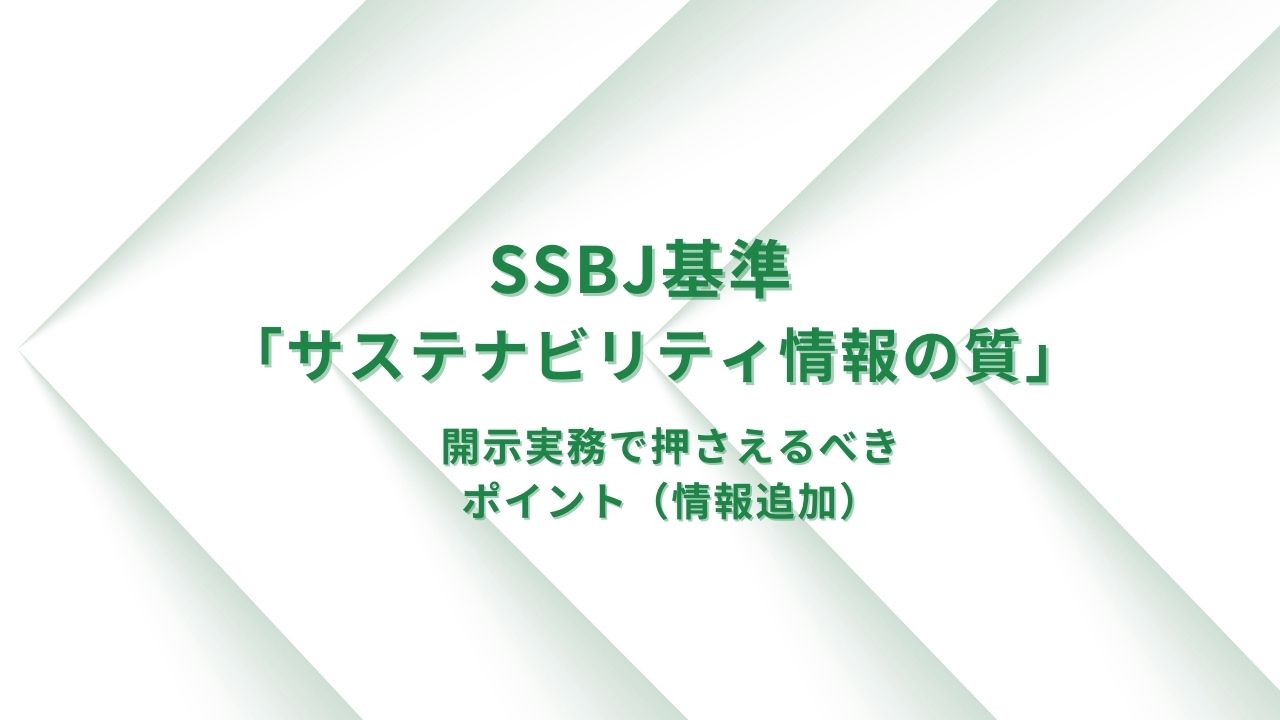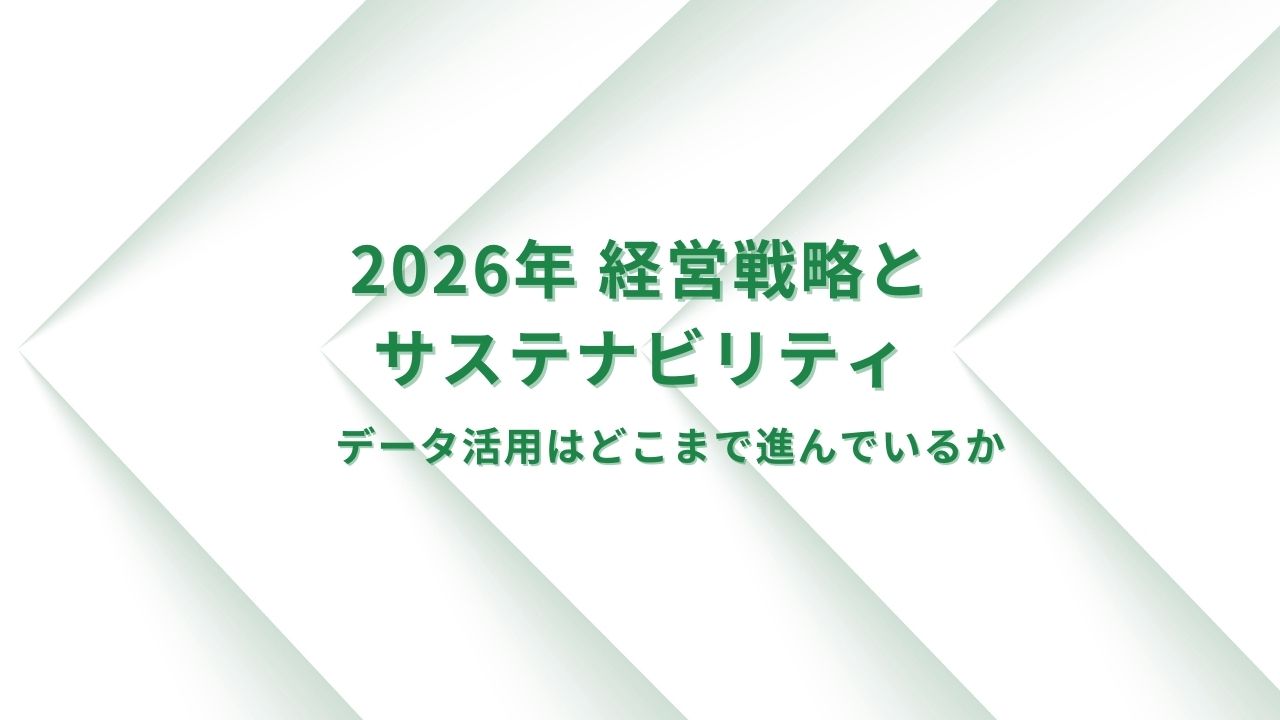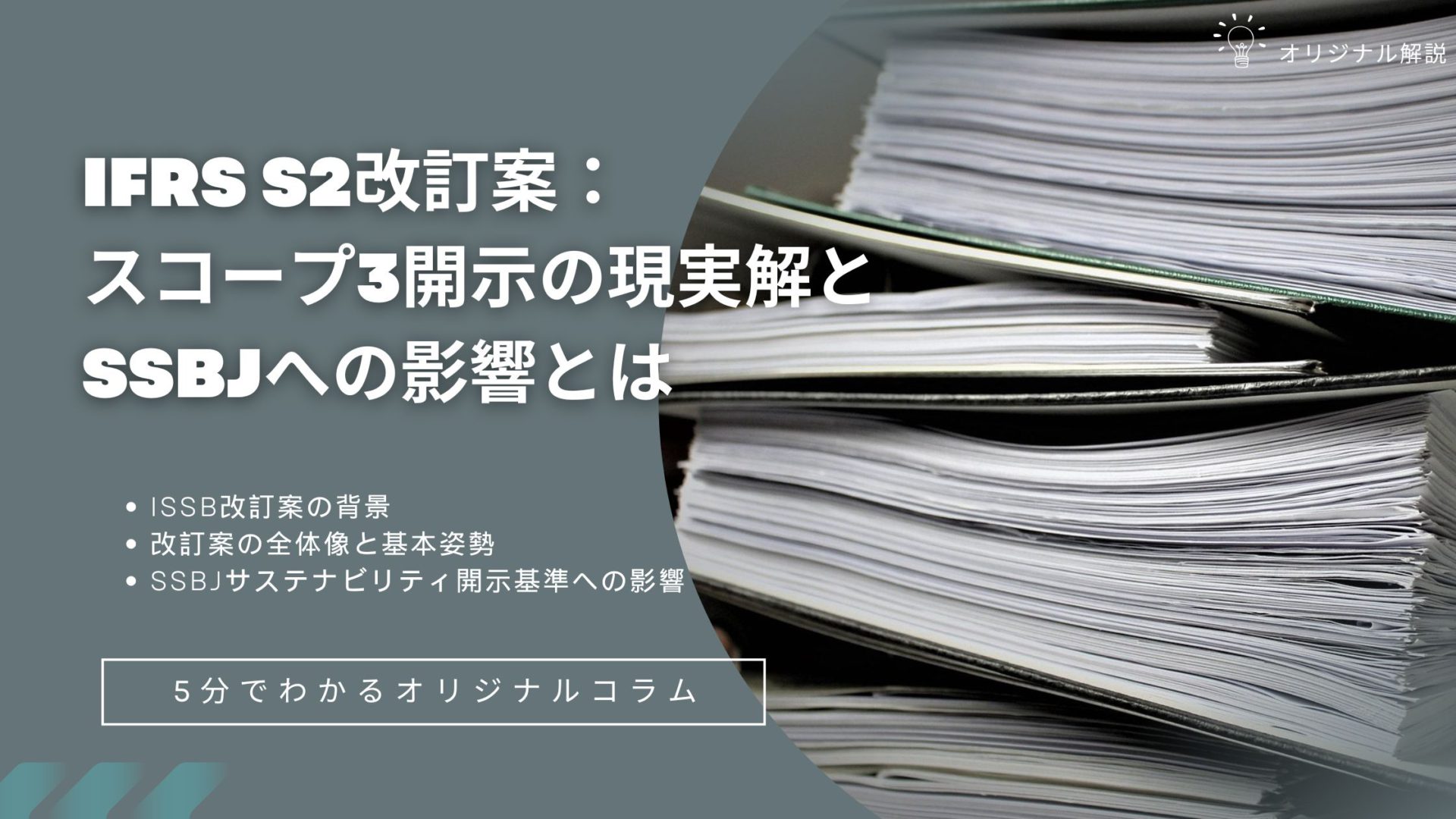国際認証ラベルの取得は企業にとって負担?メリットと負担軽減策を解説。
近年、国際認証ラベルの付いた商品が普及し、企業が国際認証ラベルを取得する重要性が高まってきている。しかし、国際認証ラベルの取得には、定められた手順が必要で、手間がかかるという印象があるかもしれない。そこで、本稿では、国際認証ラベル取得のメリットや課題、さらには手続きの負担の軽減方法を紹介する。
国際認証ラベルとは
国際認証ラベルとは、人や地域、社会、環境に配慮した製品であることを証明する国際的なラベルである。別名「サステナブルラベル」とも呼ばれる場合もあり、よく耳にすることもあるだろう。認証ラベルを取得するには、第三者機関による製品の「安全性や品質」に関する基準に基づいた審査が必要となる。この審査に合格した商品のみに「認証ラベル」が与えられている。
以降のコンテンツは無料会員登録を行うと閲覧可能になります。無料会員登録を行う
すでに登録済みの方はログイン画面へ