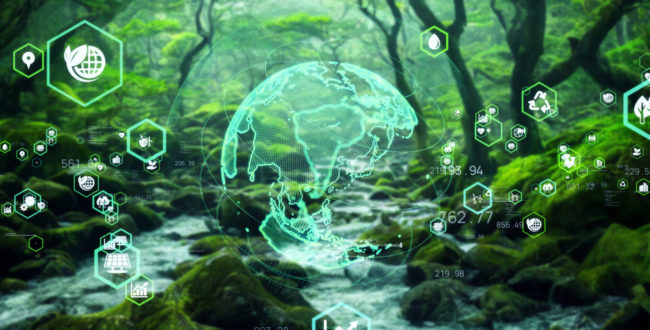GX-ETS:割当調整・移行計画・価格制御の方向性が明らかに

11月7日、経済産業省は、第5回産業構造審議会イノベーション・環境分科会 排出量取引制度小委員会を開催し、割当ての個別論点や移行計画、上下限価格の設定方針など、実務設計に直結する要素について議論した。
活動量調整の明確化、災害時には例外措置も
事業所ごとの活動量変動に応じた割当調整の仕組みについては、基準年度に対して過去2年度平均で7.5%以上の変動があった場合に基準活動量を見直す原則を設けつつも、法定点検や災害等の不可避的要因による減産は対象外とする方針が示された。
この場合、該当年度は「活動量実績×BM水準」で割当量を算定する。自然災害の範囲も明確化され、激甚災害法や特定非常災害法の適用地域が対象となる見通しだ。一方で、感染症拡大や経済危機など全国的影響事案への対応も将来的課題として議論に残された。
早期削減・リーケージ・研究開発
制度移行時の公平性を担保するための「勘案事項」も整理された。
- 早期削減量の補正係数として、活動量減少分を控除するための0.8係数を導入。過去の努力を一定程度反映しつつ、制度後の割当水準とのバランスを図る。
- リーケージリスク緩和措置では、排出枠コストが営業利益の4%を超えた場合に発動。不足分の50%程度を追加割当する。
- 研究開発費の扱いについては、特許情報など外形的に確認可能な根拠に基づくが、グリーンイノベーション基金(GI基金)を通じた自己負担額は特許要件を緩和して認める方向だ。
BM・GF間の均衡を確保、当初5年間に特例設定
ベンチマーク(BM)業種とグランドファザリング(GF)業種の削減負担の不均衡を是正するため、2026〜2030年度の5年間限定で特例を設ける。
2030年度のBM水準は、通常の「上位32.5%」に加え、「上位50%×0.915」と比較し、いずれか大きい方を採用する方式が導入される見込みだ。
移行計画の提出など情報開示が義務化
GX-ETSの導入により必要になるのが、「移行計画」の提出である。対象事業者には、直接・間接排出削減目標や研究開発方針を含む移行計画の毎年度提出・公表が義務付けられる。なお、第三者認証は不要だが、透明性確保のため詳細な記載が求められる。
また、研究開発に係る追加割当を受ける事業者には、特許出願情報やGI基金プロジェクトの実施状況、GX技術区分などの公表も求められる。
なお、グループ企業による共同届出も認められ、サプライチェーン全体のGX投資戦略を一体的に把握する枠組みが整備されつつある。
>>>関連するお役立ち資料:「<先進事例付> 気候関連開示・移行計画 統合実践ガイド(TCFD/IFRS S2/TPT対照表)」
なお、価格上昇時の負担抑制に向け、上限価格を設定。これを支払うことで義務履行を可能にする仕組みを導入する。一方、下限価格については、一定期間市場価格が下回った場合にリバースオークションで需給を引き締める。2033年以降の政府オークション導入後は、入札価格に下限を設けて維持する方針だ。
次回の審議会では、上下限価格の具体水準と全体とりまとめが議題となる予定だ。これまでの5回で、割当設計・対象範囲・算定方法・勘案措置・移行計画といった中核要素が出そろい、制度全体の姿が明確になった。