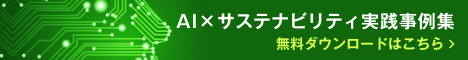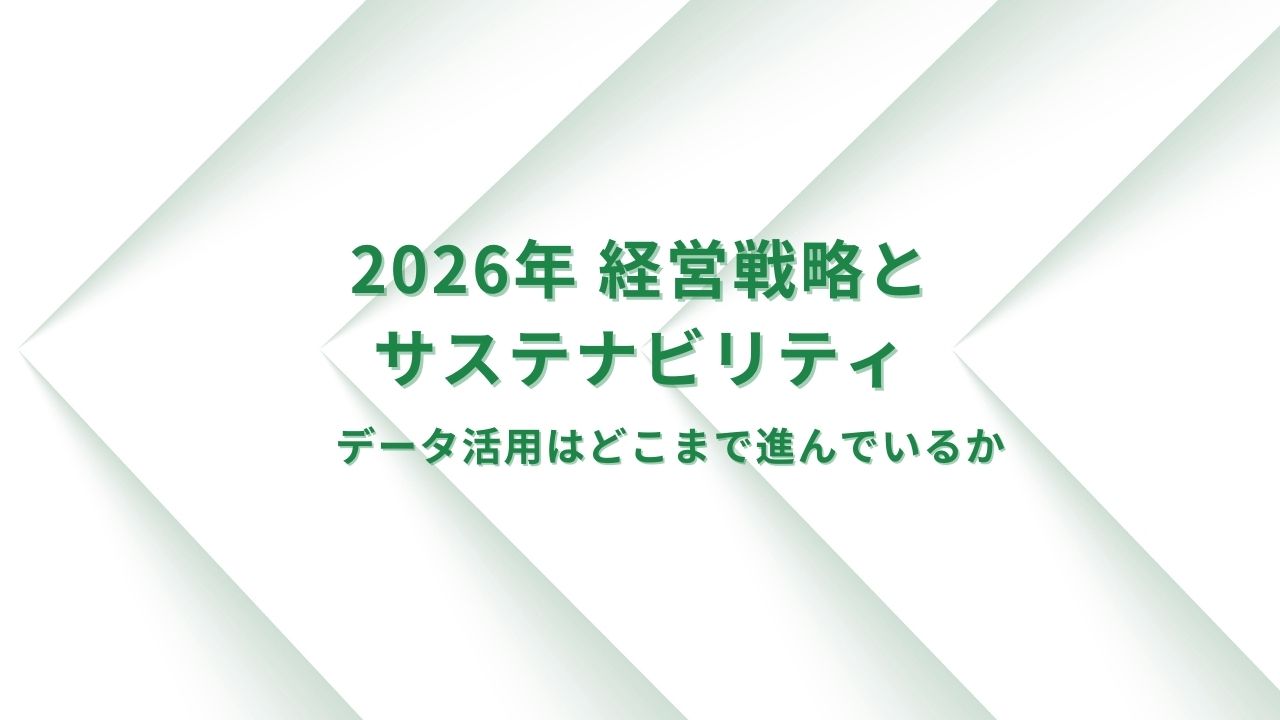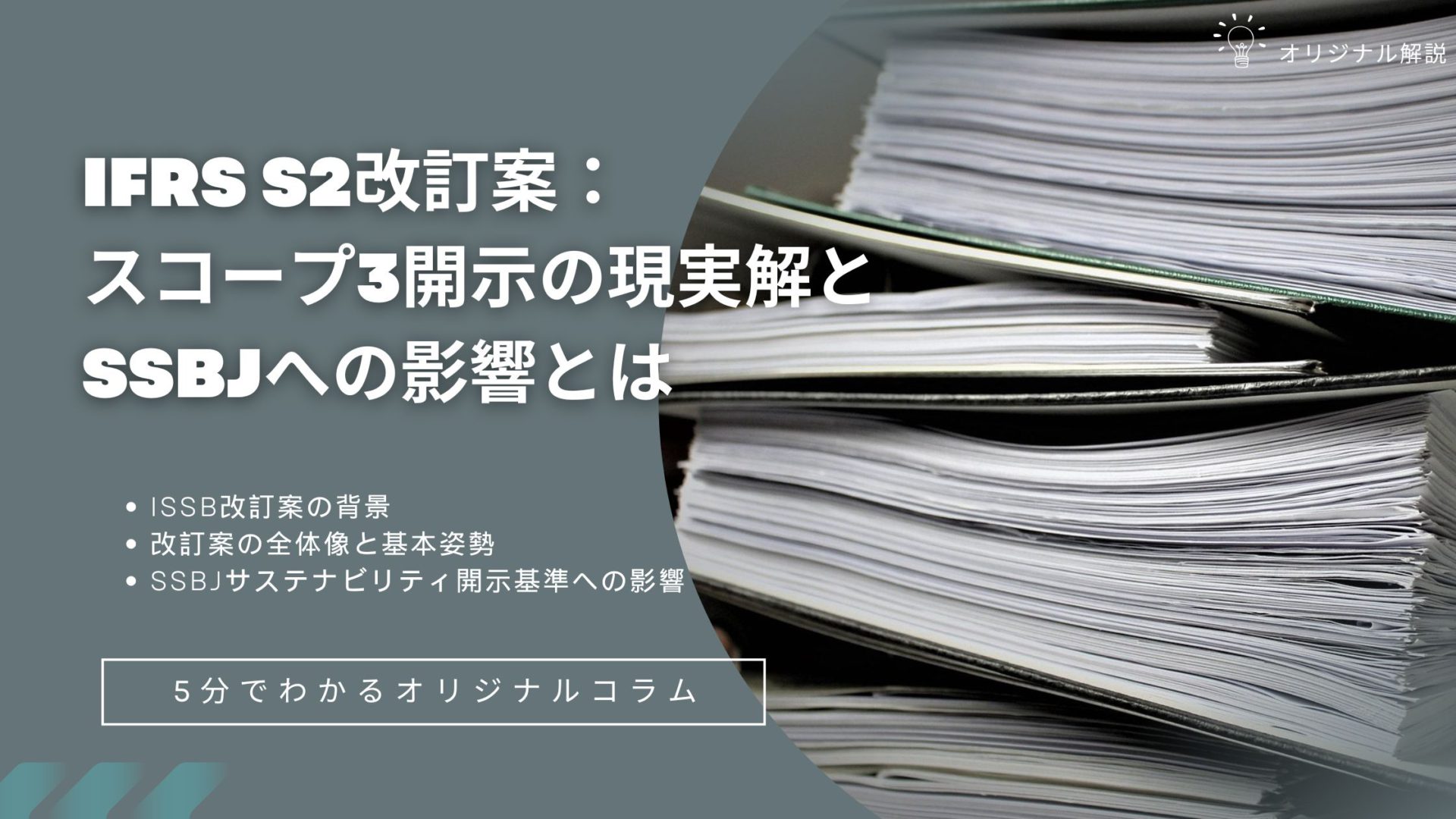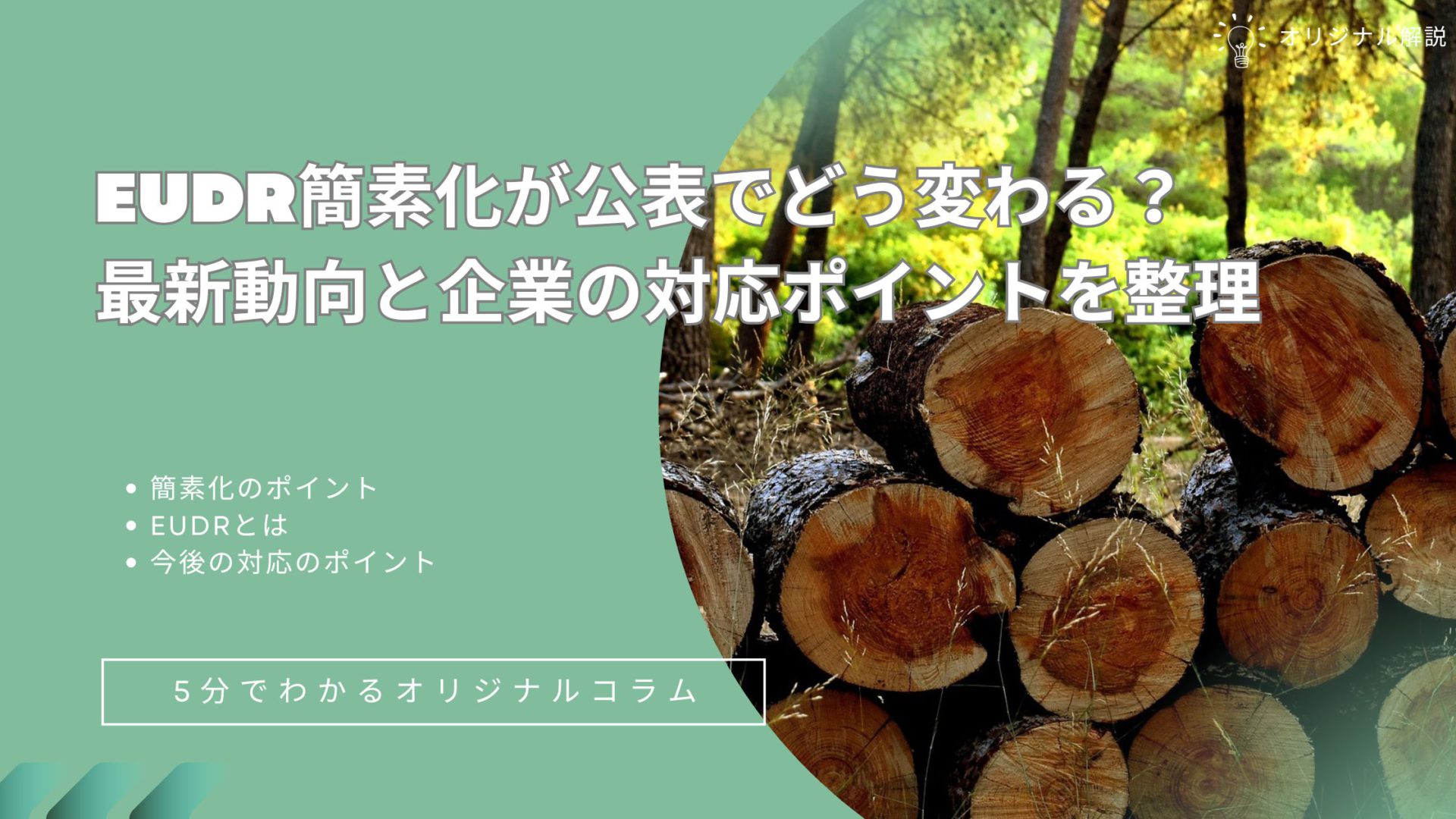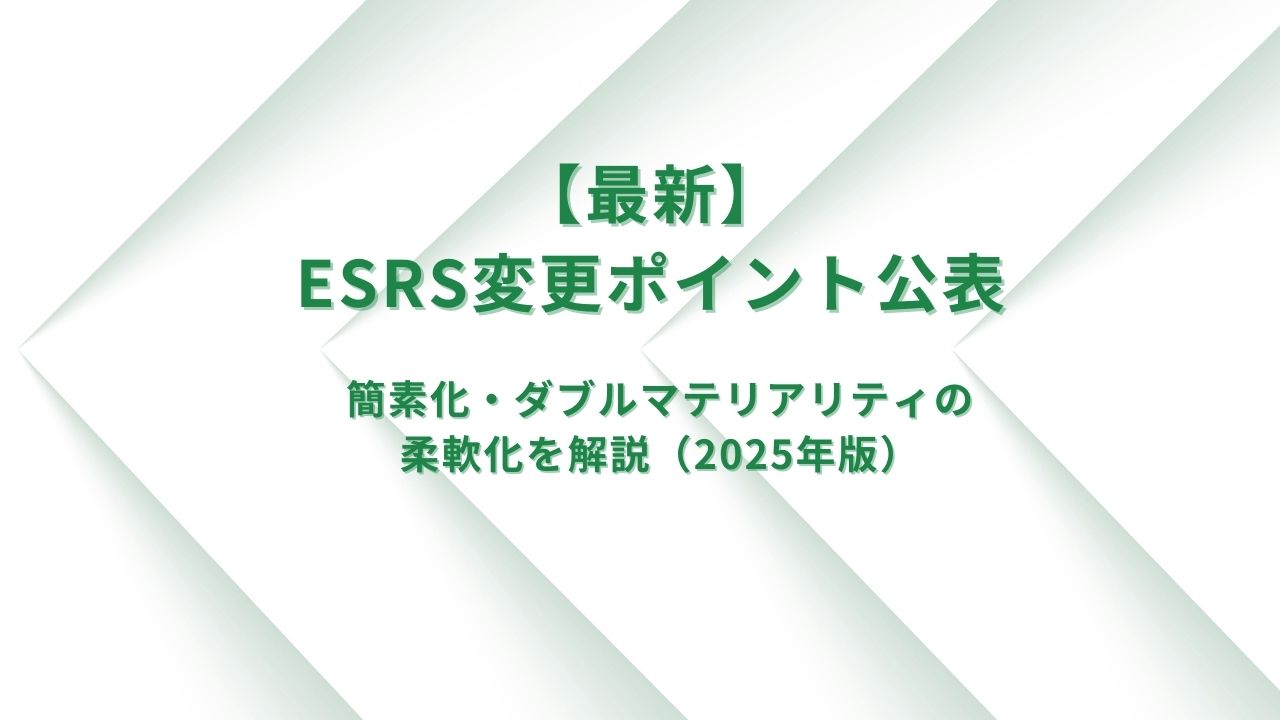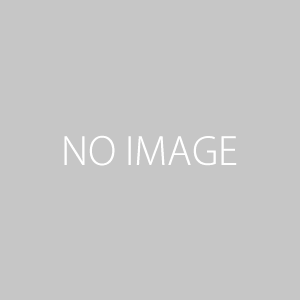マテリアリティ開示の進め方。各ガイドラインに共通する考え方も紹介
マテリアリティの開示は、サステナビリティ報告においても重要な内容として投資家からの注目度が高い。マテリアリティは、企業にとってのリスクや重要課題(機会)を社内外の視点から特定していく作業である。しかし、マテリアリティは様々なガイドラインにて定義されており、開示基準ごとにマテリアリティ特定作業をしなければならないと考えている場合があるだろう。本稿では、主なガイドラインにて定義されているマテリアリティを紹介しつつ、投資家が重要視するマテリアリティ開示手順やポイントを解説していく。
Contents
マテリアリティ開示の概要
マテリアリティ開示に当たっては、マテリアリティにかかる3つの考え方、そして各ガイドラインがどの考え方に依拠しているのかをしっかり理解しておく必要がある。
マテリアリティとは
マテリアリティとは、様々なサスティナビリティに関する課題の中で自社が優先して取り組むべき重要課題のことである。
ESGの情報開示プロセスにおいて、特定することが求められるマテリアリティには、「シングルマテリアリティ」と「ダブルマテリアリティ」の2つの考え方がある。
環境・社会問題が企業活動・業績に与える影響のみを重視する考え方を「シングルマテリアリティ」、企業活動が環境・社会に与える影響も含めた双方向の考え方を「ダブルマテリアリティ」と呼ぶ。
さらに、金融庁によれば、マテリアリティには時代とともに変化する動的なものと捉えた「ダイナミックマテリアリティ」という考え方もあるとしている。時間の経過や外部環境の変化とともに、これまで考慮してこなかったテーマがサステナビリティの報告事項に含まれたり、財務諸表に反映されたりするからだ。
出所:事務局説明資料②(サステナビリティに関する開示(1))|金融庁
以降のコンテンツは無料会員登録を行うと閲覧可能になります。無料会員登録を行う
すでに登録済みの方はログイン画面へ