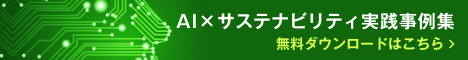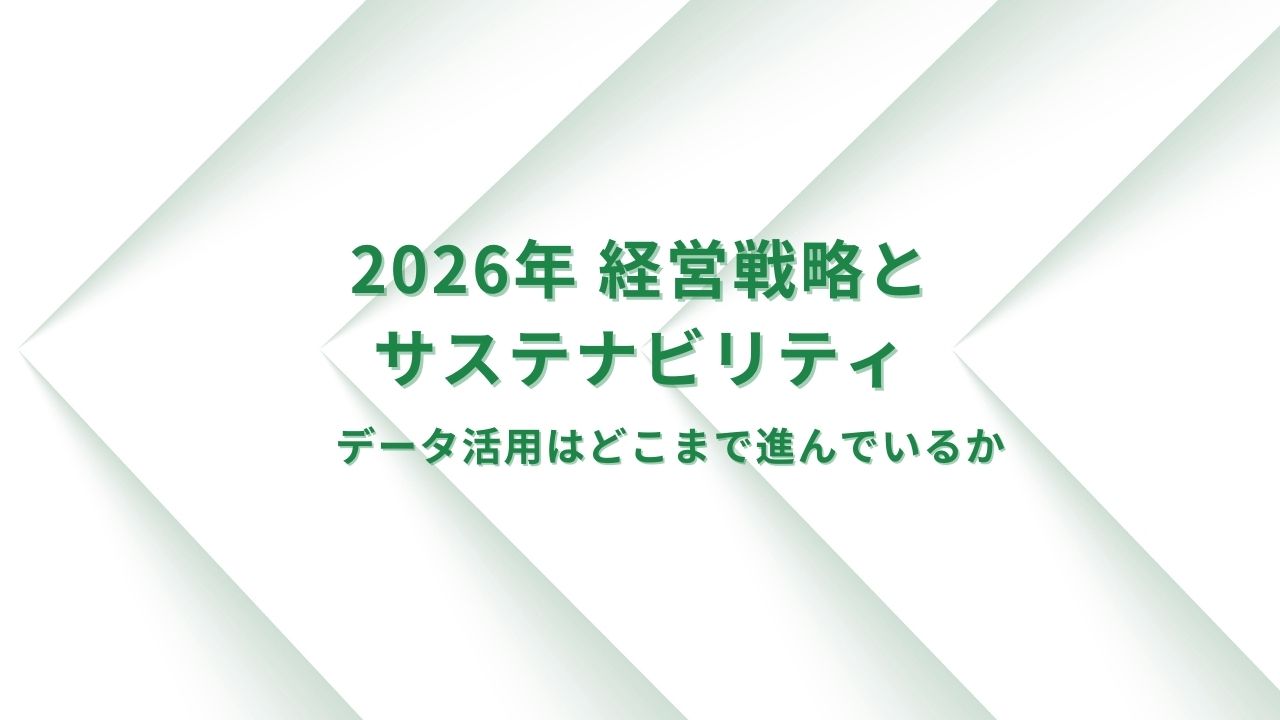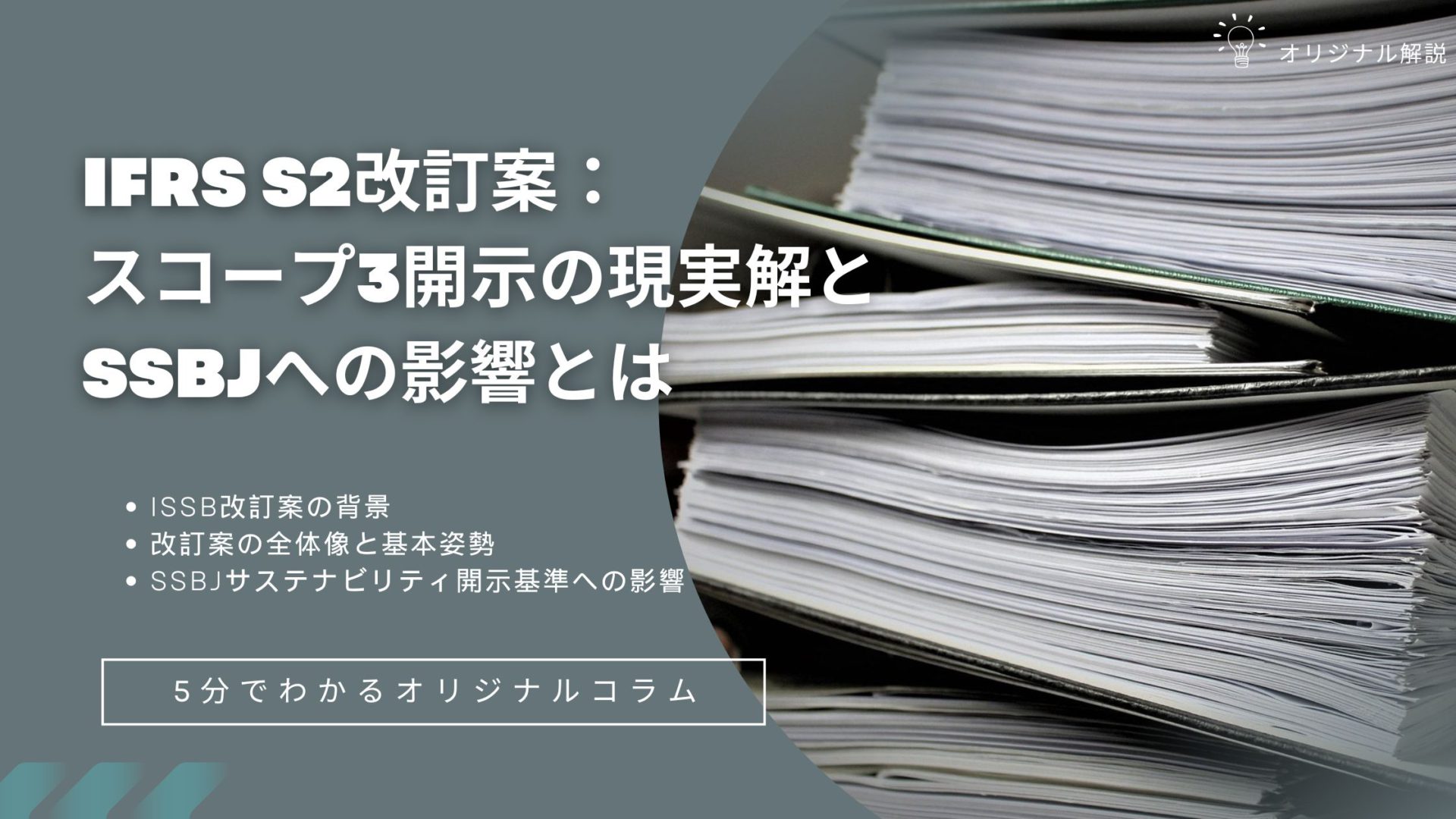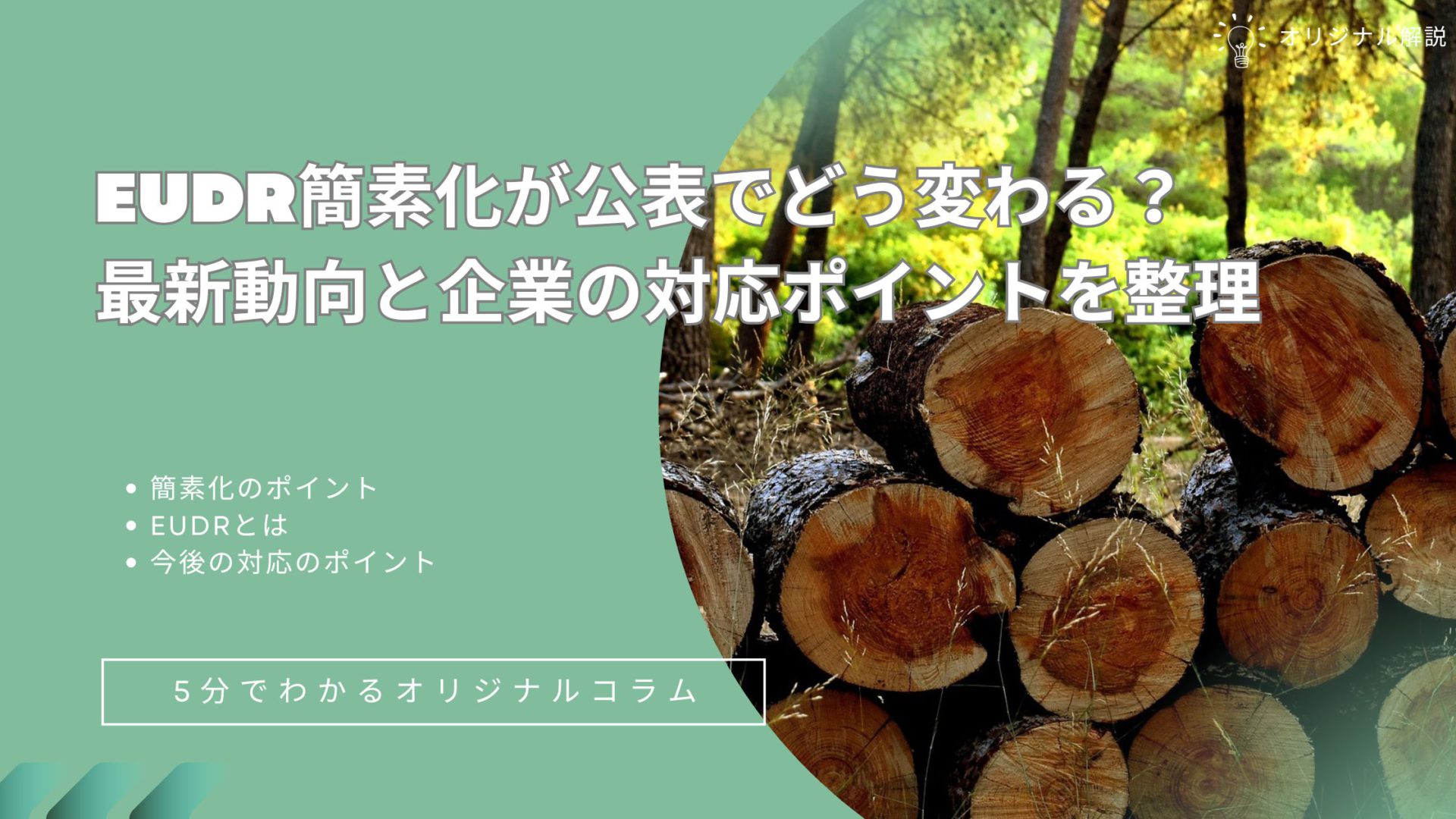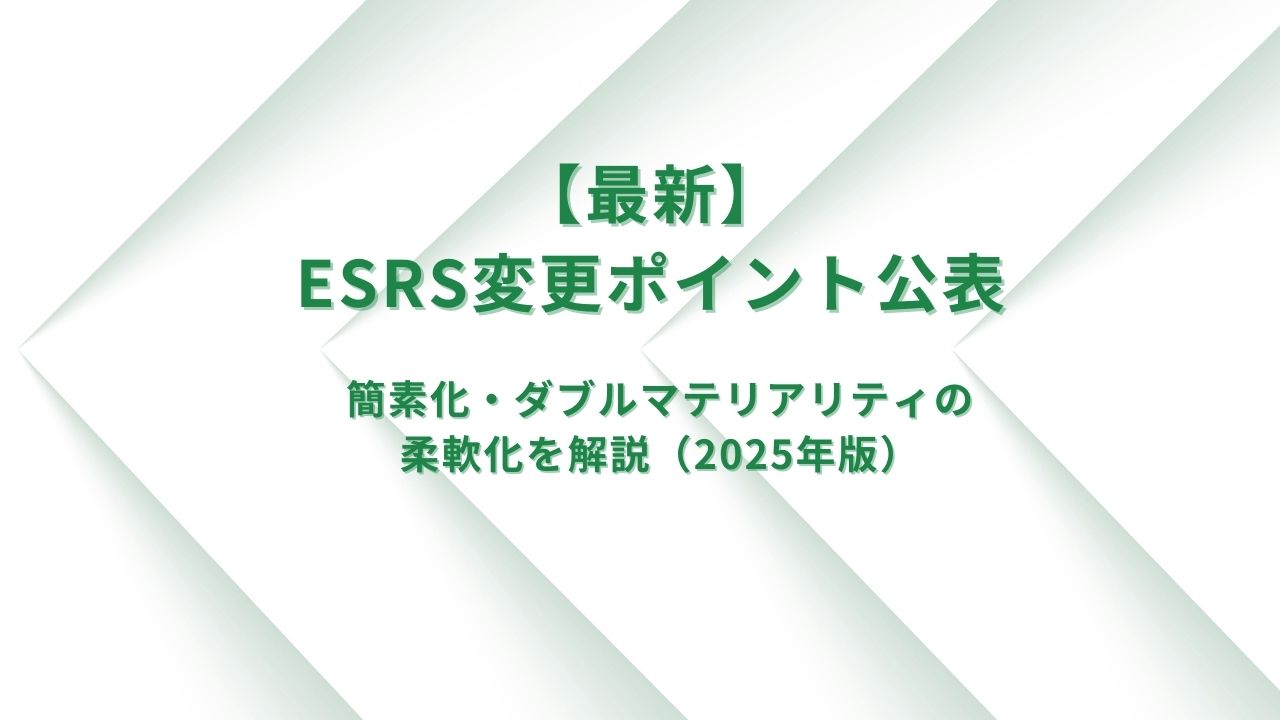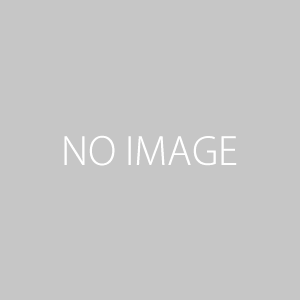人権デューデリジェンス(人権DD)が進まないのはなぜ?日本企業の人権リスクへの対応状況

人権デューデリジェンスの法令化が海外では進む中、日本でも対応への社会的関心が高まっている。そこで本記事では、人権デューデリジェンスを実行するために必要な事項をまとめた。人権デューデリジェンスについて気にはなっているが、どう取り組めばいいかわからないという方は、ぜひ参考にしてみてほしい。
国内の人権デューデリジェンスの対応状況
国内の人権デューデリジェンスへの対応状況は他国に比べて遅れをとっている。実際に、認知度・実施率の双方において半数以下にとどまっている。
以降のコンテンツは無料会員登録を行うと閲覧可能になります。無料会員登録を行う
すでに登録済みの方はログイン画面へ