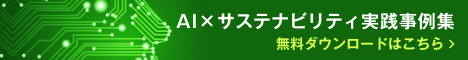米国農地で干ばつ対策としての灌漑が拡大、一方水不足の懸念も

8月14日、米ダートマス大学の研究者らは、灌漑は作物収量を増加させることができ、重要な干ばつ対策となりうる一方で、将来の水の利用可能性は不確かであると示す論文を発表した。
米国の農地における灌漑面積は過去数十年で大幅に増加している。効率改善により原単位の水消費量は低減しているものの、依然として灌漑農業は米国の水使用量の約80%を占める。
同研究では、米国全土におけるとうもろこしと大豆の灌漑の現状と、拡大による経済的コストと便益を調査。将来予測される気候の下で、21世紀半ばと末の双方の状況を調べた結果、今世紀半ばまでに、灌漑の利益が地下水の汲み上げと設備の所有コストを上回る地域が拡大することが明らかとなった。作物の水需要の増加により、とうもろこしを持続的に灌漑できる地域は限定されるが、大豆は、米国中西部と南東部の全域で灌漑設備の導入が可能となり、限界収量も増加した。
一方、灌漑設備の設置・維持に対するインセンティブが変化することで、資源の利用可能性にさらなる課題が生じる可能性があると言及。灌漑の設置や利用における政策策定の際には、地域の水需要と利用可能性を理解し、考慮することが重要であるとした。
【参照ページ】
(原文)Irrigation benefits outweigh costs in more US croplands by mid-century
(日本語参考訳)米国農地で干ばつ対策としての灌漑が拡大、一方水不足の懸念も