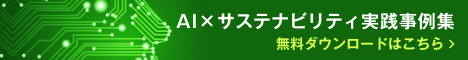PwC、「サステナビリティに関する消費者調査2022」を公表

9月、PwC Japanグループは、世界と日本のサステナビリティ動向に関するレポート「サステナビリティに関する消費者調査2022」を公表した。本調査では、消費者の現状を示しながら、未来のトレードオン実現に向けて「消費者をいかに巻き込んでいくか」について考察する。
本レポートは、グローバルおよび日本におけるサステナビリティ市場の現在地と未来に向けた課題と兆しを明らかにし、企業のアクション検討の一助とすることを目的としている。調査は日本・中国・米国・英国を対象国とし、webでアンケートをとった。
まず、世界の動向としては、欧米・中国では、小売とメーカーの協働により、快適にサステナブルな消費ができる環境づくりが進んでいることが明らかになった。過去1年間でサステナブルな商品を「購入したことがある」人は、中国91%、英国84%、米国79%、日本58%であった。また、「購入したことがない」人のうち、「身近に売っていない」ことをその理由に挙げた割合は、日本では19%であるのに対し、米国は13%、英国は5%にすぎなかった。
次に、日本における3つの壁として、
1.価格とアクセシビリティがサステナブルな商品の購入を阻んでいる
2.サステナビリティに関する情報を得る媒体が偏っている
3.商品購入を通じてサステナビリティに貢献するという行動が広がっていない
が挙げられている。
グローバルでは、すでに消費者がサステナビリティを意識し、購買行動にも反映され始めている。一方、日本ではまだ黎明期にあるものの、光明の兆しもある。日本では、3年前の調査と比較して、サステナビリティへの認知・理解は高まっている。また、次世代市場の主役となる若年層は、より能動的に情報収集し、判断している傾向が見られる。その弾みを、機会に転換すること、つまり、既存の価値をフックとして商品を手に取ってもらい、背景にあるサステナビリティに関する認知と理解を変えていくような取り組みが企業には求められている。
企業・商品がサステナブルであることは、企業の財務にプラスのリターンをもたらす。「他商品と比べても、選びたい(選好プレミアム)」「少し高くても、購入したい(価格プレミアム)」「他者にもお勧めしたい(拡散プレミアム)」という3つのプレミアムがあるブランド形成につながり、購買決定要因となる傾向が見られた。
気候変動をはじめとする中長期の環境・社会課題は、消費者の未来の暮らしを脅かすリスクだが、消費者はこのリスクを必ずしもまだ感知できていない。企業は、この環境・社会課題に先回りして対応することで、今のニーズに応えながらも、未来の消費者が暮らす世界を守る新しい「顧客至上主義」を実現できるとPwCは述べている。
【参照ページ】
新たな価値を目指して サステナビリティに関する消費者調査2022 | Consumer Markets: PwC