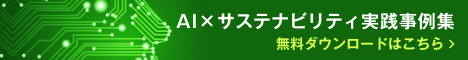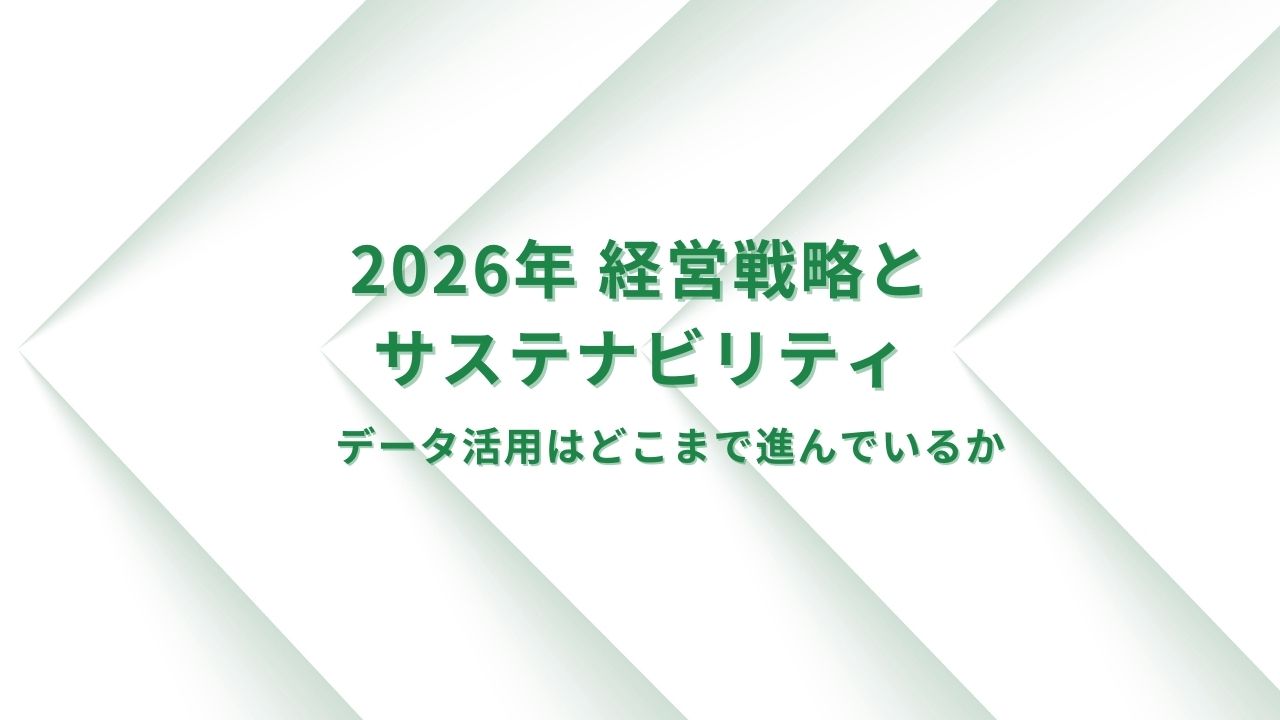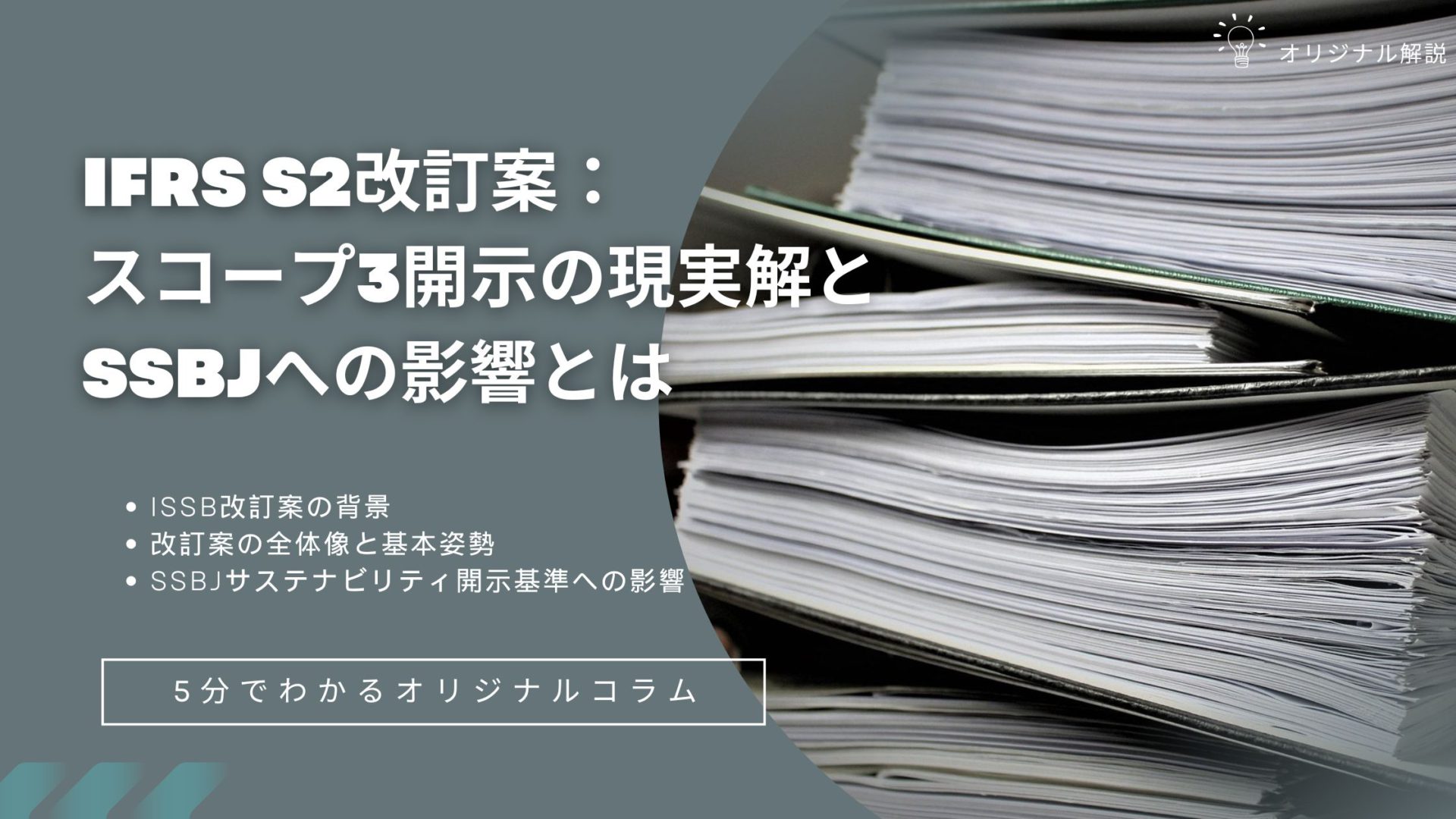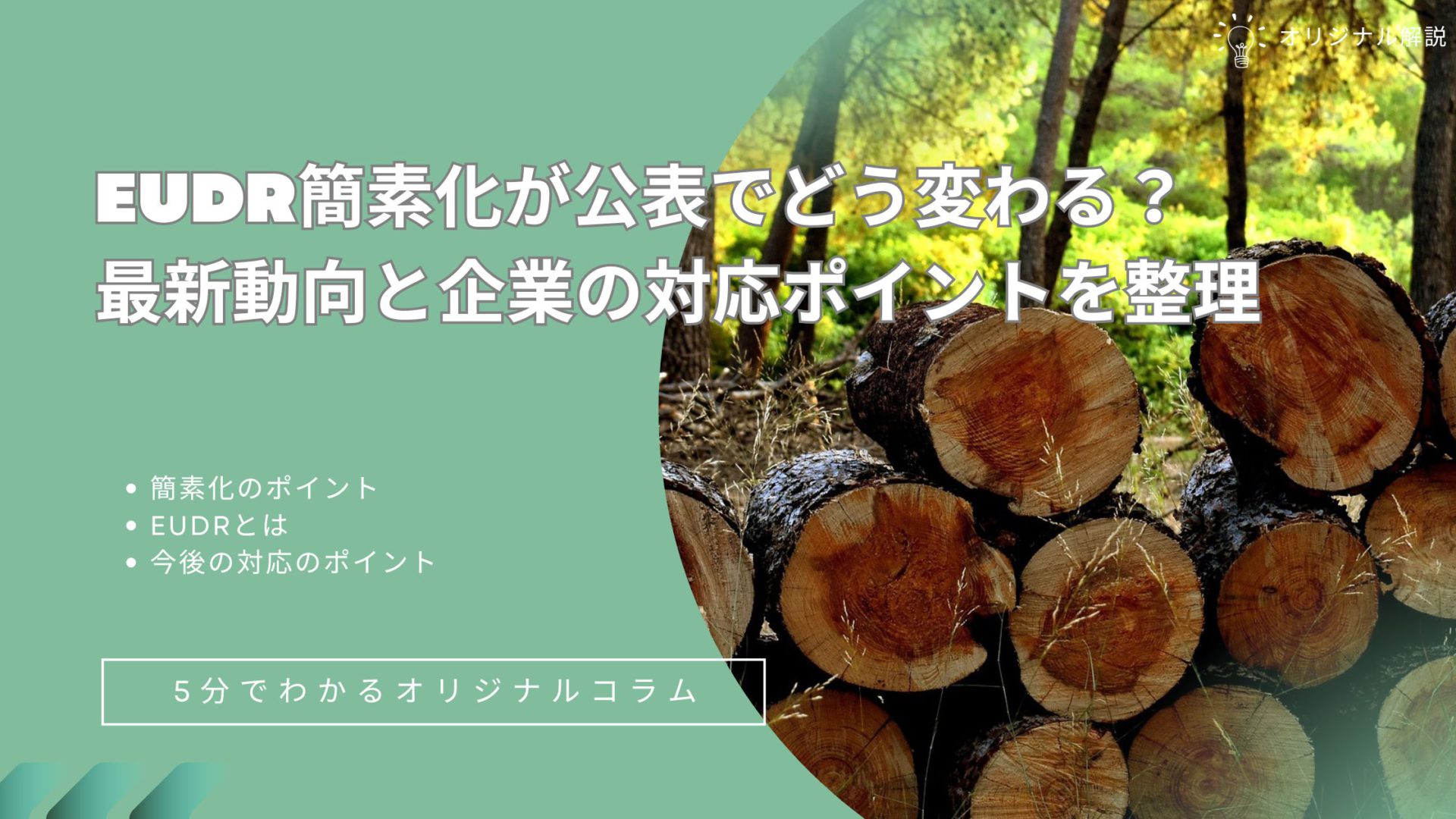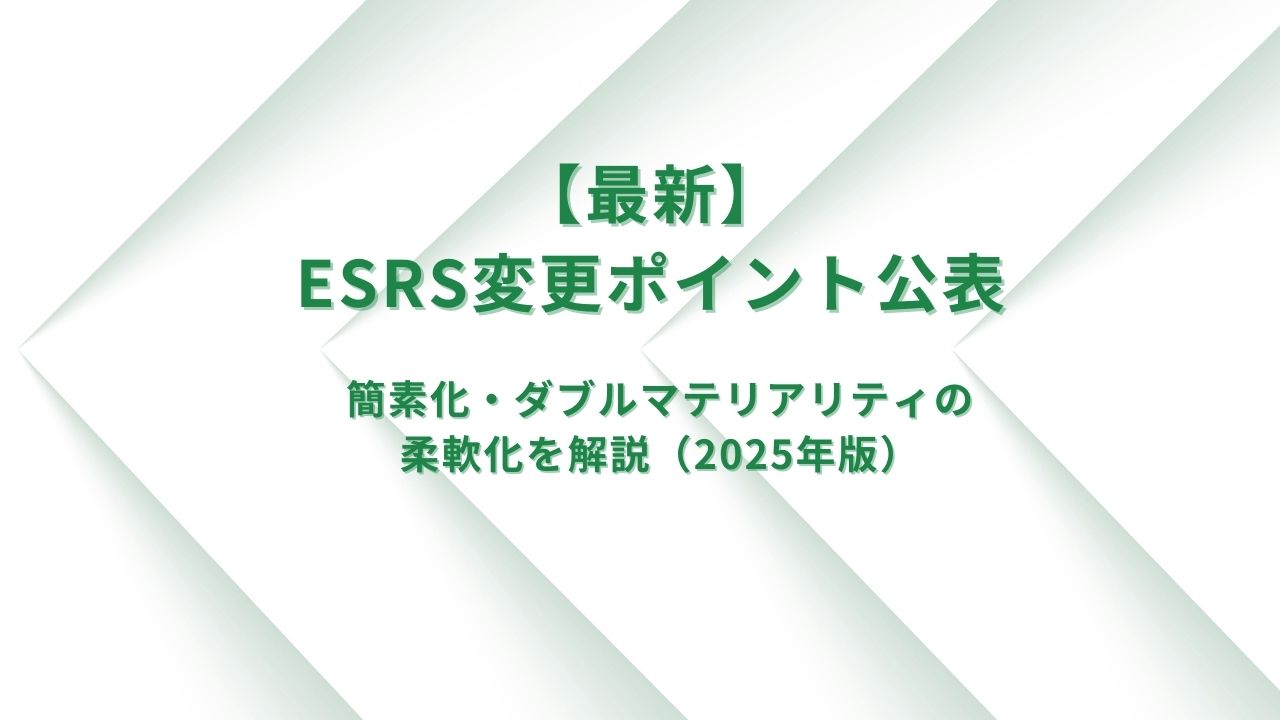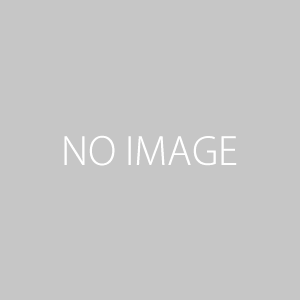SBT認定の取得が企業の間で進んでいる理由とメリットを簡潔に解説。
SBT「Science Based Targets」は、パリ協定(2015)を基準とする企業の排出削減目標であり、京都議定書の枠組みに変わる目標として国際的に注目されている。世界的にみても、SBT認定に参加を表明する企業は、2022年時点で2,500を超えており、2021年からの増加率は90%以上。国内でも200社を超える参加があり、関心が高まっている。一方で、なぜこれほどまでにSBT認定への参加(取得)が進んでいるのかメリットを詳細に把握していない場合も多いだろう。SBT認定の概要から取得までの流れおよびメリットについて紹介する。
SBTの概要
SBTとは
SBT(Science-Based Targets)は、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標の一つであり、企業の温室効果ガスの排出量が、パリ協定が求める水準と整合することを目指す。※地球温暖化を1.5°C未満に抑えるために必要な取り組みを企業に求める。
SBTは、CDP(Carbon Disclosure Project)、UNGC(United Nations Global Compact)、WRI(World Resources Institute)、WWF(World Wide Fund for Nature)の4つの機関が共同で運営されている。
SBTで注視すべきは、削減対象の排出量を「サプライチェーン排出量」に定義している点だ。サプライチェーンの排出量は、次の3つのスコープ(Scope)に分けられており、考え方はTCFDと同様な部分もある。
- Scope 1排出量:直接的な排出源からの排出(例:工場からの排ガス)。
- Scope 2排出量:電力や蒸気などの間接的な排出源からの排出(例:購入した電力の排出)。
- Scope 3排出量:サプライチェーン全体にわたる間接的な排出源からの排出(例:原材料の生産、輸送、廃棄物処理など)。
SBTは、認定制度を設けており、認定を取得することで、削減目標が科学的に妥当であることを証明することができる。対外的に削減目標の達成度を提示できるので、外部ステークホルダーや投資家に信頼性を示すことにつながるだろう。
以降のコンテンツは無料会員登録を行うと閲覧可能になります。無料会員登録を行う
すでに登録済みの方はログイン画面へ