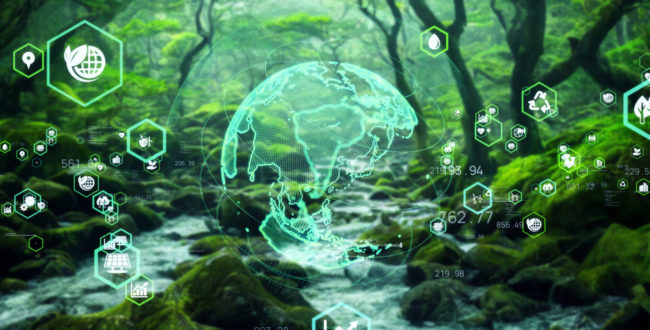ベイン、「サステナビリティ経営者ガイド2025」公表、AI活用進展も環境負荷に懸念
9月15日、経営コンサルティング大手ベイン・アンド・カンパニーは最新調査報告書「サステナビリティ経営者ガイド2025」を発表した。近年、環境・社会・ガバナンス(ESG)投資への逆風が強まっているが、企業経営者や消費者、取引先は依然としてサステナビリティへの取り組みを強化し、その活動は収益性と直結しつつあると分析した。
報告書によると、世界の産業部門における二酸化炭素(CO₂)排出量の約25%は既に「採算の取れる削減策」で対応可能とされる。エネルギー効率改善や循環型デザイン、供給網の地域化といった施策が挙げられる。さらに32%の削減レバーは中期的に利益を伴う可能性があるとした。
ベインは大手企業CEOの発言3万5000件をAIで解析。従来の「規制遵守」「倫理的責務」といった文脈から、「事業価値創出の手段」へと経営者の認識が明確に移行していると説明した。
AI利用の加速も報告書の特徴だ。約8割の経営層が「AIはサステナビリティ推進に大きな貢献を果たす」と回答し、廃棄物削減や職場安全対策などで成果を確認。ただしベインの試算では、2035年にはAIやデータセンターが年間8億1000万トンのCO₂を排出する恐れがあり、産業部門排出の17%を占める可能性がある。
企業間取引(B2B)市場ではすでに半数の購買担当者が「サステナブルな取引先を優先」としており、3年以内に3分の2に拡大する見通しだ。売上成長率で競合を上回る企業の9割は、今後3年間でサステナビリティが収益を押し上げると予測している。
消費者市場でも持続可能性は意識され続けている。ベインが世界8カ国で実施した調査では、約3割が「6種類以上の持続可能な習慣を日常的に実践」と回答し、7割が行動拡大を希望。ただし、グリーン商品の価格が依然高水準にあることや、環境影響に関する情報不足が普及の妨げとなっている。
ベインのジャン=シャルル・ファン・デン・ブランド氏は「サステナビリティを語る回数は減っているが、実行は着実に拡大している。成功する企業はすでに収益を生み出す領域を加速させ、次の変革に備えている」と述べた。
(原文)Sustainability is not dead – CEOs, consumers and B2B buyers continue to act sustainably, and tie it to business value
(日本語参考訳)持続可能性は死んでいない。CEO、消費者、B2Bバイヤーは持続可能な行動を継続し、それをビジネス価値に結び付けている。