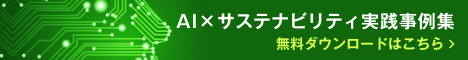ESGフロントライン:移行計画の“実行力”が企業価値を左右する時代へ
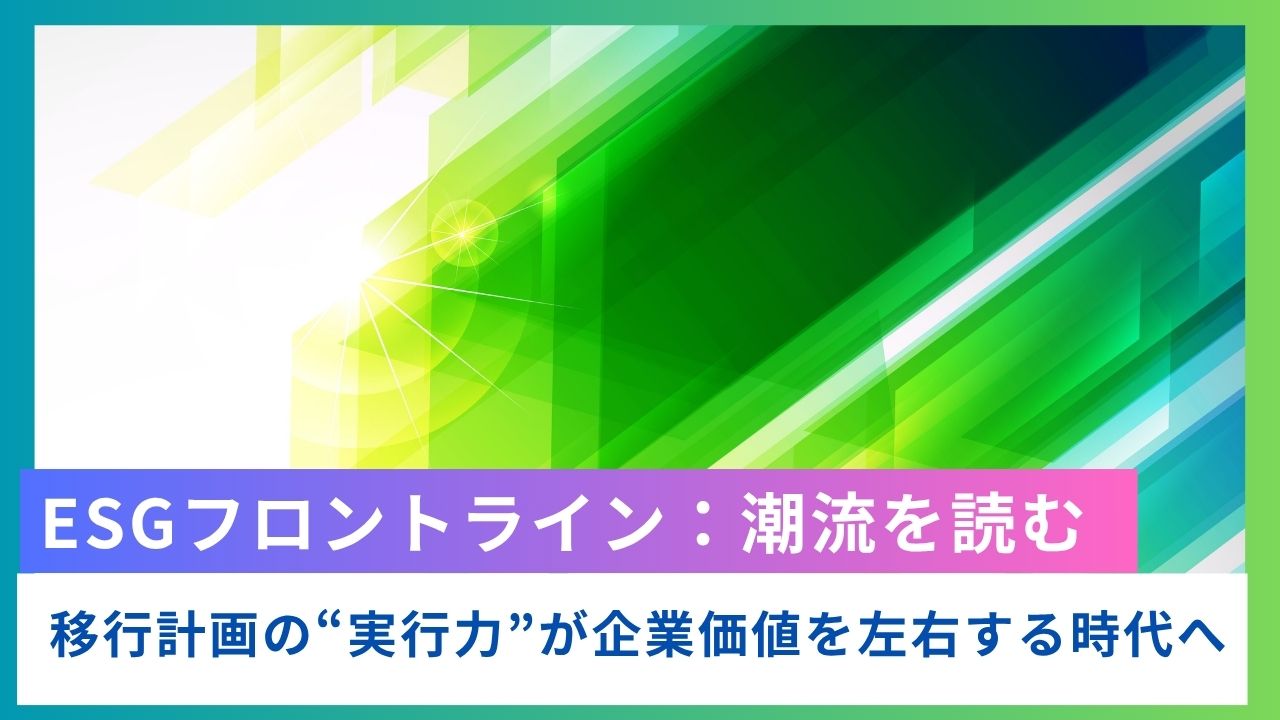
※本記事は、ESG Journal編集部が注目のニュースを取り上げ、独自の視点で考察しています。
2025年トランプ氏が大統領に再選されてから約半年。米国の政策は、気候・エネルギー分野において明確に転換を見せている。パリ協定からの再離脱の決定や「インフレ抑制法(IRA)」による支援策の見直しなど、サステナビリティ推進に対する姿勢が揺らぐなか、企業や金融機関はどう対応しているのか。本稿では、米国の動きを軸に、サステナビリティの取り組みや開示はどのように変わったのか再整理する。
トランプ大統領の動き ーサステナビリティ軽視の流れ
トランプ大統領は2025年1月20日、大統領令14162号に署名し、パリ協定からの再離脱を正式に宣言した。この動きについてAP通信は、 国際協調から距離を置く姿勢が鮮明になったと報じている。
さらに、再生可能エネルギー支援の要となっていた「インフレ抑制法(IRA)」の主要インセンティブにも大幅な見直しが加えられている。ロイターによれば、米上院は風力・太陽光に対する税制優遇措置を2028年までに段階的に廃止する案を検討しており、本来2032年までの適用を予定していた措置が前倒しされる可能性が浮上している。
同法の期限前倒し案では、建設開始から60日以内の完了を求める条件や、2028年までの稼働を義務づける条項が議論されており、ロイターはこれがすでに投資家や開発企業に対して「駆け込み着工」の動きを生んでいると伝えているが、その後の新規投資が失速する懸念が強まっている。
さらに、クリーンエネルギー支援の縮小は、電池材料などクリティカルミネラルの国内供給や製造サプライチェーンにも影響している。ロイターによると、ニッケルやレアアースといった重要資源の採掘・精錬支援も打ち切りの対象とされており、中国との競争力低下を懸念する声が上がっている。
他国にも波及する逆風
このような米国の動きにより、国際社会でも環境規制の緩和圧力が強まる可能性がある。国際的金融規制においても、バーゼル委員会や国際決済銀行(BCBS)が「金融機関における物理・移行リスクの把握」を促す枠組みを推進しているが、ロイターによれば、米国金融当局(FRBなど)はグリーン規制からの後退を進めており、温暖化リスクへの機運が後退する傾向が見られる 。この米国と欧州の温度差は、グローバルな規制の足並みにも影響することが想定される。
ただし、国際的には脱炭素や気候リスクへの対処は中長期的な潮流として根強く、安全網としての金融制度整備は進み続けている。その一例として、欧州・日本を含む多くの国では、金融機関が「移行計画の開示」を義務化しつつあり、2025年以降はTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に基づく透明性向上が進んでいる。
気候災害のコストと保険市場の限界
一方で、地球温暖化に伴う異常気象の頻発が顕著となりつつある。ロイターによると、スイス再保険(Swiss Re)の予測では、2025年における自然災害の保険支払いが1,450億ドルに達し、これは2024年比で約6%増加し、過去最高級の水準に達する見込みであると報じられた。同社のレポートは、森林火災、洪水、暴風雨などが複雑に絡み合って損害規模を拡大させている点を強調しており、実際の被害には保険未加入分も含めると、2024年には3,180億ドルにまで膨らんだと指摘している。
NRDCの報告書によると、カリフォルニア州やフロリダ州では、大手保険会社が自然災害のリスクを理由に保険料の大幅引き上げや新規契約停止を実施しており、基本的な災害保険にアクセスできない家庭が急増している。この「保険の空白(insurance gap)」は、地域経済・住宅市場・金融システム全体に連鎖的な圧力を及ぼしており、不動産担保の価値下落や銀行の資産健全性にも影響を与えるリスクが現実味を帯びてきている。
金融機関の対応――移行計画の開示が投資条件に
気候リスクへの対応が経営戦略の要件となるなか、金融機関も企業の移行計画を重視する姿勢を強めている。日本銀行のディスカッションペーパーによれば、金融機関は、企業が脱炭素社会への移行に向けてどのような目標と手段を設定しているかを、信頼性評価の重要な要素と位置付けている。
とりわけ注目すべきは、移行計画が単なる「開示義務」を超え、気候リスクに対する戦略的な取り組みの証拠として見なされている点である。調査に回答した金融機関の多くは、企業の移行計画について「脱炭素目標と実施手段との整合性」や「GHG排出量削減に向けた中間目標・定量的指標の有無」といった観点から、定性的かつ定量的な評価を行っていることが明らかにされている。
また、同ペーパーは、移行計画の開示が「気候変動に係るリスク管理の高度化と市場からの信認獲得に資する」との見解を示しており、気候対応の“見える化”が企業にとって競争力の源泉になる可能性を示唆している。つまり、移行計画の策定・開示は、もはや気候リスク対応の一環にとどまらず、資金調達・投資判断における基準の一部として組み込まれつつあるのである。
このように、持続可能な経営と信頼性の高い移行戦略が両立しているかどうかが、企業評価に直結する時代が到来している。特に今後、各国で移行計画開示の義務化が進むなかで、企業にとっては計画の整合性と実行力を裏付ける仕組みづくりが、長期的な金融アクセスの確保に不可欠となるだろう。
規制後退でも、対応は待ったなし
足元では米国をはじめ、一部の国で環境規制の緩和やクリーンエネルギー政策の後退が進みつつある。だが、それによって気候変動リスクそのものが和らぐわけではない。異常気象や災害リスクは今後も確実に拡大し、企業や金融機関の経営・資産に対する影響はむしろ深まっていくと見られる。
制度的な強制力が一時的に弱まったとしても、金融市場における気候関連リスクへの警戒は続いている。とりわけ、欧州や日本では、移行計画の開示義務化や気候情報の透明性向上が着実に進展しており、投資家や貸し手は企業の脱炭素方針と実行力を厳しく見極めるようになっている。開示が不十分な企業や、移行戦略が曖昧な企業は、資金調達の面で不利な評価を受ける可能性が高まっている。
こうした現実を踏まえれば、気候変動への対応は「規制だからやる」ものではなく、リスク管理と持続的価値創造のための戦略的取り組みであると位置づける必要がある。環境政策が揺れる局面であっても、企業が中長期視点で脱炭素に取り組み、信頼性ある移行計画を示すことが、変動の激しい社会において持続可能性と競争力を確保する鍵となるだろう。
関連オリジナル解説記事
◆進化するサステナビリティ開示 ― 傾向から考える“自社の対応状況”
◆TCFD・IFRS・CSRDの移行計画とは:業界別に考える開示ポイント
文:菅沼友音(ESG専属ライター)
【主な参考ページ】Trump signs executive order directing US withdrawal from the Paris climate agreement — again
日本銀行:気候変動関連の市場機能サーベイ(第4回)調査結果